逆流性食道炎を放っておかないで!つらい胸やけを和らげる 5つの対策法
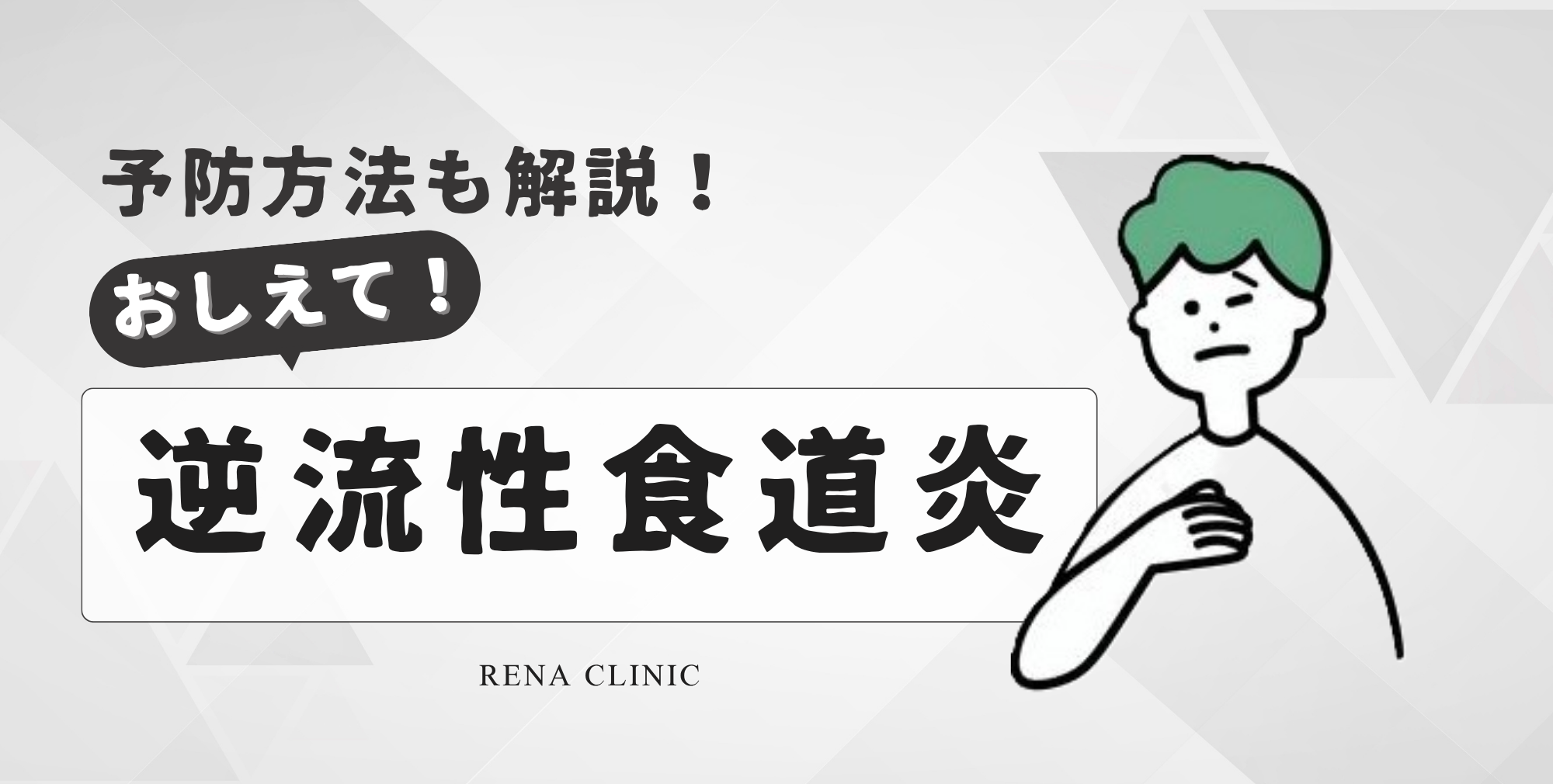
最近、食後に胸がムカムカしたり、喉に何か詰まった感じがしたりしていませんか?
もしかするとそれは「逆流性食道炎」のサインかもしれません。
症状が軽いうちは市販薬でごまかしてしまう人も多いですが、放置してしまうと慢性化したり、粘膜が傷ついてしまったりと、意外とやっかいな病気なんです。
今回は、逆流性食道炎の原因や症状、自宅でできる対策、医療機関での治療までわかりやすくご紹介します。
目次
- 逆流性食道炎とは?|仕組みと主な症状
- なぜ起きる?原因と生活習慣の関係
- 自分でできる対策|日常生活の工夫とセルフケア
- 医療機関での検査と治療法とは
- 繰り返さないための予防法と再発防止のポイント
1. 逆流性食道炎とは?|仕組みと主な症状
逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。
本来、胃と食道の間には「下部食道括約筋」という筋肉があり、逆流を防ぐ働きがあります。
しかしこの筋肉がゆるむことで、胃酸が食道に上がってきてしまい、炎症や不快な症状を引き起こします。
主な症状は以下の通りです
- 胸やけ(みぞおちから喉元にかけての焼けるような痛み)
- 呑酸(酸っぱい液が喉に上がってくる)
- のどの違和感、咳、声枯れ
- 食後や横になったときの胸の痛み
一見すると風邪や胃もたれと似ているため、見過ごされやすいのが特徴です。
しかし、慢性化すると食道粘膜がただれてしまい、「バレット食道」と呼ばれる前がん状態に進行することも。
早めに気づいて対処することが大切です。
2. なぜ起きる?原因と生活習慣の関係
逆流性食道炎は、生活習慣や体質、加齢による消化機能の低下が複合的に関与しています。
【主な原因】
- 食べすぎ・早食い:胃がいっぱいになることで、圧が上がり、胃酸が逆流しやすくなります。

- 脂っこい食事・刺激物の摂取:脂質やカフェイン、アルコールなどは、食道括約筋をゆるめてしまう作用があります。
- 喫煙:ニコチンは胃酸分泌を促進し、逆流を起こしやすくします。
- 加齢:年齢とともに筋力が衰え、胃からの逆流を防げなくなることがあります。
- 肥満・腹圧の上昇:内臓脂肪が多い人や妊娠中の女性も、胃が押されやすくなり逆流が起きやすいです
これらの習慣は、症状の悪化と深く関係しています。「ただの胸やけ」で済ませず、自分の生活を振り返ることが、症状の改善につながります。
3. 自分でできる対策|日常生活の工夫とセルフケア
逆流性食道炎の症状が軽度であれば日常生活の見直しによって改善が期待できます。
【食事編】
- 食べ過ぎない(腹八分目を意識)
- 脂っこいものや揚げ物を控える
- 刺激物(カレー、キムチ、アルコールなど)は症状がある時は避ける
- よく噛んでゆっくり食べる
【姿勢・生活編】
- 食後すぐ横にならない(最低でも30分は座って過ごす)
- 枕を少し高くする(頭を15〜20cm高くすると逆流しにくい)
- 締めつけの強い服やベルトは避ける
- 禁煙・節酒を心がける
【ストレス対策】
- ストレスは胃酸分泌を高めるため、軽い運動やリラクゼーションを取り入れることが大切です。
市販の胃薬で一時的に症状が軽くなる場合もありますが、継続して服用する前に医師の診察を受けることをおすすめします。
東京新宿レナクリニックでは、ライフスタイルに合わせたセルフケア指導も行っております。
4. 医療機関での検査と治療法とは
逆流性食道炎が疑われる場合、まずは医師の問診と診察が行われます。
症状がはっきりしていれば、薬の処方から始まることもありますが、詳しく調べるために以下の検査を行うことがあります。
【主な検査】
- 内視鏡検査(胃カメラ):食道や胃の粘膜の状態を直接確認できます。炎症や潰瘍の有無、バレット食道のチェックも可能です。
- pHモニタリング検査:食道内の酸度を24時間測定し、逆流の頻度を把握します。
- X線造影検査(バリウム):食道や胃の形状を観察する際に使われます。
【治療法】
- PPI(プロトンポンプ阻害薬):胃酸の分泌を強力に抑える薬で、現在の治療の主流です。
- H2ブロッカー:PPIに比べてマイルドな作用ですが、軽症には有効です。
- 消化管運動改善薬:胃の動きを活発にし、胃内容物をスムーズに排出させます。
これらの薬を組み合わせながら、生活指導を行い、症状の緩和と再発予防を目指します。
5. 繰り返さないための予防法と再発防止のポイント
逆流性食道炎は、一度よくなっても再発しやすい傾向があり、継続的な生活管理がとても重要です。
特に、薬で症状を抑えても、食事や姿勢などの生活習慣を見直さないままだと、再び症状が出てしまうこともあります。
【予防・再発防止のために心がけたいポイント】
- 食事の時間と内容の見直し:夕食は就寝3時間前までに済ませ、脂っこいもの、刺激の強い食品、過度なカフェインやアルコールは控えましょう。暴飲暴食を避け、腹八分目を意識することも大切です。
- 睡眠時の工夫:頭を15〜20cmほど高くして寝ると、胃酸の逆流が起きにくくなります。枕やベッドの傾斜を活用してみましょう。
- 体重管理:肥満は腹圧の上昇を招き、逆流を起こしやすくなります。特に内臓脂肪型肥満の方は要注意です。
- 服装・姿勢の見直し:締めつけの強い服やベルトは避け、猫背を改善する意識を持つことで、胃への圧力を軽減できます。
- ストレスケアと禁煙:精神的なストレスやタバコも逆流性食道炎の悪化因子。ストレスマネジメント法を取り入れるのも予防には効果的です。
また、定期的な内視鏡検査や診察を受けることも、再発防止と安心につながります。
まとめ
逆流性食道炎は、胸やけやのどの違和感など、日常生活に支障をきたす症状が多いですが、正しい知識と対策を持つことで症状の緩和や再発防止が可能です。
生活習慣の改善と医師の適切な治療を組み合わせることで、多くの方が快適な日常を取り戻しています。
症状を我慢せず、気になるときには早めの受診が大切です。東京新宿RENACLINICでは、逆流性食道炎の診断から治療・生活指導まで丁寧に対応しております。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。






