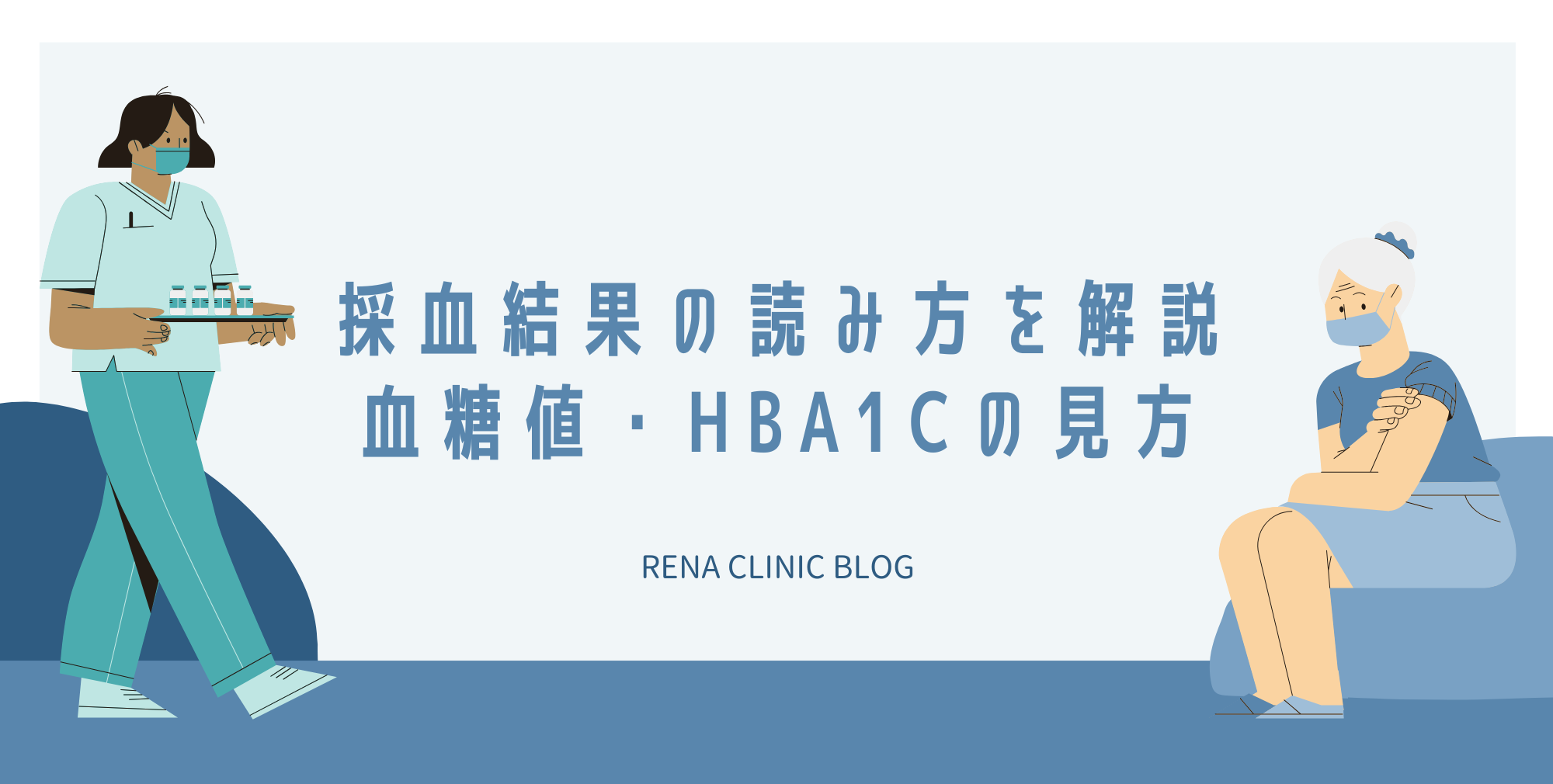
健康診断や人間ドックで採血をしたあと、「血糖値」や「HbA1c」などの項目を見て「この数値大丈夫?」と不安になる方、多いのではないでしょうか。
正常値はいくつ?高値=病気?と頭がぐるぐるしてしまいがちです。
そんな方のために、今回は“採血結果の読み取り方”にフォーカスし、血糖に関する指標である「血糖値」と「HbA1c」についてやさしく解説していきます。
東京新宿RENACLINICでは、患者さんの疑問に寄り添った診察を心がけていますので、まずはこの記事で読み取り方の基礎を押さえていきましょう。
目次
1. 血糖値とは?日々の変動と正常範囲の見方
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度を示す数値です。これはエネルギーの元になる重要な成分ですが、過剰になると体に悪影響を及ぼすことがあります。
血糖値には「空腹時血糖値」と「随時血糖値(食後など)」があり、最もよく使われるのが空腹時の値です。
空腹時血糖値の一般的な正常範囲は70〜99 mg/dLとされています。100〜125 mg/dLになると「境界型」と呼ばれる状態で、126 mg/dLを超えると糖尿病の疑いが出てきます。
ただし、検査前に何を食べたか、どのくらい時間が経っているか、ストレスや睡眠の影響なども数値に影響を与えるため、1回の値で判断するのではなく、複数回の結果や他の項目とあわせて見ることが大切です。
また、血糖値は一日の中でも大きく変動します。朝と夕方では差が出ることもあり、「自分の変動パターン」を知ることが健康管理に役立ちます。
2. HbA1cって何?1〜2ヶ月の血糖の「成績表」
HbA1cとは、過去1〜2ヶ月間の平均的な血糖の状態を示す数値です。
血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンは、血糖と結合します。この結合の割合をパーセンテージで表したものがHbA1cです。
HbA1cの正常値は4.6〜6.0%程度とされており、6.0〜6.4%は「境界型糖尿病」、6.5%以上になると糖尿病と診断される可能性があります。
この値は食事の直後や空腹時などに影響されにくいため、血糖値よりも安定した情報が得られるのが特徴です。
例えば、血糖値は正常でもHbA1cが高い場合、「普段は高血糖状態が続いている」可能性があることを意味します。
逆に、HbA1cが正常でも食後の血糖値が大きく上がるタイプの人もいます。つまり、HbA1cは「血糖の成績表」のようなもの。日々の積み重ねが現れる指標とも言えます。
東京新宿RENACLINICでは、HbA1cを重視した検査とともに、生活習慣のカウンセリングを行い、数値の意味をしっかり理解していただくよう努めています。
3. 血糖値とHbA1cをセットで読む理由と注意点
血糖値とHbA1cは、どちらも血糖の状態を知るうえで重要ですが、それぞれ意味する内容が異なります。
血糖値は一時点のスナップショット、HbA1cは長期間の平均です。そのため、一方だけを見て判断すると、誤解を招く可能性があります。
たとえば、検査当日は空腹だったり、普段よりストレスが少なかったりして、血糖値が「一時的に良い状態」だったとします。
これだけ見ると問題なさそうに思えますが、HbA1cが高かった場合、実は慢性的に血糖コントロールができていない可能性があります。
逆に、HbA1cが正常なのに血糖値が高いときもあります。これは「食後高血糖」や「夜間の血糖変動」が関係していることがあり、気づかないうちに血管へのダメージが進んでいるケースもあるのです。

血糖状態を正しく判断するには、この2つの数値を「セットで読み解く」ことが不可欠です。
東京新宿レナクリニックでは、数値の変化だけでなく、食生活や運動、ストレス状況も含めて、患者さん一人ひとりに最適なアドバイスをご提供しています。
単なる「数値の説明」にとどまらず、生活習慣とのつながりを意識したカウンセリングを大切にしています。
4. 日常生活と数値の関係:変動をどう捉えるか
採血結果の数値は、あくまで「身体の状態の目安」です。重要なのは、その数値がどのように変化しているのか、そしてその背景にどんな生活習慣があるのかを知ることです。
たとえば、同じ人が半年後に同じ検査を受けたときに、HbA1cが0.5%上がっていたとします。
このとき、「この半年間で食事の内容が変わった」「運動量が減った」「ストレスが増えた」などの要因がないかを確認することが、今後の健康維持につながります。
また、数値が基準内にあっても、「微増」や「微減」の傾向を把握することは非常に重要です。とくに血糖関連の数値は、ある日を境に急に悪化するのではなく、少しずつ変化していくことが多いからです。
東京新宿レナクリニックでは、過去の検査データと比較しながら、変動の傾向を読み取り、将来のリスクを予測したうえでアドバイスを行っています。
医師とのコミュニケーションを通じて、自分の身体の状態を“自分で理解できる”ようになることが、最大の予防策と言えるでしょう。
5. まとめ:自分の体を「数字」で知ろう
血糖値とHbA1cは、私たちの身体の状態を「見える化」してくれる大切な指標です。数字を見るだけでは一喜一憂してしまいがちですが、正しい知識をもって理解することで、健康への第一歩になります。大切なのは、一度の結果で判断せず、日々の生活とのつながりを意識して変化を見ていくことです。東京新宿レナクリニックでは、血糖値の測定タイミングや生活習慣に応じて、個別にアドバイスを行っています。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。





