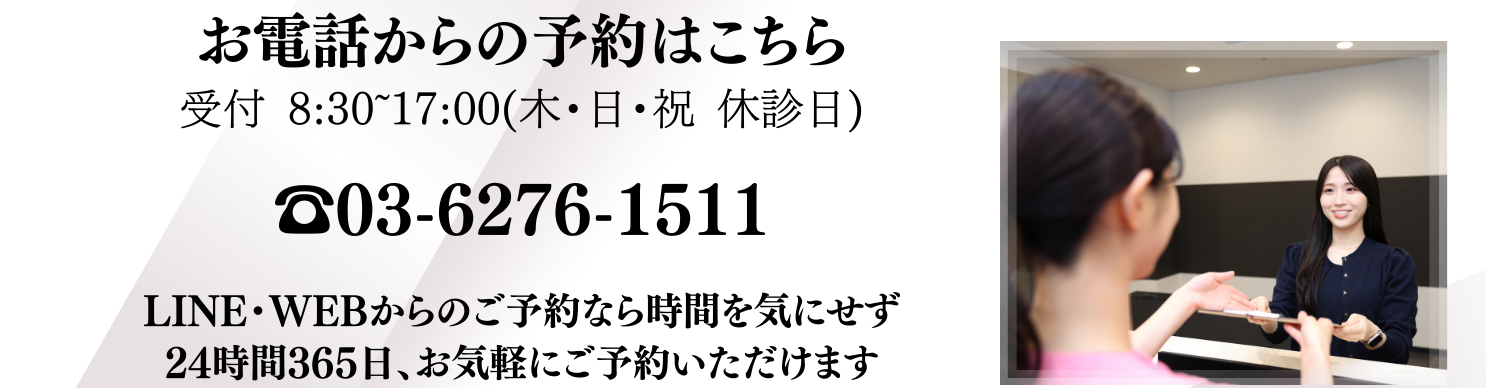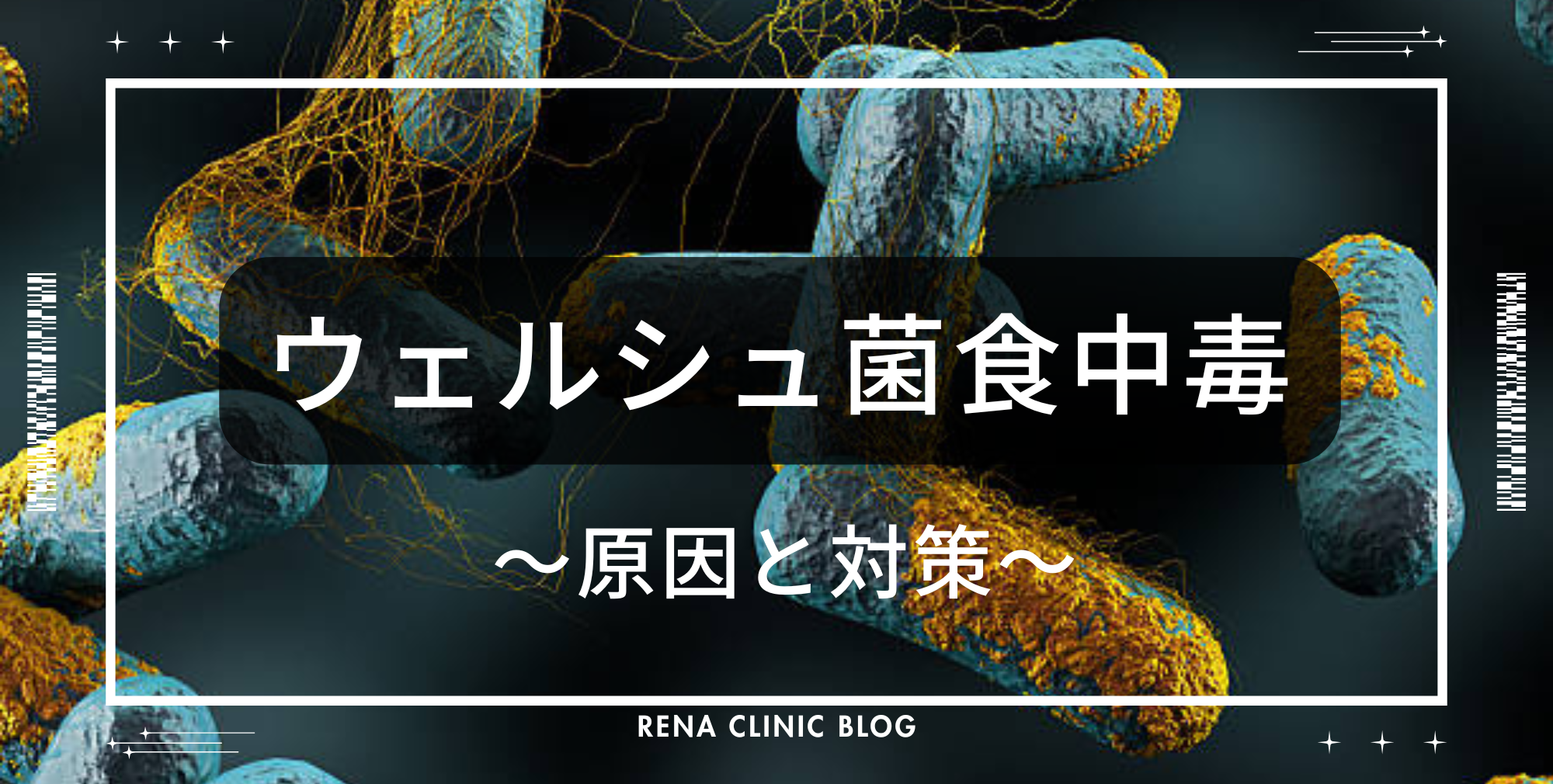
「カレーは一晩寝かせると美味しいって聞いたからやってみたけど…なんかお腹の調子が悪いな」
——それ、ウェルシュ菌が原因の食中毒かもしれません。
あまり聞き慣れないかもしれませんが、実は日本国内でも非常に多い食中毒の原因菌なんです。
特に大量調理・作り置き・常温放置は危険度アップ。家庭でも外食でも油断は禁物です。
今回はそんなウェルシュ菌の正体や症状、予防方法まで、わかりやすくお話していきます!
目次
1. ウェルシュ菌とは?|どこにいて、なぜ食中毒を起こすのか
ウェルシュ菌(学名:Clostridium perfringens)は、自然界や人・動物の腸内、土壌、水、ほこりなど、どこにでも存在する嫌気性の細菌です。

特に、酸素の少ない環境で増殖するため、「煮込み料理の底」「大量調理の大鍋」「密閉した保存容器」などが格好の住処になります。
また、この菌は芽胞(がほう)と呼ばれる耐久性の高い形に変化し、加熱や乾燥に強くなるのが特徴です。
たとえ中心温度が75℃を超えても、芽胞は生き残り、再び増殖するチャンスをうかがっています。
つまり、一度加熱した料理でも常温放置してしまうと再び菌が増殖してしまうのです。
特にリスクが高いのは、カレー、シチュー、煮物、炒め物、炊き込みご飯、チャーハンなど、一度にたくさん作る料理。
家庭だけでなく、学校や福祉施設、飲食店などでも集団食中毒が報告されています。
2. 主な症状と特徴|他の食中毒とどう違う?
ウェルシュ菌による食中毒は、他の菌による食中毒と比べて症状が軽めで見逃されやすい傾向にあります。しかし、症状が軽いからといって安心してはいけません。
主な症状は以下の通りです:
- 腹痛(下腹部中心)
- 水様性の下痢
- 軽度の吐き気やおう吐(まれ)
- 発熱はほとんどなし
発症のタイミングは、汚染された食品を食べてから6〜18時間程度。多くの場合、突然の腹痛と下痢で始まり、1〜2日で自然に回復します。
ただし、高齢者や子ども、持病のある方では脱水などを引き起こす可能性もあるため、症状が強い場合や長引くときは注意が必要です。
また、ウェルシュ菌の特徴は、体内で「腸管毒素(エンテロトキシン)」を産生すること。この毒素が腸を刺激し、腹痛や下痢を引き起こします。
下痢止めなどで腸の動きを抑えてしまうと、毒素が体内にとどまってしまい、症状が悪化する場合もあるので、市販薬の自己判断使用は控えましょう。
3. 診断と治療のポイント|受診の目安は?
ウェルシュ菌食中毒は、症状だけではなかなか特定しにくいため、医師による問診と、必要に応じて便検査などが行われます。
特に、同時期に同じ食事をした人たちに同様の症状が出ている場合、この菌の可能性が高まります。
治療の基本は自然治癒を促すサポートです。脱水予防のため、経口補水液などで水分をしっかり補給しながら安静に過ごすのが基本です。
抗生物質は基本的に使わず、症状が重い場合を除いては整腸剤や電解質補給などでの対応になります。
では、どのタイミングで受診すべきか?以下のような場合は医療機関を受診しましょう。
- 強い腹痛や水様性の下痢が1日以上続く
- 吐き気やおう吐が止まらない
- 発熱がある
- 食後に家族や同居者も同じ症状を訴えている
- 脱水症状(口の渇き、尿が出ない、フラつきなど)が見られる
東京新宿RENACLINICでは、ウェルシュ菌を含む各種食中毒の診断と対応を行っています。
受診の際は、「何をいつ食べたか」「症状が出たタイミング」などをメモしておくとスムーズです。
早めの受診で、体調悪化を防ぎましょう。
4. 予防の基本は加熱と保存|家庭・飲食店での注意点
ウェルシュ菌の予防は、「加熱」と「冷却」がカギになります。
この菌は熱に強い「芽胞」を作るため、加熱した後の保存方法が最も重要です。
まず、作った料理は「できるだけ早く冷却」すること。室温で長時間放置すると、芽胞が復活し、菌が急増してしまいます。大量調理時は以下のような工夫が効果的です:
- 鍋のまま放置せず、浅い容器に移して冷ます
- 氷水や冷蔵庫で素早く冷却する
- 常温保存は2時間以内を目安に
再加熱の際も、全体がしっかり熱くなるように加熱しましょう。電子レンジの加熱ムラにも注意です。
また、飲食店や給食施設などでも、同様の管理が求められます。大量調理をする場では「HACCP(ハサップ)」に基づく衛生管理が重要です。
家庭でも、特に夏場や梅雨時期は食中毒リスクが高まります。「とりあえずラップをして置いておく」「夜までそのまま放置」など、ついやりがちな行動が食中毒を招くので注意しましょう。
5. まとめ|おいしい食事を安全に楽しむために
ウェルシュ菌は、私たちの身の回りに広く存在しており、誰でも感染する可能性がある食中毒です。
特に、「加熱すれば安全」と思いがちな料理こそ、保存方法や再加熱の工夫が重要です。
一見軽い症状でも、日常生活や仕事に大きな支障をきたすこともあるため、違和感があれば早めの受診を心がけましょう。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。