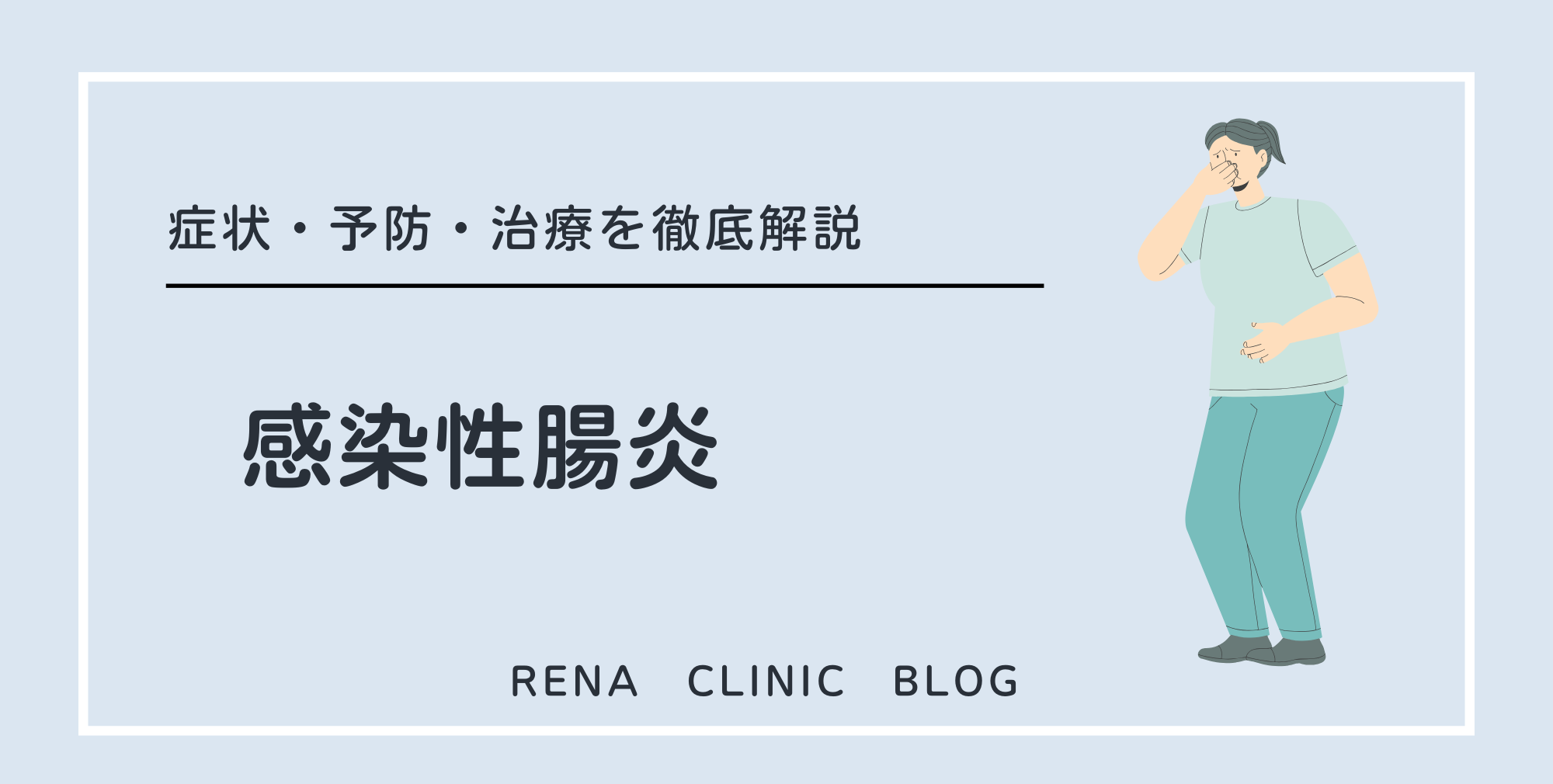
お腹の調子が悪くて「ちょっと食べすぎかな?」と思っていたら、吐き気や下痢が止まらない…そんな経験はありませんか?
実はそれ、「感染性腸炎」かもしれません。気づかずに過ごして悪化してしまうケースも多く、特に季節の変わり目や流行期には注意が必要です。
この記事では、感染性腸炎の原因から症状、治療、予防法までを分かりやすく解説していきます。東京新宿レナクリニックでも日々相談が多い疾患の一つ。
しっかり知識を身につけて、いざというときに焦らず対応できるようにしましょう!
1. 感染性腸炎とは?
感染性腸炎は、ウイルス・細菌・寄生虫などの病原体によって腸が炎症を起こす疾患です。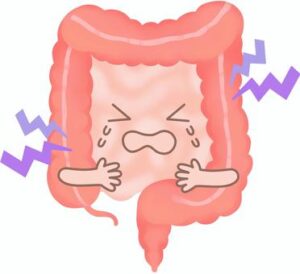
誰でもかかる可能性があり、乳幼児や高齢者は特に重症化しやすいとされています。
主に「ウイルス性腸炎」と「細菌性腸炎」に分かれ、ウイルス性ではノロウイルスやロタウイルス、細菌性ではサルモネラ菌やカンピロバクターが有名です。
これらは食事や接触など日常の中で簡単に感染してしまいます。
また、症状の現れ方も異なり、ウイルス性は突然の嘔吐や水様性下痢が中心なのに対し、細菌性は血便や高熱が出ることがあります。
いずれにせよ、放置すると脱水や合併症につながるため、早期の対応が肝心です。
2. 主な原因と流行の季節性
感染性腸炎の原因となる病原体は、季節によって特徴的な傾向があります。
冬にはノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが流行し、夏にはカンピロバクターや腸炎ビブリオなどの細菌が多くみられます。
ウイルス性は「接触感染」が多く、家庭や施設内での集団感染が起きやすいです。
細菌性は「食中毒」として発生することが多く、特に加熱不足の鶏肉や魚介類が原因になるケースが多数です。
また、井戸水や生野菜、衛生状態の悪い地域での飲食などから、寄生虫感染を起こす場合もあります。
旅行中や出張先で体調を崩す人も少なくありません。
3. 症状・診断・治療の進め方
感染性腸炎の代表的な症状は、腹痛・下痢・嘔吐・発熱です。ウイルス性では急に吐き気が始まり、続いて水のような下痢が出ることが多いです。
細菌性では、血便や強い腹痛、38℃以上の高熱を伴う場合もあります。
医師による診断では、食事内容、発症時期、周囲の感染の有無などを詳しく聞き取る問診が重要になります。
必要に応じて、便の検査や血液検査が行われ、病原体の特定や重症度の判断に役立ちます。
治療の基本は「安静」と「水分補給」です。ウイルス性の場合、多くは自然に回復しますが、下痢や嘔吐が続くと脱水症状を起こす危険がありますので、経口補水液(OS-1など)の摂取がすすめられます。細菌性の場合、抗生物質が必要になることもありますが、自己判断で市販薬を飲むと症状が悪化する場合があるので注意が必要です。
東京新宿RENACLINICでは、症状に応じた治療方針をご提案し、必要な薬やサポートを丁寧にご案内しております。安心してご相談ください。
4. 自宅療養時の注意点と生活管理
感染性腸炎と診断されたら、無理に動かず安静を保つことが第一です。
脱水を防ぐためには、こまめな水分補給が必須ですが、飲み物を一気に摂ると吐き戻すこともあるので、少量ずつゆっくり摂取しましょう。
食事は消化の良いお粥やうどん、具なしスープなどから始め、症状が落ち着いてから徐々に通常食に戻します。脂っこいものや冷たい飲食物、アルコールは厳禁です。
また、家庭内での感染拡大を防ぐため、タオルや食器の共用を避け、トイレ後や調理前の手洗いを徹底しましょう。
特にノロウイルスなどは感染力が非常に強く、排便後もウイルスが残っている場合があります。
子どもや高齢者は重症化しやすいため、少しでも「おかしい」と思ったら、早めに医療機関を受診してください。
5. 感染予防のポイント/まとめ
感染性腸炎を予防するためには、日常の衛生管理がとても重要です。
外出後やトイレ後、調理前の「手洗い」は基本中の基本。特に指先や爪の間、手首までしっかりと洗いましょう。
食品についても、魚介類や鶏肉はしっかり加熱し、生野菜は流水でよく洗うこと。お弁当や作り置きの食品は、常温放置を避けましょう。夏場は特に注意が必要です。
さらに、嘔吐物や便の処理は使い捨て手袋やマスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤で代用可)で適切に消毒することが大切です。
まとめ
感染性腸炎は、ウイルスや細菌によって引き起こされる身近な病気ですが、適切な対応をしないと重症化することもあります。特に冬場のウイルス、夏場の細菌による腸炎は患者数が増加しやすいため、早めの判断と行動がカギとなります。
症状が軽いからと放っておかず、正しい診断と対処で早期回復を目指しましょう。日常の予防も欠かせません。東京新宿レナクリニックでは、一人ひとりの症状や生活背景に寄り添いながら、丁寧な診察とサポートを行っております。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。





