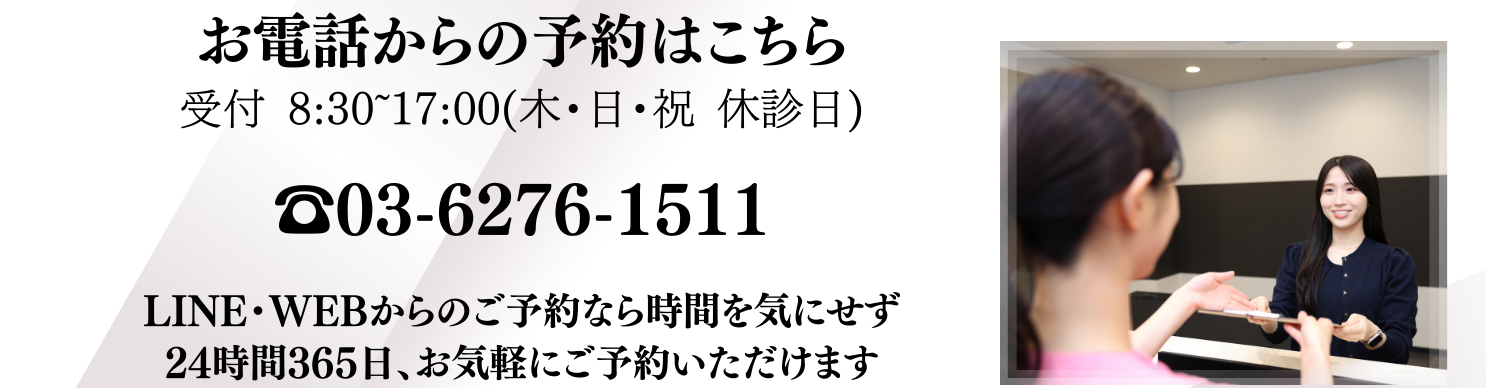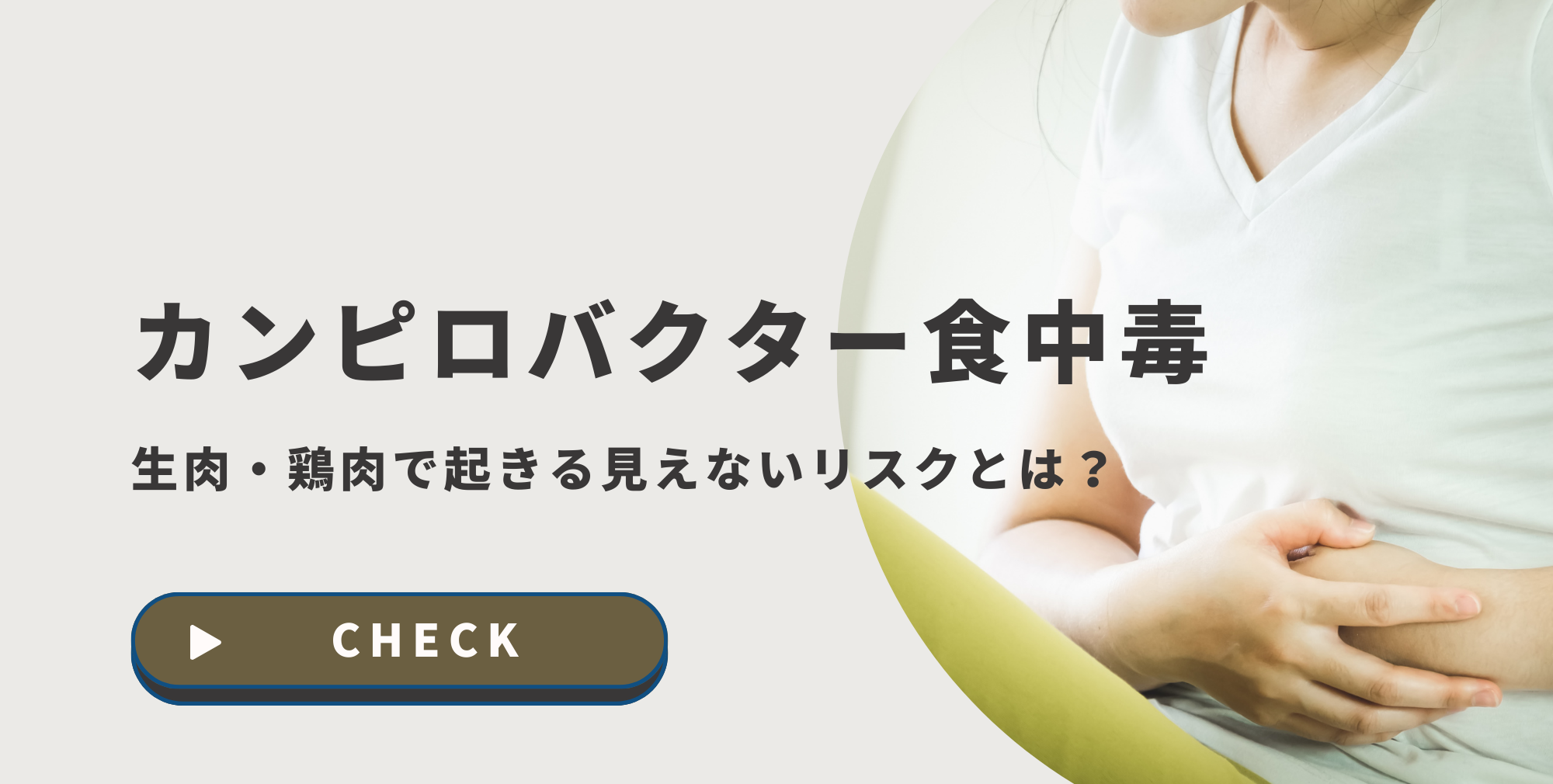
「昨日の焼き鳥、ちょっとレアだったけどおいしかったな〜」…なんて翌日にお腹がキリキリ痛み出す。
しかも下痢や熱まで。実はそれ、「カンピロバクター食中毒」かもしれません。
生焼けの鶏肉などを食べることで発症するこの病気は、毎年かなりの件数が報告されていて、特に夏場に多いのが特徴です。
しかも、腹痛がしつこく続いたり、重大な合併症を引き起こすこともあるので、甘く見てはいけません。
東京新宿レナクリニックでも、実際に「カンピロバクターかも?」と相談に来られる方は少なくありません。しっかり知って、食事の安心・安全を守りましょう!
1. カンピロバクターって何?原因と感染ルート
カンピロバクターは、動物の腸管内に生息する細菌の一種で、特に鶏や牛、豚などの家畜が保菌しています。
日本では、鶏肉が最も一般的な感染源となっており、「生焼けの鶏肉を食べた」「鶏刺しを食べた」という人が発症するケースが多いです。
この菌は加熱に弱く、中心温度が75℃で1分以上加熱すれば死滅しますが、表面だけを軽く炙っただけの肉や、内部まで火が通っていない調理法では菌が残ってしまいます。
また、まな板や包丁、手指などを介した「二次汚染」も非常に多く、鶏肉を切ったまな板で野菜を切ってしまった、なんていう場合にも感染のリスクがあります。
特に注意すべきは、菌の量が非常に少なくても感染してしまう点です。ほんの数百個の菌でも発症するため、「少しだから大丈夫」という油断が食中毒を引き起こすことになります。
2. 主な症状と発症のタイミング
カンピロバクター食中毒の特徴的な症状は、腹痛・下痢・発熱・吐き気など、いわゆる「胃腸炎」のような症状です。
ただし、この菌のやっかいなところは、感染してすぐに症状が出るわけではない点です。
多くの場合、感染後1〜7日程度の潜伏期間を経てから発症します。そのため、「食事から時間が経ってるから違うだろう」と自己判断してしまい、適切な治療が遅れることがあります。
また、便は水様便で、血便が出ることもあり、腹痛は強い場合が多いです。
発熱は38度前後まで上がることもありますが、微熱程度で済むこともあります。
大人よりも子どもや高齢者のほうが重症化しやすく、脱水症状などにも注意が必要です。
さらに、一部の人は感染後1〜3週間ほどしてから「ギラン・バレー症候群」という神経系の合併症を引き起こすことがあり、まれではあるものの、見逃せないリスクです。
3. 治療方法と受診の目安
カンピロバクターによる食中毒は、基本的には自然回復することが多く、軽症であれば水分補給と安静によって数日で回復することがほとんどです。
しかし、症状が強い場合や長引くときは、医療機関での適切な処置が必要になります。
まず重要なのは「脱水の予防」です。下痢や発熱が続くと、体内の水分と電解質が失われるため、経口補水液(OS-1など)をこまめに摂取することがすすめられます。
嘔吐が強くて飲めない場合や、排尿が減っているようであれば、点滴などが必要なこともあります。
抗菌薬は、症状が重い場合や免疫力の低い方には処方されることがありますが、自己判断での服薬は絶対に避けてください。
また、市販の下痢止めはかえって症状を悪化させる恐れがあるため、使用は控えましょう。
受診の目安としては、「下痢が1日以上続いている」「血便が出ている」「高熱が出ている」「嘔吐が止まらない」などが挙げられます。
東京新宿RENACLINICでは、症状の重症度や体力状況をしっかり見極め、必要な処置を丁寧に行っています。「様子見で大丈夫かな?」と迷ったときは、お気軽にご相談ください。
4. 予防のコツ|調理と外食で気をつけたいこと
カンピロバクターを防ぐためには、何よりも「しっかり加熱」と「衛生管理」が大切です。鶏肉は必ず中心部まで火を通し、ピンク色の部分が残らないように調理しましょう。
焼き鳥や唐揚げなどでも、「見た目で判断しない」ことが重要です。
調理器具の使い分けも基本です。生肉を切った包丁やまな板は、使い終わったらすぐに洗浄・消毒を。
できれば肉用と野菜用で器具を分けておくと安心です。手洗いも忘れずに、調理前・調理中・調理後の3段階で行うとより効果的です。
外食時も注意が必要です。特に居酒屋や焼き鳥店などで「鶏刺し」「たたき」「半生」の表記がある場合は、リスクがあることを理解したうえで判断しましょう。
安全な調理法を選ぶのも、体を守る大切な意識です。
また、お子さまや高齢の方、妊娠中の方は免疫力が下がっている場合があるため、特に注意が必要です。
東京新宿レナクリニックでは、こうした予防対策についてのアドバイスも積極的に行っています。安全な食生活を送るための疑問や不安は、いつでもご相談ください。
5. まとめ|美味しく安全な食卓を守るために
カンピロバクターは「身近なリスク」である一方で、正しい知識と対策があれば十分に予防できます。
おいしい鶏肉を安全に楽しむためにも、日々の調理や食事の選び方にはひと工夫が大切です。
腹痛や下痢が続く場合、「食べたものが原因かも?」と疑ってみることも健康を守る第一歩。
東京新宿RENACLINICでは、カンピロバクターをはじめとする感染性胃腸炎の診療・予防指導に力を入れております。
お腹の不調や気になる症状がある際は、どうぞお気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。