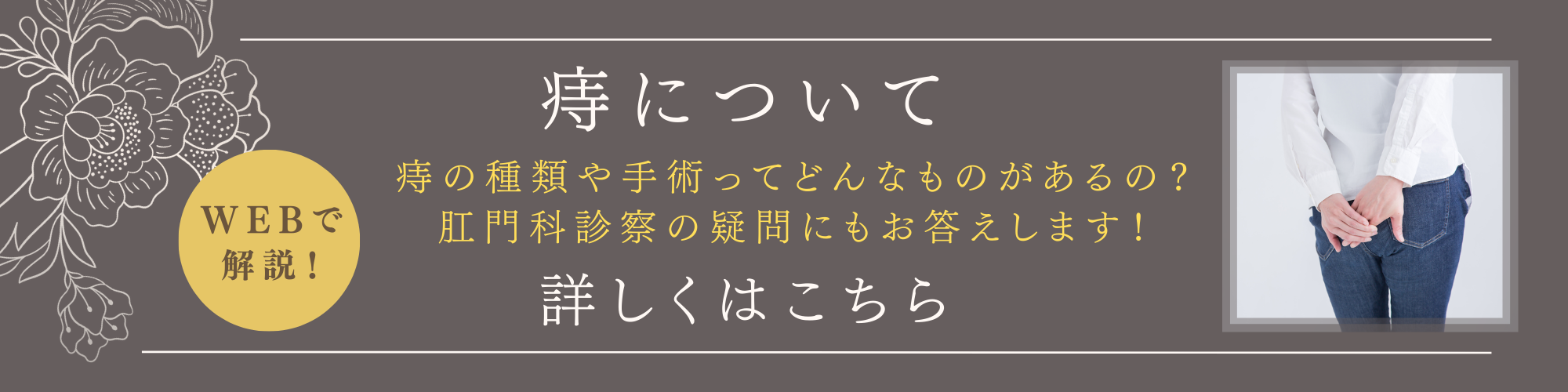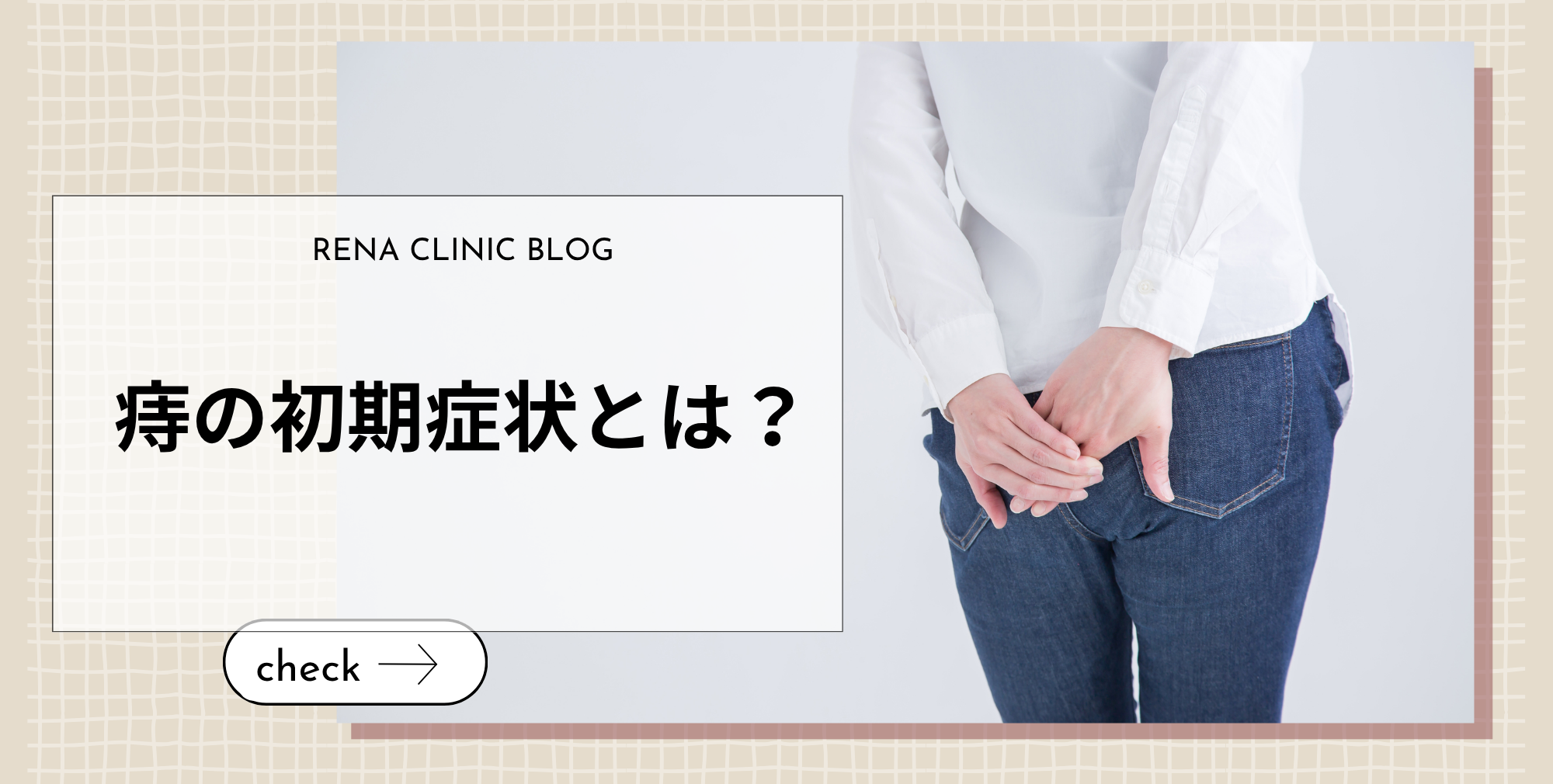
トイレでおしりを拭いたら、トイレットペーパーにほんの少し血が…「大丈夫かな?」と思いつつ、様子を見てしまうこと、ありませんか?
出血が少なければ「切れただけ」「ちょっと硬い便のせいかな」で終わらせがち。
でも、それが“痔”の初期症状かもしれませんし、まれに他の病気のサインである可能性も含んでいます。
初期なら治療も比較的負担が軽く済むことが多く、放っておくと出血が増えたり痛みが出たり、治りにくくなることも。
東京新宿レナクリニックでは、こうした「出血・初期ステージ」こそ早く気づくことの大切さを伝えたいと思っています。まずは“どんな出血なら痔?”を一緒に整理してみましょう。
目次
1. 痔とは何か?種類と構造の基礎知識
痔とは、「肛門部および直腸下部」に存在する静脈の血管クッション(肛門静脈叢など)が何らかの原因で腫れたり、炎症を起こしたりする状態を指します。
大きく分けると「内痔核(いぼ痔)」と「外痔核」、さらには裂肛(きれ痔/肛門の皮膚や粘膜が裂ける状態)が代表的な種類です。
- 内痔核:肛門の内側、歯状線より上側の粘膜下にできるタイプ。痛みを伴いにくく、「出血」「脱出感」「粘液が出る」などの症状が出ることがあります。
- 外痔核:肛門の入口近く、皮膚表面または直下にできるため、痛み・腫れ・触るとしこりがあることがあります。出血だけでなく、強い痛みを伴うことが多いです。
- 裂肛(切れ痔):硬い便や便秘などで排便時に肛門の壁(皮膚/粘膜)が切れてしまう状態。出血とともに鋭い痛みが特徴です。
これら痔の発生要因としては、便秘・硬い便・長時間座ること・いきみの習慣・妊娠や出産・肛門に負荷がかかる生活様式・下痢などが挙げられます。
肛門周囲の血液の流れが悪くなること、静脈のクッションの支持組織が弱くなることも関係しています。
初期段階では「ちょっと血が付く」「軽い違和感がある」など、軽い症状が中心です。
この段階で気づけば、軟膏・坐剤・生活改善で比較的簡単に改善することが多くなります。
2. 初期の出血サイン:見た目・タイミングでわかること
痔の初期段階での出血には、特徴的なパターンがあります。見た目(血の色や場所)、出るタイミング、痛みの有無などをよく観察することで、「痔かもしれない」と感じるサインがつかめます。
血の色・量・出る場所
- 血が鮮やかな赤色で、便器にポタポタ落ちる・トイレットペーパーに付く程度 → 肛門近くからの出血、典型的な痔(特に内痔核か裂肛)に多い。ただし直腸などの可能性もある。
- 黒っぽい・暗赤色・タール状の便になる → 出血が消化管を通って時間や場所を経ている可能性。肛門より奥、大腸・胃腸系の問題の可能性を考える必要あり。
出血のタイミング・頻度
- 排便時または直後のみ → 硬い便やいきみが関与しているケースが多い。初期の痔や切れ痔によく見られる。
- 出血が断続的に続く・トイレットペーパーにいつも付く・便を拭いたときに毎回少し血が付くような状態 → 初期でも軽症ではない可能性あり。放置せずチェックを。
痛み・その他の症状の有無
これらのサインをよく観察することで、自分が「ただの硬い便の影響か」「痔初期か」「もっと注意が必要な状態か」の判断がしやすくなります。
ですが、自分だけで判断しきれないことも多いので、専門医の意見を仰ぎましょう。
3. 出血がある痔と「他の原因(大腸や直腸等)」との見分け方
出血がお尻からあるとき、「痔だけ」の可能性が高いケースと、「それ以外(大腸ポリープ・大腸癌・炎症性腸疾患など)」が関与している可能性があるケースがあります。
ただし、あくまで痔の可能性が高いということであって、直腸を含めた大腸の疾患の否定が非常に重要ですので、そこを忘れてはいけません。
痔が原因と思われるケースの特徴
- 出血が鮮やかな赤色で、便を拭いたときやトイレットペーパーに付く程度である
 排便後に少し出るが、出血が続くことはなく、量も多くない
排便後に少し出るが、出血が続くことはなく、量も多くない- 痛みやかゆみ、肛門の違和感があるが発熱・体重減少・便の形の変化など全身症状はない
- 便秘・硬い便・長時間の座位・いきむ習慣など明らかな誘因がある
他の原因が疑われるサイン
- 血便が暗赤色・便と混ざっている・タール便のような黒い便になっている
- 出血量が増加してきている・断続的かつ頻繁に出血する
- 排便習慣の変化(便秘と下痢を繰り返したり、便の形が細くなるなど)
- 体重減少・疲れやすさ・貧血症状がある・腹痛がある・発熱・腹部の膨満感など伴う
東京新宿RENACLINICでは、出血がある場合には「痔の可能性が高いか」「他の疾患の可能性が否定できるか」を最初の診察で見極め、必要に応じて大腸内視鏡検査もご提案し、安心して受診していただける体制を整えています。
4. 初期の治療・ケア方法:薬・生活習慣の見直しなど
痔の出血が初期で、まだ痛みが軽い・症状が軽度である段階では、薬物療法と生活習慣の改善での軽快が期待できます。
薬物療法
- 軟膏・坐剤:炎症を抑える薬や血管を収縮させる成分を含む製剤。出血・出血後の粘膜の修復を促すもの。痛みやかゆみがある場合は局所麻酔成分の入ったものが有効なこともあります。
- 抗炎症薬・止血薬:内服薬での補助的治療。必要に応じて使われることがあります。
生活習慣の改善
- 便秘対策:十分な水分摂取・食物繊維豊富な食事(野菜・果物・全粒粉等)を取り入れる。便を硬くしないことが重要。
- 排便習慣の改善:我慢しない、便意があったらすぐに行くこと。トイレでの長居を避ける。いきみすぎない。柔らかくするための便の調整。
- お尻に負担をかけない生活:長時間座ることを避ける、重いものを持つ時に腹圧をかけない、入浴・温浴で血行を促すなど。
ローカルケア
- 座浴:ぬるめのお湯で肛門周りを温めて血行を良くし、炎症・痛みを和らげる。
- 清潔保持:排便後の拭き方(刺激を与えないように優しく)、下着の選び方など、清潔で乾燥した環境を保つ。
規則的な経過観察
- 出血が改善するかどうかを記録(トイレットペーパーに付く・頻度・量など)
- 痛みの増減・他の症状の有無をチェック
5. 出血が続くときの注意点と受診のタイミング
痔の初期の出血がある程度軽ければ自宅ケアで改善することも多いですが、「いつまでも続く」「変化がある」なら早めに受診する方が安心です。
注意すべき変化・赤信号
- 出血の量が増えてきている
- 出血が頻繁になった・止まらない
- 血が暗くなってきた・便と混ざっている
- 排便習慣の大きな変化(便秘と下痢を交互に繰り返す・便が細くなるなど)
- 全身症状(貧血・体重減少・だるさなど)が出る
- 痛みが強くなっている・腫れ・発熱など炎症を思わせる兆候
受診のタイミング
- 初めて出血を見たとき、少しでも不安なら
- 出血が2〜3回繰り返したり、1週間以上続いたとき
- 出血以外の症状が出てきたとき(痛み・便の異常・体調の変化など)
診察で期待できること
- 視診・触診・肛門鏡で痔核・裂肛など肛門障害を調べる
- 臨床的に必要であれば大腸内視鏡などで精密に調べる
まとめ
おしりからの出血があると驚いてしまいますが、「トイレで少し血が付いた」「拭いたら赤い線が見えた」などの初期のサインは見逃さないことが非常に重要です。
痔の初期であれば、保存療法・生活習慣の見直しなどで改善できる可能性があります。
その一方で、出血が暗い色になったり、頻度や量が増えたり、体調の変化が伴ったりする場合は、痔以外の原因を含めて検査が必要です。
迷いや不安があれば、自分で判断せずに専門医に相談されることをおすすめします。
東京新宿RENACLINICでは、早期の出血サインを見逃さず、患者さんに合った治療プランとサポートを提供しています。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。
引用論文
- Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids
著者:Ho YH, Seow‑Choen F 他 PubMed
雑誌名:British Journal of Surgery PubMed - The efficacy of Aescin combined with MPFF for early control of bleeding from acute hemorrhoids, a randomized controlled trial
著者:Witcha Vipudhamorn, Suwan Sanmee 他 サイエンスダイレクト+1
雑誌名:Asian Journal of Surgery サイエンスダイレクト - An optimal painless treatment for early hemorrhoids; our experience in Government Medical College and Hospital
著者:著者不特記(India の医療機関のチーム) PubMed
雑誌名:International Journal of Surgery or類似の外科学会誌(Outpatient non‑surgical ambulatory study) PubMed