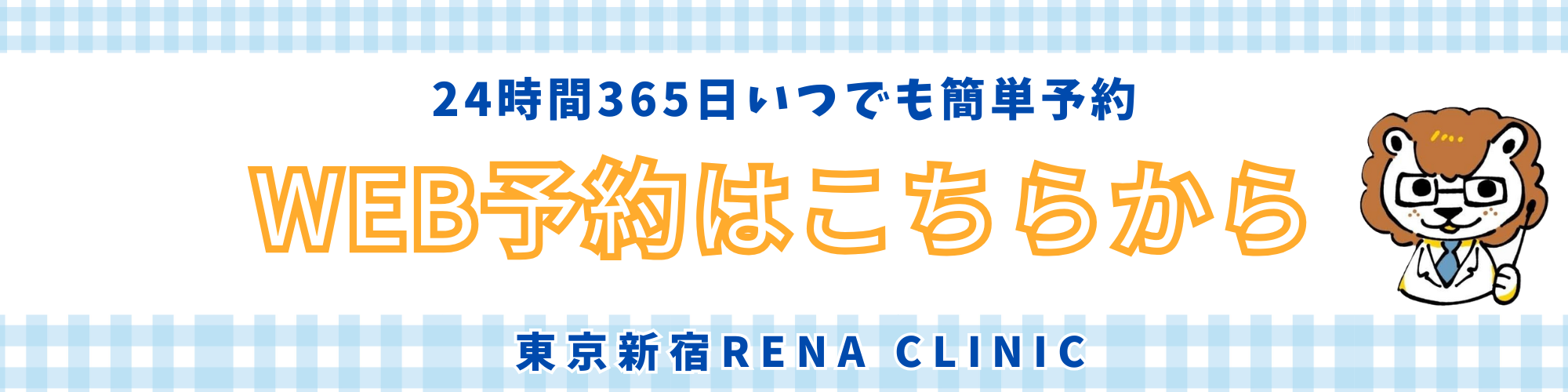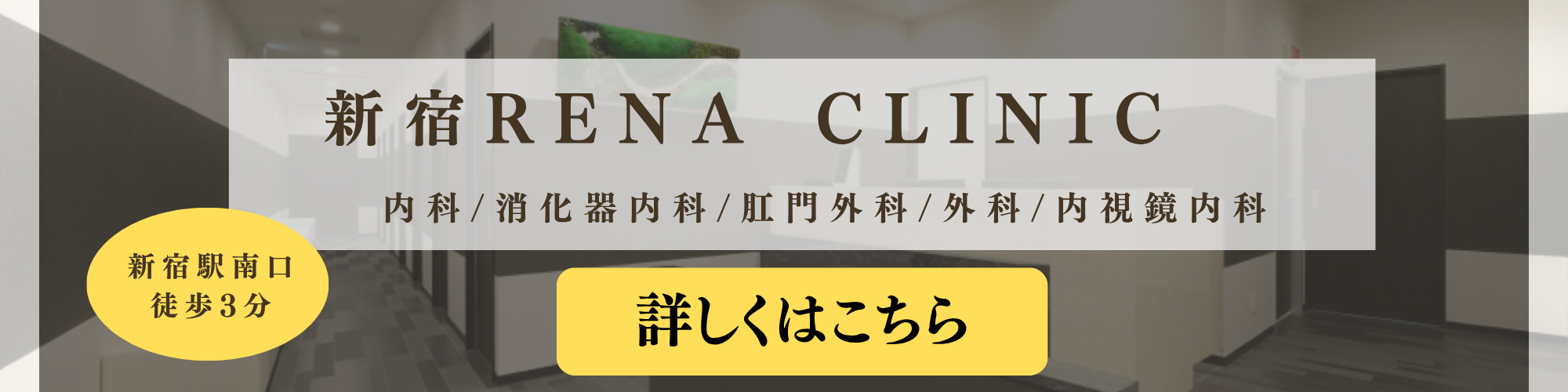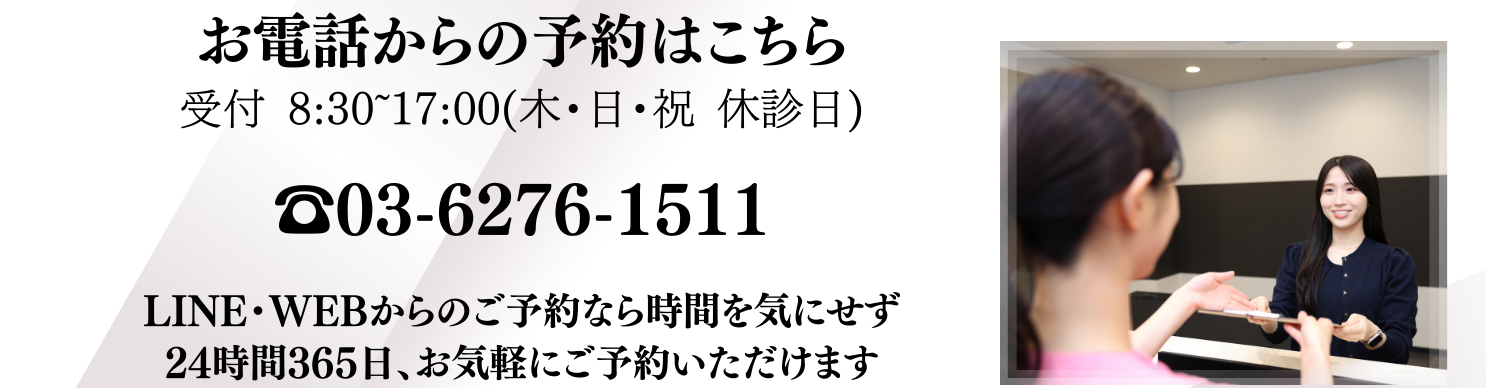あれっ、なんだか足の親指がズキズキ痛い…「ただの疲れかな?」と我慢していませんか?
痛風発作は、前触れなく突然やってくる“激痛”として知られており、その痛みは靴を履くだけで飛び上がるほど…という人も。
高尿酸血症という血液中の尿酸値の異常がベースにあり、普段の生活習慣や飲食・ストレスなどが引き金になることも多いです。
放っておくと再発を繰り返したり、関節の変形・腎機能への悪影響を及ぼすことも。この記事では、「痛風発作」の症状・原因・治療法・予防・日常でできる対応策をわかりやすく整理します。
目次
1. 痛風発作って何? – 原因と発症のメカニズム
痛風発作とは、血液中の尿酸(にょうさん)が一定以上高くなり過ぎ、それが関節内などに結晶化し、これに体の免疫が反応して「急性の炎症」を起こす状態を指します。
発作が起きると、関節が腫れ、熱を持ち、激しい痛みを伴います。
特に足の親指の付け根が最も典型的な発症部位とされています。では、なぜ尿酸が体内に溜まってしまうのでしょうか。主な要因には次のようなものがあります。
- プリン体の過剰摂取:肉類、魚介類の一部(特に内臓や干物)、アルコールなどプリン体を多く含む食品の摂り過ぎ。
- 尿酸排出の低下:腎機能の低下や遺伝的素因、薬の影響などで尿酸が十分尿に排泄されない。体質によるものもあります。
- その他の誘因:大量のアルコール摂取、脱水、極端なダイエット、ストレス、急激な体重変化など。こうした要因が重なると、「発作スイッチ」が入ることがあります。
発作が起きるまで無症状の高尿酸血症であるケースも多く、「尿酸値が高い」というだけでは痛くならないこともあります。
ただし尿酸が高い状態をそのまま放置すると、発作の発生率が上がるだけでなく、痛風結節というしこりの形成や腎障害など長期的な合併症リスクが増します。
2. 痛風発作の典型的な症状と前兆サイン
痛風発作は突然起こることが特徴で、以下のような症状が典型的です:

- 激しい関節痛:発作の最中は非常に痛く、軽く触れただけでも「飛び上がるほど痛い」と感じる方が多い。特に夜間や明け方に痛みが強くなることがあります。
- 関節の腫れ・熱感・赤み:痛みのある関節が腫れて熱を持ち、皮膚が赤くなることも。見た目でも異常と分かるケースが多い。
- 発作の場所:最も多いのは足の親指の付け根。それ以外にも、足首、膝、手首、肘などに起こることがあります。
- 前兆サイン:発作の数時間から1日前に「関節がムズムズする」「違和感・しびれ感」が出ることもあり、再発の経験がある人はこの前兆を感じ取れることがあります。
発作の持続時間は普通、適切な治療を受けると 数日〜1週間程度で症状のピークが収まり、1~2週間でほぼ回復することが多いですが、対応が遅れたり炎症が強い場合はさらに長くかかることも。
また、痛風発作が繰り返されると、関節の破壊や痛風結節、腎機能障害などのリスクが高まりますので、初回の発作でもできるだけ早めに医療機関に受診することが望ましいです。
東京新宿レナクリニックでは、症状の前兆や典型的な発作サインを見逃さない診察を心がけています。
3. 発作が起きたらどうする?治療法と対応の流れ
痛風発作が起きたときには、「まず痛みと炎症をできるだけ早く抑えること」が最優先です。以下は一般的な治療と対応の流れです。
対応の流れ
- 安静・保冷
発作部位は動かさず、靴などの刺激を避ける。冷たいタオルやアイスパックで冷やすことで炎症と腫れが軽減します。 - 薬物治療
- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):発作時の痛みや腫れを抑える標準的治療。腎機能・胃腸などへの影響を考慮して選ぶ必要があります。
- コルヒチン(Colchicine):発作開始直後に使うと効果的。胃腸症状など副作用に注意。
- ステロイド:NSAIDsやコルヒチンが使えない・制限がある場合や重度の場合に、内服または関節内注射が検討されます。 - 発作期後の高尿酸血症治療
発作期間が落ち着いたら、尿酸値を長期的にコントロールする治療を考えます。尿酸の生成を抑える薬(例:アロプリノール、フェブキソスタット等)や尿酸の排泄を促す薬を使い、目標値(通常は血清尿酸値6.0mg/dL以下)を維持することが推奨されます。 - 生活習慣の改善
発作が出た後だけでなく、日常的な食事・水分摂取・体重・アルコール摂取などの見直しが重要。生活習慣が原因であることが多いため、発作が治まった後も継続することが再発予防に直結します。
発作時の治療だけで終わらせず、その後の尿酸管理と習慣改善が肝心です。
東京新宿RENACLINICではこうした全体像を踏まえて、発作治療からその後の長期管理まで一貫したサポートを行っています。
4. 再発を防ぐための生活習慣と予防戦略
痛風発作を一度経験すると、「また痛くなるかも」という不安がつきまとうものです。再発を抑えるためには、次のような生活習慣の改善・予防戦略が有効です。
- 適切な体重管理:肥満は尿酸生成を増やし、排泄を妨げます。体重を減らすことで尿酸値が下がることが多いです。
- 食事の見直し:プリン体を多く含む食品(内臓、魚卵、干物、ビールなど)の摂取を控える。野菜・低脂肪乳製品を適度に取り入れることで尿酸値の管理がしやすくなります。
- 水分を十分に摂る:1日あたり2リットルを目安にこまめに水分をとることで尿酸の排泄を促進。脱水は発作の引き金になります。
- アルコールの制限:特にビールなどプリン体やアルコールの代謝で尿酸値が上昇する飲料は量を控えることが重要。
- 規則正しい生活とストレスケア:睡眠不足・疲労・過度なストレスが免疫や代謝に影響し発作リスクを高める。適度な運動やリラックスする時間を持つことも効果的。
5. 日常でできるケアと治療後のフォローアップ
痛風発作が治まった後も、日常生活でのケアと定期フォローアップが症状の再発抑制・関節保護において非常に重要です。
- 関節のケア:発作中は使えていなかった関節を徐々に動かすストレッチや軽い運動を取り入れる。無理に動かさないが、固まらないように注意する。
- 靴の選び方・足への負担を減らす:発作が多い親指の付け根(母趾第一関節)などに負荷がかかりやすいため、ゆとりのある靴や底の柔らかい靴を選ぶ。
- 定期的な尿酸値チェック:治療後も血液検査で尿酸値を確認し、目標値6.0mg/dL以下を維持できているかモニタリングする。異常があれば薬の調整を行う。
- 薬の服用の継続性:尿酸降下薬を開始した場合、自己判断で中断せず医師の指示に従うこと。発作時のみのケアではなく、長期管理が鍵です。
- 合併症への注意:痛風が繰り返されると痛風結節や、腎臓への負荷、尿路結石などの合併症が出ることがあります。これらを予防するための生活習慣・治療の最適化が必要。
まとめ
痛風発作は突然訪れる激しい関節の痛みですが、きちんと原因を理解し、適切な治療・生活習慣の見直しを行えば、発作の頻度や痛みの重さを大きく軽減できます。初期の発作では NSAIDs やコルヒチン、必要に応じてステロイドを使って炎症を抑え、その後は尿酸値を下げる薬とともに、プリン体の多い食事を控え、水分を十分にとるなどの予防策が重要です。発作を何度も経験する前に対策を始めることが関節・腎臓の健康を守る鍵となります。東京新宿RENACLINICでは、発作の治療だけでなく、その後の尿酸管理・生活習慣改善・栄養指導・再発予防までトータルにサポートいたします。痛みを感じたら、我慢せずご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。