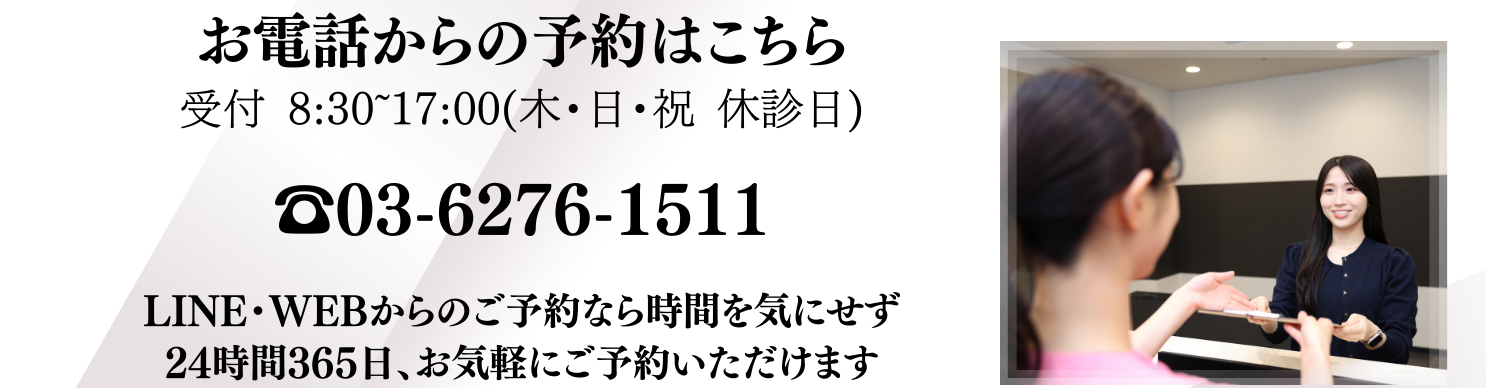下血が出た!どうしたらいい?
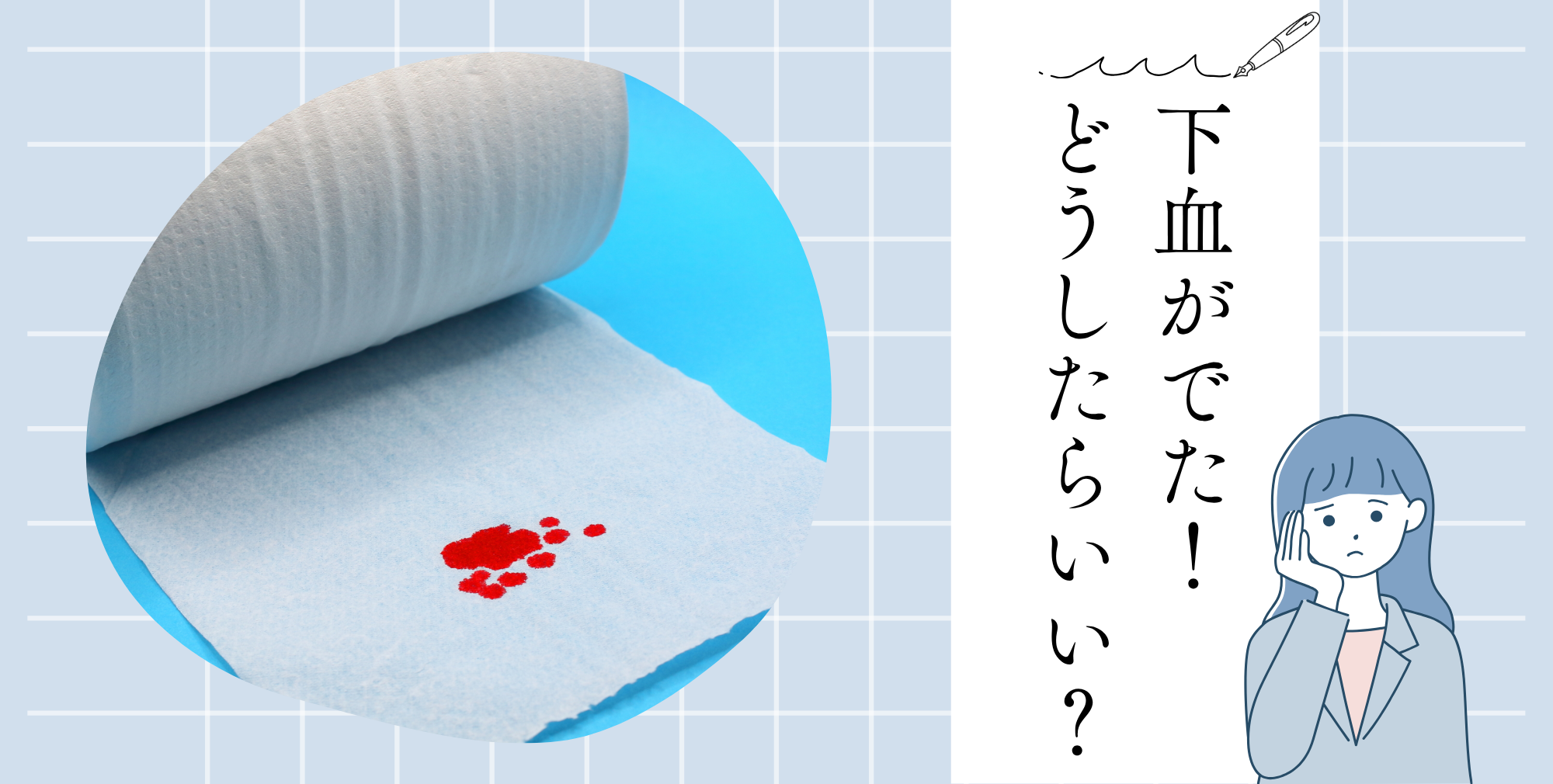
こんにちは!新宿RENA CLINICです!
「えっ、血!?おしりから…」そんなとき、どうすれば?
ある日突然、トイレで便器を見ると「血が…」
驚きと不安で、頭が真っ白になってしまう人も少なくありません。
でも、落ち着いてください。
下血(げけつ)にはいろんな原因があり、すべてが深刻なわけではありません。
この記事では、
-
下血とは何か
-
よくある原因
-
受診すべき診療科
などをやさしく解説します。体のサインを見逃さないためにも、まずは正しい知識を身につけましょう
目次
- 下血とは?見た目でわかる出血部位のヒント
- 下血の主な原因とその特徴
- 下血を見つけたときの初期対応
- 受診すべき診療科と検査の流れ
- 命に関わることも?放置するリスクと予防法
1.下血とは?見た目でわかる出血部位のヒント
「下血」とは、消化管からの出血が肛門から排出される症状を指します。
一般に、血便とも呼ばれ、便に鮮血が混じる場合や、真っ黒な便(タール便)になることもあります。
血の色や形状から、出血の部位をある程度予測できます。
例えば、鮮やかな赤色の血が便の表面についている場合は、痔や肛門裂傷など肛門付近からの出血の可能性が高いです。
一方で、暗赤色や黒っぽい便は、腸の奥や胃・十二指腸など上部消化管からの出血を示唆します。
また、血液が便と混ざり込んでいるような状態だと、大腸からの出血のこともあります。いずれの場合も、自己判断は危険です。
軽い症状でも、重大な病気のサインである可能性があるため、注意が必要です。
特に、腹痛を伴う、意識がぼんやりする、繰り返す場合は、早急に医療機関を受診すべきサインです。
2.下血の主な原因とその特徴

下血を引き起こす原因は多岐にわたりますが、比較的多いのは痔核(いぼ痔)や裂肛(切れ痔)などの肛門疾患です。
これらは排便時に出血しやすく、鮮やかな赤い血がトイレットペーパーや便器に付着することで気づかれることが多いです。
一方、大腸ポリープや大腸がん、潰瘍性大腸炎、感染性腸炎なども下血の原因になります。
特に、大腸がんや炎症性腸疾患などは、血便が唯一の初期症状ということもあるため、軽視できません。
まれに、胃や十二指腸潰瘍による出血が腸を通って排出され、タール便となって現れるケースもあります。
いずれの原因であっても、自己判断で「きっと痔だろう」と決めつけてしまうのは危険です。
特に、40代以降の方や、家族に大腸がんの既往がある方は、出血が一度でもあった場合は必ず医師の診断を受けるようにしましょう。
3.下血を見つけたときの初期対応
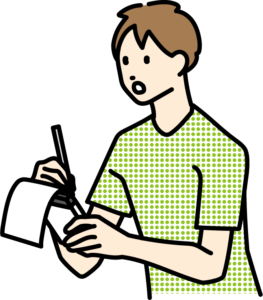
もしトイレで下血に気づいた場合、まずは慌てずに出血の色や量、便の形状を確認しましょう。
鮮血か、黒っぽいか、便に血が混ざっているかなど、状況をメモしておくと、後の診断に役立ちます。
特にタール状の便や、立ちくらみ・動悸などの症状がある場合は、すぐに救急受診が必要です。
また、繰り返し出血する場合や、腹痛・発熱を伴う場合も注意が必要です。
一方で、痔などによる一時的な出血であっても、生活習慣の見直しや肛門科の受診、内視鏡の検査が勧められます。
便秘気味の方は、無理な排便による切れ痔の可能性もありますので、水分摂取や食物繊維の多い食事を心がけることも大切です。
なお、市販薬での対応は一時的な対処に過ぎず、原因を見極めることが根本的な改善につながります。
4.受診すべき診療科と検査の流れ
下血があった場合、まず相談すべき診療科は「消化器内科」または「肛門科」です。
特に大腸や肛門周辺の出血が疑われる場合は、内視鏡を使った精密検査が有効です。
診察では、問診(出血のタイミング、色、頻度など)のほか、必要に応じて肛門鏡での直腸診や血液検査、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)や、胃カメラも追加されることがあります。
これにより、出血源の特定や、ポリープ・炎症・潰瘍・がんなどの病変の有無を調べることができます。
検査には前処置のため、事前の診察が必要ですが、場合によってはRENA CLINIC院内にて下剤を飲み大腸内視鏡検査を行うことも可能です。

ただし、緊急性が高い場合(大量出血・貧血・強い腹痛など)には、救急外来を受診し、入院や即時検査となることもあります。
新宿RENA CLINICでは、日帰り内視鏡検査やオンライン予約を導入しており、早期の受診がしやすくなっています。
5.命に関わることも?放置するリスクと予防法
下血は、一見軽く見える症状でも、深刻な病気のサインである可能性があります。
たとえば、大腸がんや胃潰瘍からの出血は、放置すると進行して命に関わる事態になることもあります。
また、出血量が多い場合は貧血を引き起こし、日常生活に支障をきたすこともあります。
初期の段階で適切に検査・診断を受ければ、比較的簡単な処置や生活習慣の改善だけで済むケースも多くあります。
逆に「恥ずかしい」「忙しい」と受診を先延ばしにすると、症状が悪化し入院や手術が必要になるリスクも高まります。
予防のためには、バランスの良い食事、水分摂取、便通の安定、ストレスの軽減など、腸内環境を整えることが大切です。

また、40歳以上の方や、過去にポリープやがんを指摘された方は、年1回の大腸カメラ検査を習慣にすることが理想です。
「おかしいな」と思ったら、早めに医療機関へ相談することが、何よりの安心につながります。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 多くの病院、クリニックで消化器内視鏡・外科治療を習得後、
2024年東京新宿RENA CLINIC開院。