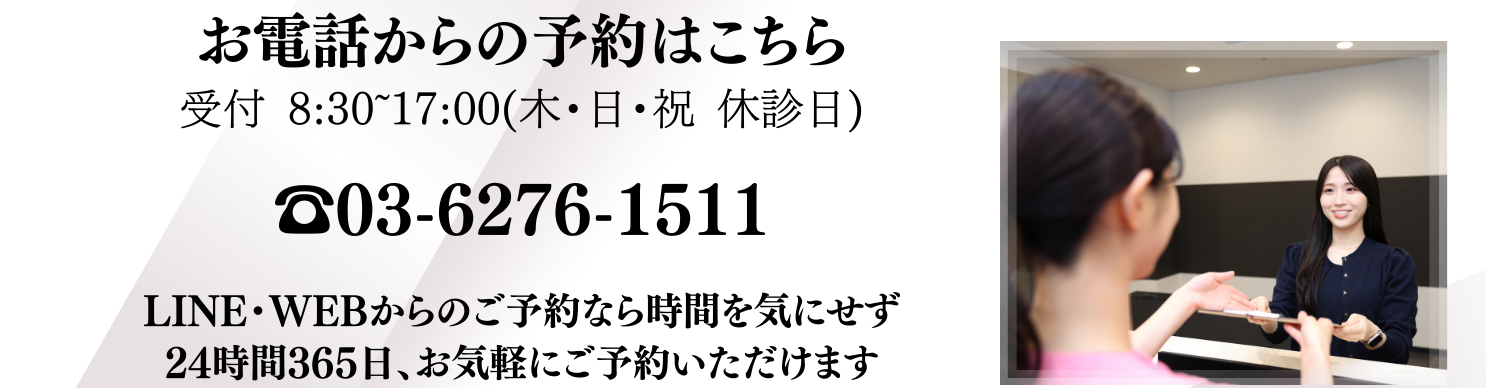下痢で鮮血の血便?その原因と対処法を徹底解説!
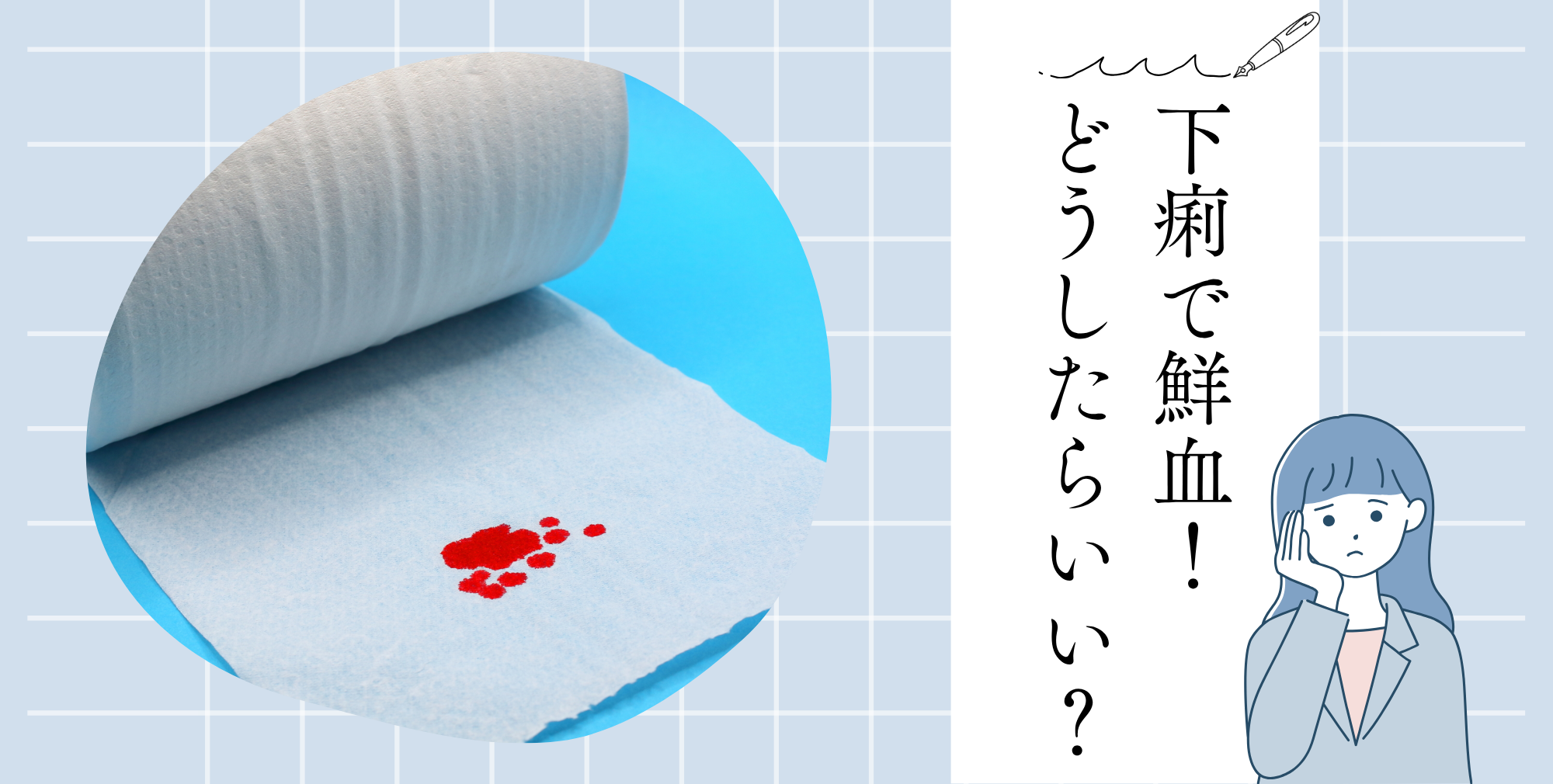
下痢が続いてトイレで…あれ?赤い…。それ、ただの下痢じゃなくて鮮血の血便かもしれません。
一気に不安になりますよね。「下痢で血便って、何か怖い病気?」と思うかもしれませんが、実は痔や感染性腸炎、虚血性腸炎など意外と身近な原因でおこることもあります。
とにかく大切なのは、「色・量・回数・痛み・熱があるかどうか」などを冷静に観察し、適切に対処することなのです。
目次
- 下痢+鮮血便が出るときに考えられる疾患
- 血便の色別サインと意味
- 鮮血の血便が出たときの対処法と注意点
- 病院に行くべき症状とは?検査のすすめ
- 自宅でできるセルフケア&生活改善法
1. 下痢+鮮血便が出るときに考えられる疾患
下痢と鮮血の組み合わせが出たら、以下のような疾患が疑われます
- 大腸憩室出血・大腸ポリープ・大腸がん:憩室は突然の大量出血を、大腸がんやポリープは鮮血便や下痢を伴うことがあります 。
- 虚血性腸炎:中高年に多く、激しい腹痛と下痢・鮮血便がセット。左下腹部の痛みも特徴的です。
- 潰瘍性大腸炎・クローン病:血便や粘液の混じった下痢が続く。発熱や体重減少も起こることがあります。
- 痔(内痔核・裂肛):痛みが少ないことも多く、下痢便が肛門を傷つけて鮮血便になるケースが多いです。
- 感染性腸炎:細菌感染(O157・サルモネラ・カンピロバクターなど)では、水様便や激しい腹痛、発熱を伴い、血便になることもあります。
まずは原因を絞るため、痛み、発熱、排便パターンをしっかりチェックすることが重要です。
2. 血便の色別サインと意味
- 鮮血便(赤):肛門や直腸近くからの出血。痔や裂肛、大腸の炎症性疾患などが多い。
- 暗赤〜赤黒色便:大腸の奥からの出血。大腸がん、虚血性腸炎、炎症性疾患など。
- 粘血便:潰瘍性大腸炎・クローン病、アメーバ腸炎などで粘液と血が混ざる。
- タール便(黒色便):上部消化管(胃・十二指腸)での出血。潰瘍やがんなど。
ただし色だけで判断せず、下痢・腹痛・熱・粘液などの併発症状と合わせて見ることが必要です。
3. 鮮血の血便が出たときの対処法と注意点
💡まず、慌てずに以下を実施してください
- 便の状態を記録:色・量・粘液の有無・回数・痛み・発熱をノートや写真に収めましょう。
- 水分補給と整腸:電解質入り飲料&整腸剤がおすすめ。激しい下痢には脱水予防が重要です。
- 安静&消化に良い食事:脂っこいもの、刺激物は避け、小分け食が良いとされています。
- 坐浴やぬる湯入浴:肛門の血流改善と刺激緩和に有効です。
- 市販の止血薬や軟膏:痔や裂肛が原因なら一時的に症状を緩和できます。
⚠️注意点
熱がある、激しい腹痛、大量の鮮血が続く、黒色便が出る、体重減少などはすぐ医療機関を受診しましょう!
特に虚血性腸炎や感染性腸炎、がんの可能性が考えられます。東京新宿レナクリニックでは、消化器外来で対応可能です。
4. 病院に行くべき症状とは?検査のすすめ
以下のサインがあれば、なるべく早く受診・検査をしましょう。
- 頻回の鮮血便・激しい腹痛
- 発熱・体重減少・全身倦怠感
- 黒色便やタール便
- 便潜血検査が陽性
- 40歳以上で定期的な大腸内視鏡未受診
検査フローは
- 問診・問診ノートチェック
- 血液検査(炎症・貧血)
- 内視鏡検査(胃カメラ/大腸カメラ)
- CTや超音波による画像診断
痔や軽度感染なら外来治療でOK。重症や腫瘍が見つかったときはより精密な治療に。
東京新宿RENACLINICでは、消化器・内視鏡専門医が診療から検査まで一貫ケアします。
5. 自宅でできるセルフケア&生活改善法
自宅でのケアが回復と再発予防に役立ちます
- 規則正しい食事と水分:食物繊維や発酵食品で便通を整え、脱水対策。
- ストレス対策・運動:腸の緊張を緩和し自律神経を安定化。軽い運動や深呼吸がおすすめ。
- 体を温める習慣:ぬる湯入浴や温タオル、カイロで血行促進。腸活動にも好影響。
- 排便姿勢と習慣の見直し:いきみすぎない、トイレタイムはリラックス、スマホ長時間はNG。
- 坐浴・温水洗浄便座(ぬるま湯):排便後の清潔ケアと肛門血流改善に◎ 。
これらにより、回復と症状予防がスムーズになります。
まとめ
下痢に鮮血が混ざった血便は、不安に感じる方も多いですが、原因は多岐にわたり、痔や感染性腸炎など軽度のものから、虚血性腸炎や炎症性腸疾患、大腸がんまでさまざまです。
色・頻度・痛み・発熱などをチェックし、適切なタイミングで医療機関を受診することが重要。
まずは水分補給・整腸・安静・坐浴などのセルフケアを行い、症状が強い場合は東京新宿RENACLINICでは消化器専門医が迅速に検査・診療を行います。
あなたの不安に寄り添い、原因を見極め、安心できるサポートを提供します。どうぞお気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。