胃痛を和らげるには?食事・ストレス・セルフケアから医療まで徹底解説!
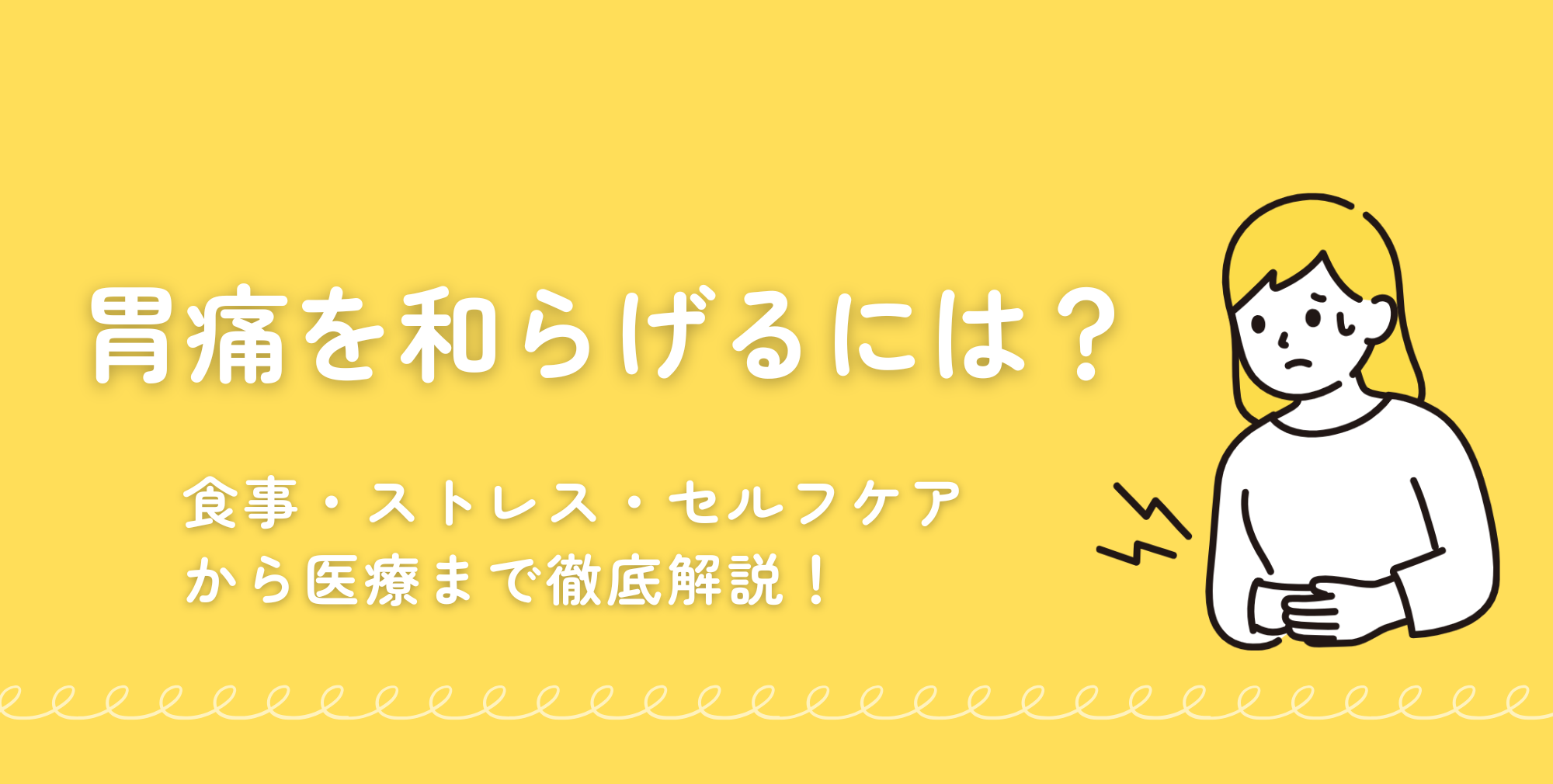
「また胃が痛い…」「食後になるとみぞおちがズキズキ」そんな経験、誰しも一度はあるのでは?
ついストレスや食べすぎのせいにして我慢していませんか?胃痛は日常生活に支障をきたすだけでなく、放置することで慢性化や病気のリスクも。
大切なのは、“我慢しすぎず、自分でできるケアから始める”ことです。
このブログでは、医療の視点を交えながら「胃痛を和らげる方法」を分かりやすくご紹介します。
目次
- 胃痛の原因とは?|なぜ痛くなるのかを正しく知ろう
- 食べ物と胃痛の関係|避ける・摂るべき食品は?
- 胃痛を和らげるセルフケア|すぐできる生活習慣のコツ
- こんなときは医療機関へ|検査・治療の流れ
- 胃痛の治療と予防|薬・漢方・再発防止のポイント
1. 胃痛の原因とは?|なぜ痛くなるのかを正しく知ろう
胃が痛くなる理由は一つではなく、日常的な要因から病気まで幅広くあります。
もっとも多いのは「機能性胃腸障害」や「急性胃炎」で、暴飲暴食やストレス、生活の乱れが大きく関わっています。
中には、ピロリ菌感染や潰瘍、逆流性食道炎などが隠れている場合もあります。胃は自律神経の影響を大きく受ける臓器の一つで、精神的なストレスや睡眠不足、緊張によって胃酸の分泌が増加し、胃粘膜が荒れてしまいます。
また、カフェインやアルコール、香辛料などの刺激物も粘膜を傷つけ、痛みの引き金になることがあります。
このように、胃痛の原因には「生活習慣・食習慣」「ストレス」「胃の病気」などさまざまな要因が複雑に絡み合っています。まずは、自分の症状がいつ、どのような場面で起こっているのかを振り返ることが、正しい対処への第一歩です。
2. 食べ物と胃痛の関係|避ける・摂るべき食品は?
食事内容は、胃痛の発症にも緩和にも大きく関係します。
胃に優しい食事を意識することで、症状の悪化を防ぐだけでなく、予防にもつながります。
まず避けたいのは、脂っこいもの・刺激物(香辛料、キムチ、にんにくなど)・カフェイン・アルコール・炭酸飲料などです。これらは胃酸分泌を促進したり、胃の粘膜を刺激して炎症を悪化させる可能性があります。
一方で、胃痛があるときにおすすめの食品には、以下のようなものがあります。
- おかゆ、うどん、柔らかく煮た野菜
- 白身魚や豆腐などの消化しやすいタンパク質
- 生姜やキャベツ(胃粘膜保護効果あり)
- バナナやりんご(胃酸を中和する作用)
また、食べ方も重要です。一気に食べず、少量をゆっくり噛んで食べる、食後はすぐ横にならず30分は体を起こしておくなど、日々の習慣が胃への負担を減らすことに繋がります。
3. 胃痛を和らげるセルフケア|すぐできる生活習慣のコツ
日常的にできるセルフケアは、胃痛予防と症状緩和にある程度効果的です。まず基本となるのが、以下の4つのポイントです。
①規則正しい生活リズム
睡眠不足や夜更かしは自律神経を乱し、胃の動きを弱めてしまいます。就寝・起床時間を一定にし、睡眠時間をしっかり確保しましょう。
②ストレスコントロール
胃は「心の鏡」とも言われるほどストレスに敏感です。軽い運動や深呼吸、趣味の時間を取り入れることも大切です。また、ぬるめのお風呂に浸かることも効果的とされています。
③腹部を温める・マッサージする
カイロや蒸しタオルでみぞおち周辺を温めると、胃の血流が改善されて症状が和らぐことがあります。また、優しく時計回りにお腹をマッサージするのもおすすめです。
④市販薬の使用について
H₂ブロッカーや胃粘膜保護薬、消化酵素剤などは一時的な緩和に有効ですが、頻繁に使用する場合は医師の判断が必要です。
「いつもの胃痛だから」と我慢しがちですが、生活の中で少しずつ体と向き合うことで症状が和らぐことも少なくありません。
東京新宿レナクリニックでは、管理栄養士による栄養指導を含めた診察・治療を行っています。
4. こんなときは医療機関へ|検査・治療の流れ
セルフケアで改善しない、あるいは以下のような症状がある場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。
- 胃の痛みが1週間以上続いている
- 空腹時・食後どちらでも強い痛みがある
- 吐き気・嘔吐・吐血などを伴う
- 貧血や体重減少などがみられる
診察ではまず問診が行われ、症状のタイミングや内容、服用中の薬などを確認します。
その後、必要に応じて胃カメラ検査や血液検査、ピロリ菌の有無を調べる検査を行うこともあります。
治療は、診断内容に応じて薬物療法が基本になります。機能性ディスペプシアなら消化機能改善薬、ピロリ菌感染があれば除菌治療が行われることもあります。
症状が慢性化する前に、一度専門医の診察を受けることが大切です。
5. 胃痛の治療と予防|薬・漢方・再発防止のポイント
胃痛の治療は、原因に合わせたアプローチが必要です。一般的には以下の治療が行われます。
①胃酸分泌抑制薬(PPI・H2ブロッカー)
胃酸の過剰分泌を抑えて、胃粘膜を保護します。逆流性食道炎や胃潰瘍に効果的です。
②粘膜保護薬・消化酵素剤
胃の粘膜を覆い、刺激から守ります。消化を助ける薬も併用されることがあります。
③漢方薬の活用
六君子湯、半夏瀉心湯などは、胃の機能低下やストレス性胃炎に用いられます。自然由来の作用で、体質改善を目指せるのが魅力です。
④ピロリ菌除菌治療
ピロリ菌の除菌を行い、胃の不調の原因を改善します。
まとめ
胃痛は、ストレスや生活習慣の乱れ、食事内容など、誰にでも起こり得る身近な症状です。
軽く見られがちですが、放置すると慢性化したり、深刻な病気につながることもあります。
まずは自分でできる食事改善やセルフケアを実践し、それでも改善しない場合は、早めに医療機関へご相談ください。
東京新宿RENACLINICでは、胃痛の原因から適切な検査・治療・生活指導まで、患者様に合わせたサポートを行っています。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。






