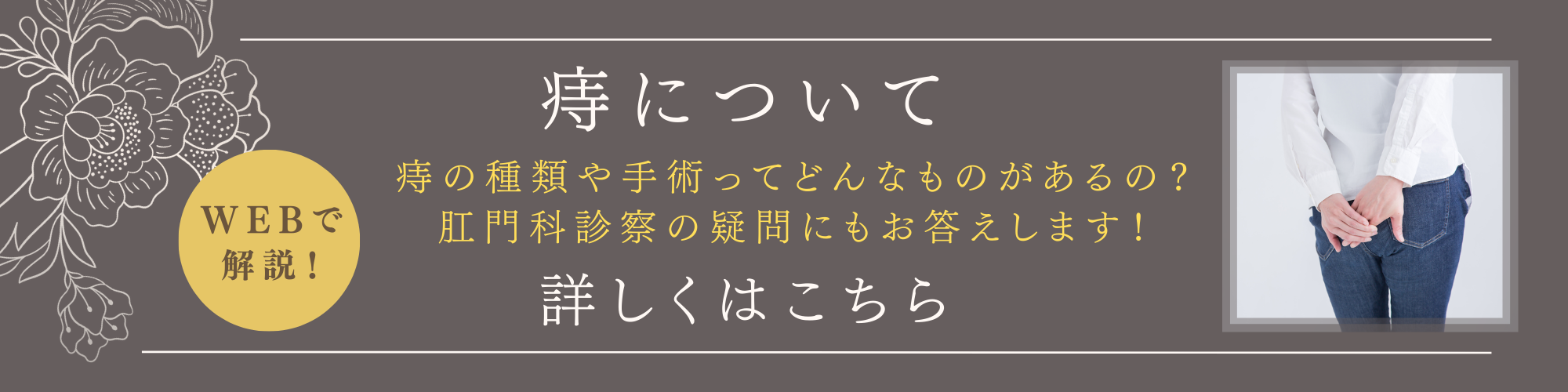痔になりやすい生活習慣とは?予防のための5つのポイント

こんにちは!東京新宿RENACLINICです!
今日はちょっとデリケートなお話、「痔になりやすい生活習慣」についてお話ししていきます。
「なんか最近お尻がムズムズする…」「トイレのあと、ちょっと違和感あるかも?」そんなあなた、もしかしたら生活習慣に原因があるかもしれません。
恥ずかしがらずに、まずは知ることから始めてみましょう。
目次
- 長時間の座位と運動不足
- 食生活の乱れと便通への影響
- 排便時の習慣と肛門への負担
- ストレスと自律神経の関係
- 予防のための日常生活の工夫
1.長時間の座位と運動不足
デスクワークや長時間の座位は、肛門周囲の血流を悪化させ、痔の原因となります。
また、運動不足も血行不良を招き、肛門周辺の静脈に負担をかけます。
1時間に一度は立ち上がってストレッチを行うなど、適度な運動を取り入れることが大切です。
日常生活にウォーキングや軽い体操を取り入れることで、血流が改善され、痔の予防につながります。
2.食生活の乱れと便通への影響
食物繊維の不足や水分摂取の不足は、便秘を引き起こし、排便時に肛門に過度な力がかかります。
また、脂っこい食事や刺激物の過剰摂取も、肛門への刺激となり、痔を悪化させる要因となります。
バランスの取れた食事を心がけ、野菜や果物、全粒穀物を積極的に摂取しましょう。
また、1日に1.5~2リットルの水分を摂ることで、便通が改善されます。
3.排便時の習慣と肛門への負担
排便時に過度に力むことや、長時間トイレに座る習慣は、肛門に大きな負担をかけます。
便意を感じたら我慢せず、スムーズに排便を行うことが重要です。
また、トイレでのスマートフォンの使用など、長時間座る習慣は避けましょう。
排便時はリラックスし、無理な力みを避けることで、肛門への負担を軽減できます。
4.ストレスと自律神経の関係
ストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の動きや血流に影響を与えます。
これにより、便秘や下痢を引き起こし、痔のリスクが高まります。
リラクゼーションや趣味の時間を持つことで、ストレスを軽減しましょう。
また、十分な睡眠を確保し、規則正しい生活を送ることも、自律神経の安定に寄与します。
5.予防のための日常生活の工夫
痔の予防には、日常生活での小さな工夫が効果的です。
例えば、便座に長時間座らない、適度な運動を取り入れる、バランスの良い食事を心がけるなどです。
また、肛門周辺を清潔に保つことも大切です。
入浴時に優しく洗い、刺激の少ない下着を選ぶことで、肛門への負担を減らすことができます。
まとめ
痔は日常生活の習慣が大きく影響する疾患です。
長時間の座位、運動不足、食生活の乱れ、排便時の習慣、ストレスなど、さまざまな要因が関与しています。
これらの習慣を見直し、適切な生活を心がけることで、痔の予防や改善が期待できます。
症状が気になる場合は、早めに医療機関を受診し、適切なアドバイスを受けましょう。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。
青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 多くの病院、クリニックで消化器内視鏡・外科治療を習得後、
2024年東京新宿RENA CLINIC開院。