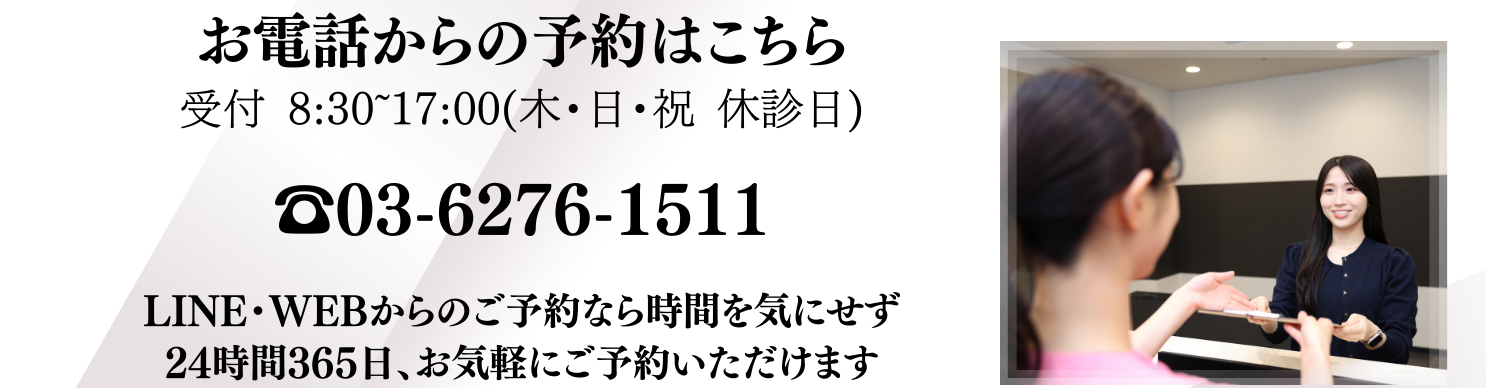「水様便が続く…」その原因と対処法を知ろう

「最近、トイレに行く回数が増えた」「お腹がゴロゴロして、すぐに水様便が出てしまう」
そんな経験はありませんか?水様便が続くと、日常生活にも支障をきたすことがあります。
しかし、これらの症状は一時的なものか、何か病気が隠れているのか、判断が難しいところです。今回は、水様便が続く原因とその対処法について詳しくご紹介します。
目次
- 水様便とは?その特徴と分類
- 水様便が続く主な原因とは?
- 受診のタイミングと必要な検査
- 日常生活でできる対処法と予防策
- 東京新宿RENACLINICでの対応と治療方針
1. 水様便とは?その特徴と分類
水様便とは、通常の便よりも水分が多く含まれ、形がなく、流動的な状態の便を指します。
一般的に、便の水分量が90%以上になると水様便とされます。水様便は、急性と慢性に分類されます。
- 急性水様便:数日から1週間程度で回復することが多い。
- 慢性水様便:3週間以上続く場合、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
水様便が続く場合、放置せずに専門医の受診を検討することが重要です。
2. 水様便が続く主な原因とは?
水様便が続く原因は多岐にわたります。以下に代表的なものを挙げます。
- 感染性腸炎:ウイルスや細菌による感染が原因で、急性の水様便を引き起こすことがあります。発熱や嘔吐を伴うこともあります。
- 過敏性腸症候群(IBS):ストレスや食生活の乱れが影響し、下痢型の症状が続くことがあります。
- 炎症性腸疾患(IBD):潰瘍性大腸炎やクローン病など、腸に慢性的な炎症が生じる疾患です。血便や体重減少を伴うことがあります。
- 薬剤性下痢:抗生物質や制酸剤などの薬剤が腸内細菌のバランスを崩し、下痢を引き起こすことがあります。
- 食物不耐症:乳糖不耐症やグルテン不耐症など、特定の食品が原因で水様便が続くことがあります。
これらの原因を特定するためには、専門的な検査が必要です。
3. 受診のタイミングと必要な検査
水様便が続く場合、以下のような症状がある場合は、早めの受診が推奨されます。
- 水様便が1週間以上続く
- 発熱や嘔吐を伴う
- 血便や黒色便が出る
- 体重減少や倦怠感がある
- 便秘と下痢を繰り返す
受診時には、以下のような検査が行われることがあります。
- 便検査:感染症の有無や腸内細菌の状態を調べます。
- 血液検査:炎症反応や栄養状態を確認します。
- 大腸内視鏡検査:腸の内部を直接観察し、炎症やポリープの有無を確認します。
- 画像検査:CTやMRIを用いて、腸の状態を詳しく調べます。
これらの検査により、原因を特定し、適切な治療方針を決定します。
4. 日常生活でできる対処法と予防策
水様便が続く場合、以下のような生活習慣の見直しが有効です。
- 食事の改善:脂っこい食事や刺激物を避け、消化の良い食事を心がけましょう。
- 水分補給:下痢により失われた水分を補うため、こまめに水分を摂取しましょう。経口補水液が効果的です。
- ストレス管理:ストレスが腸に影響を与えることがあります。リラックスできる時間を持つよう心がけましょう。
- 規則正しい生活:睡眠不足や不規則な生活は腸の働きに影響を与えます。規則正しい生活を心がけましょう。
これらの対策を講じることで、症状の改善が期待できます。
5. 東京新宿RENACLINICでの対応と治療方針
東京新宿RENACLINICでは、水様便が続く患者様に対して、以下のような対応を行っています。
- 丁寧な問診と症状の把握:患者様の生活習慣や食事内容、ストレスの有無などを詳しくお伺いします。
- 必要な検査の実施:症状に応じて、便検査や血液検査、大腸内視鏡検査などを行い、原因を特定します。
- 個別の治療計画の策定:検査結果をもとに、薬物療法や食事療法、生活習慣の改善など、患者様一人ひとりに合った治療計画を立てます。
- 継続的なフォローアップ:症状の改善状況を確認し、必要に応じて治療方針を見直します。
水様便が続くことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
水様便が続くことは、単なる体調不良ではなく、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
症状が1週間以上続く場合や、他の症状を伴う場合は、早めの受診が重要です。東京新宿RENACLINICでは、専門的な検査と治療を通じて、患者様の健康をサポートしています。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。