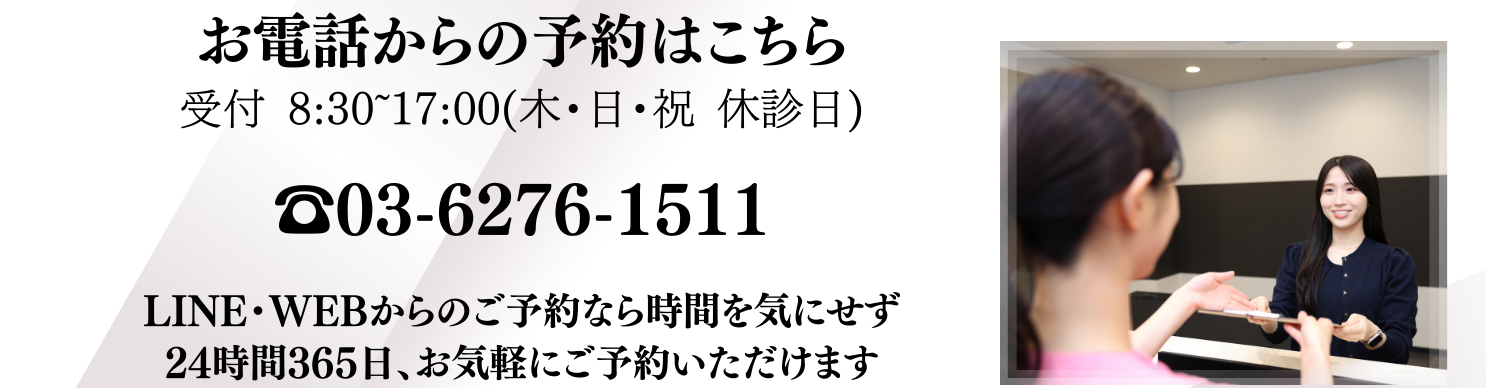お酒を楽しむ機会が多い方、もしかすると腸内環境に影響が出ているかもしれません。
「毎日の晩酌が日課」「週末は飲み会が続く」そんな方は少なくないでしょう。
適度なお酒は気分をリラックスさせる効果がありますが、実は“腸内細菌”にとっては大きな刺激になることをご存じですか?
腸内環境が乱れると、便秘や下痢、肌荒れ、免疫力の低下などさまざまな体調不良に繋がります。
この記事では、アルコールと腸内細菌の関係について、医学的な観点から詳しく解説します。
目次
1.腸内細菌とは?私たちの健康を支えるミクロの世界
2.アルコールが腸内細菌に与える影響
3.飲酒とうまく付き合うための腸活習慣
4.注意すべき体のサインと受診の目安
5.まとめ
1. 腸内細菌とは?私たちの健康を支えるミクロの世界
私たちの腸内には、数百〜数千種類、約100兆個以上もの腸内細菌が住みついており、その総量は1.5kgにもなると言われています。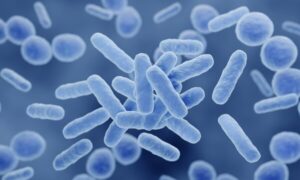
これらの腸内細菌は、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」に分類され、バランスを保ちながら私たちの体にさまざまな良い影響を与えています。
善玉菌は、消化吸収の補助、ビタミンの合成、免疫機能の活性化、腸のバリア機能維持などに関与しています。
一方、悪玉菌が増えると、腸内で腐敗物質や有害ガスが発生し、便秘・下痢・お腹の張り・肌荒れ・倦怠感など、さまざまな不調を引き起こします。
健康な腸内環境を維持するには、善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えることが大切です。
この微妙なバランスが乱れることで、体調は目に見えて変化します。そして、そのバランスを崩す要因のひとつが「アルコール」なのです。
2. アルコールが腸内細菌に与える影響
アルコールは口から入って胃や小腸で吸収され、一部は肝臓で分解されますが、その過程で腸内細菌にも影響を及ぼします。
まず、アルコールが腸内環境に与える代表的な影響を見ていきましょう。
- 善玉菌の減少と悪玉菌の増加
アルコールやその代謝産物であるアセトアルデヒドは、腸の粘膜にダメージを与え、善玉菌の生育環境を悪化させます。その結果、腸内の善玉菌が減少し、相対的に悪玉菌が増えやすくなります。特に多量飲酒はこの傾向が顕著です。 - 腸のバリア機能低下(リーキーガット症候群)
アルコールは腸の粘膜を刺激し、「腸のすき間」が広がってしまう「リーキーガット」を引き起こすことがあるという説もあります。これにより、通常は吸収されない未消化物質や毒素が体内に入り込み、慢性的な炎症を引き起こす原因になるといわれることもあります。 - 下痢や便秘の引き金に
腸内細菌のバランスが崩れると便通が不安定になります。お酒を飲んだ翌日「下痢になる」「お腹が張る」「便秘気味になる」などの症状があれば、腸内環境の乱れが疑われます。 - 肝臓と腸内細菌の相互関係
腸内細菌が産生する毒素は、門脈を通じて肝臓に送られます。腸内環境が悪化していると、肝臓への負担も増加し、肝機能低下の一因になります。アルコールの影響が腸を経由して肝臓へ波及するという点も見逃せません。
3. 飲酒とうまく付き合うための腸活習慣
「アルコールは一切禁止すべき」というわけではありません。
大切なのは、飲酒と腸内環境のバランスを意識しながら、日々の生活の中で腸をケアしていくことです。以下のような腸活習慣を取り入れてみましょう。
- 発酵食品を意識的に摂る
納豆・ヨーグルト・キムチ・ぬか漬けなどの発酵食品には善玉菌が多く含まれています。食事に取り入れて、腸内細菌の多様性をサポートしましょう。 - 食物繊維をバランスよく摂取
野菜、豆類、海藻類、きのこ類などに含まれる水溶性・不溶性の食物繊維は、腸内の善玉菌のエサになります。特に水溶性の食物繊維は発酵性が高く、腸内の短鎖脂肪酸を増やす働きがあり、炎症の抑制にも役立ちます。 - お酒を飲む日は「量」と「頻度」に注意
週に2日以上の休肝日を設けたり、個人差はありますが、1日の飲酒量を適量(ビールなら缶1本程度)に抑えたりすることが重要です。体調が悪い日や腸の不調を感じるときは、お酒を飲まないことも大切です。 - 水分をしっかり補給する
アルコールは利尿作用があり、腸内の水分バランスを乱します。脱水による便秘も招くため、飲酒時は水も一緒に摂るようにしましょう。
腸内環境を整えることで、アルコールとの付き合い方もより健康的になります。
東京新宿RENACLINICでは、腸の不調に関する検査やアドバイスも行っております。
4. 注意すべき体のサインと受診の目安
アルコールによる腸内環境の悪化は、次のような体のサインとして現れます。
- 下痢や便秘が続く
- お腹が張る・ガスが多い
- 肌荒れが治らない
- 疲れやすくなった
- 飲酒後に腹痛がある
- 風邪をひきやすい
こうした症状が慢性的に続く場合、腸内細菌のバランスが乱れている可能性があります。また、腸の不調は他の疾患のサインであることもあります。
東京新宿レナクリニックでは、腸内環境の検査や、体質・生活習慣に合わせたアドバイス、必要に応じて消化器系の精密検査なども行っております。
自己判断で放置せず、専門医の診断を受けることも大切です。
まとめ
アルコールは私たちの生活に欠かせない楽しみの一つですが、腸内細菌に与える影響も忘れてはなりません。お酒の飲みすぎは腸内環境を悪化させ、体のさまざまな不調の原因となります。大切なのは、日常の中で腸を労わる習慣を持ちつつ、無理のない範囲でお酒と付き合っていくことです。
東京新宿RENACLINICでは、腸内環境の診断や、腸の不調に関するご相談にも対応しております。お腹の不調や体調の変化を感じた際には、お気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。