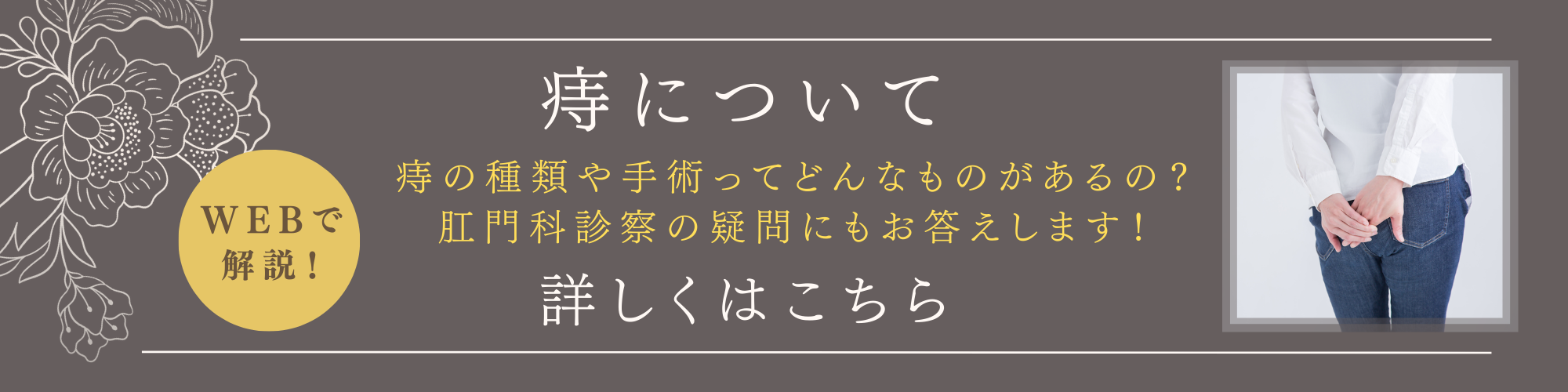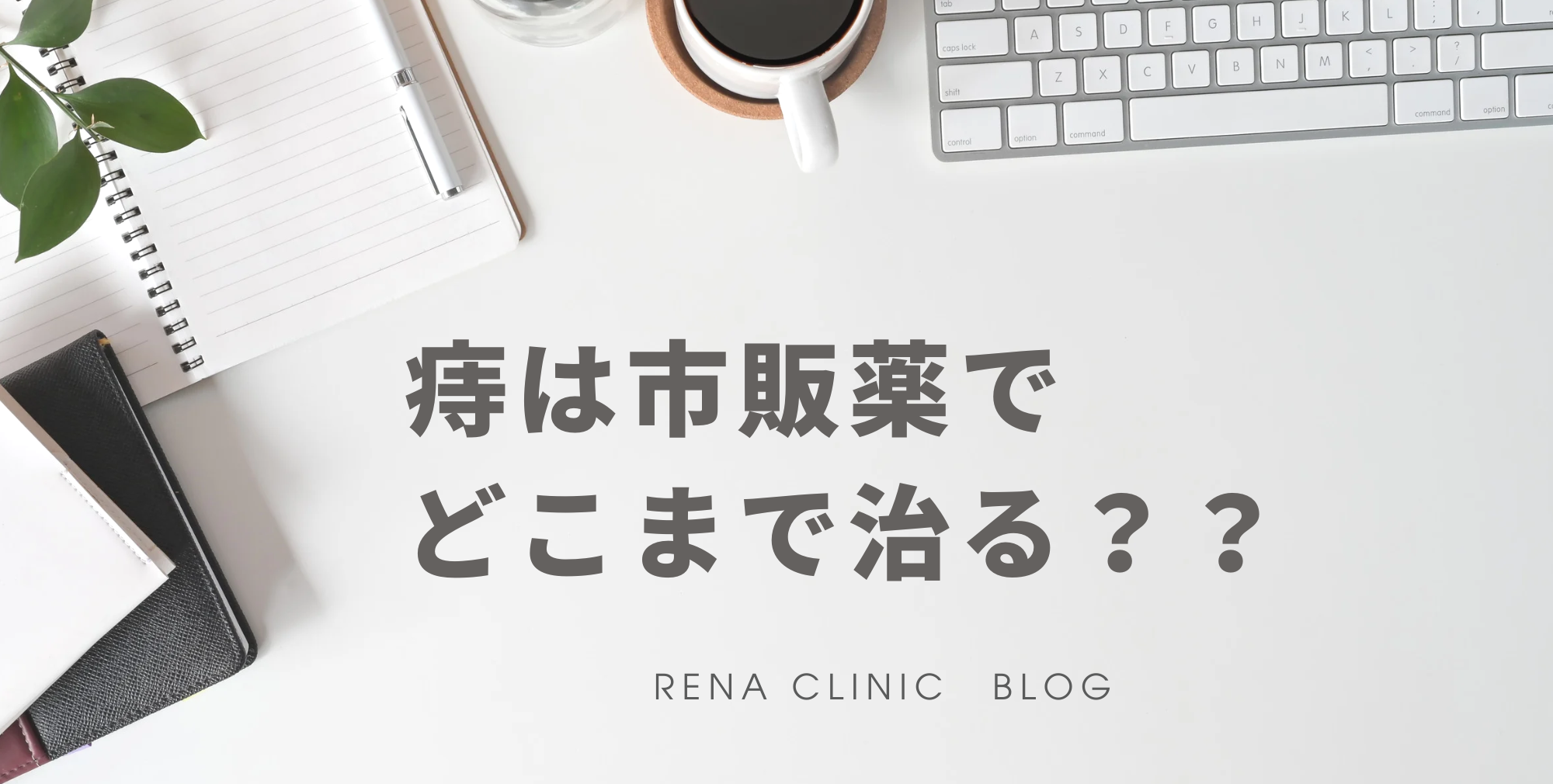
「またお尻が痛い…」「トイレットペーパーに血が…?」そんな経験、誰しも一度はあるかもしれません。
痔は日本人にとって身近な悩み。ネットで“市販薬で治る”との記載を見て、買おうか迷っている人、いませんか?
確かに、市販薬にも“効く成分”は入っていて、軽めの痔(例えば軽度の内痔核・外痔核・切れ痔など)なら症状を和らげたり、大きさや出血を抑えたりできることがあります。
でも、「治る」という言葉の定義は人それぞれであることに加え、症状や期間・程度によっては市販薬だけでは不十分なことも多いです。この記事では「痔に使う市販薬の効能」をキーワードに、どのようなケースで市販薬が有効か・どこまで期待できるか・市販薬を使う上で注意すべきポイントやその限界を、東京新宿RENA CLINICの視点も交えて解説します。
目次
1. 市販薬で使われる主な成分とその作用メカニズム
市販薬でよく見られる成分には、以下のようなものがあります。
- 血行・静脈系改善成分:ヘパリン類似物質、ヒドロコルチゾン・プレドニゾンなどの抗炎症ステロイド、あるいは血管収縮作用のある成分(例:酸化アルミニウム、タンニン酸)。これらは腫れ・炎症・出血を抑える作用があります。
- 鎮痛・かゆみ止め成分:リドカインやベンゾカインなどの局所麻酔、カンフル、メントールなどの冷感・刺激でかゆみを和らげるものがあります。
- 止血作用・収れん作用:上述のタンニン酸や、アルミニウム塩などで、出血を抑える目的で使用されます。
- 保湿・保護作用:皮膚・粘膜を保護する軟膏基材、バリア作用を持つもの。便がこすれて刺激を受けやすい部位なので、保護が重要です。
- 漢方薬・生薬:日本では、例えば乙字湯などの生薬処方も使われ、炎症を抑えること、血流改善、組織の修復促進などを期待する声があります。軽度の症状であれば漢方が有効なこともあります。
ただし、これらの成分・作用は“対症療法”であるため、根本的な構造的な問題がある場合、市販薬のみで完全に“治す”のは難しいことがあります。
2. 市販薬で効く場合と効きづらい場合
市販薬が効く可能性が高い場合
- 痔がまだ軽度である:内痔核の初期段階(出血が少ない、腫れや脱出が軽い)、または裂肛で痛みが主な症状。
- 痔発症から期間が短い:長期間放置していないものほど、炎症・腫れ・傷が深くならず、市販薬+生活改善で改善しやすい。
- 排便習慣・生活習慣が整っている:便秘・硬便の改善、座り過ぎや重い荷物を持つことなどの負荷を減らすなど、原因へのアプローチができる。
- 症状が限定的である:たとえば痛みやかゆみ・軽い出血のみで、脱出や重大な腫れ・組織の壊死などがない。
市販薬だけでは効果が出にくい場合
- 内痔核が脱出していて、肛門外に出て戻す必要がある/戻らないもの(中度〜重度)。
- 出血が頻繁・多量で貧血を起こしそうな場合。
- 歩行困難なほど痛みが強い・腫れが大きい・発熱を伴うなど炎症が強い場合。
- 長期間(数週間~数か月)市販薬を使っても改善が乏しい場合。
- 痔ろう・癌など他の肛門疾患の可能性が否定できない場合。
このようなケースでは、市販薬は補助的なもの、あるいは手術・注射療法・クリニックでの専門治療の前処置として使うのが現実的です。
3. 市販薬を使う際のポイントと注意点
市販薬を有効に使うためには、以下の点に注意する必要があります。
- 正しい薬の選択:ステロイド入りか否か、鎮痛成分か収れん成分か、あるいは局所麻酔が含まれているかなど。刺激に弱い人はまず非ステロイド・低刺激のものを試しましょう。
- 用法・用量を守ること:塗布の回数・期間をきちんと守りましょう。過度に使うとステロイドの副作用(皮膚の萎縮・感染など)が出ることもあります。
- 清潔の保持・保湿・摩擦を避ける:肛門周囲をやさしく洗う、乾かす、便がついた時はなるべく早く洗浄・保湿剤使用など。肛門をこする・トイレットペーパーで激しく拭くなどの行為を避けましょう。
- 便通の改善:硬い便や便秘は痔を悪化させる主要因。水分・繊維を摂る、排便時のいきみを減らす、下剤や便軟化薬を使うことも検討しましょう。
- 生活習慣の見直し:長時間座る・重い荷物を持つ・体を冷やすなど肛門への負荷を増やす要因を減らしましょう。運動も効果的です。
注意点としては、市販薬はあくまで“対症的”な方法であるため、症状が改善しない・悪化する場合は無理に自己判断で続けないこと、またアレルギー反応や皮膚の異常が出たらすぐ使用を中止することなどがあります。東京新宿レナクリニックでは、こうした注意点を含めた使い方をアドバイスしています。
4. 症状が改善しない・悪化したときはどうするか
市販薬を使っても症状が改善しない、あるいは悪化してきたら、以下のステップを考えてみてください。

- 期間を区切る:一般には数日〜1週間(症状が軽い場合)市販薬を使ってみて、改善が見られれば継続、出血が続く・痛みが強い・腫れが引かない場合は医療機関受診を検討しましょう。
- 医師/肛門科クリニックでの専門的判断:診察で痔の種類(内痔核・外痔核・脱出の程度・他の疾患の可能性など)を診断し、必要なら注射療法・手術療法などを提案します。
- 再発予防を意識する:改善しても、原因となる便秘・排便習慣・生活環境を改善し続けましょう。再発を防ぐケアが長期的には大切です。
もし「市販薬を使っても2週間以上改善しない」「出血がひどく量が多い」「脱出が戻らない・痛みで歩行や日常生活に支障がある」といった症状がある場合は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。
5. 東京新宿レナクリニックでの対応と相談の目安
東京新宿RENA CLINICでは、市販薬を試したいという方にも、まず丁寧な視診(肛門検査)を行い、どの程度の痔かを把握します。
症状の強さ・脱出の有無・炎症や出血の頻度などを元に、専門的治療を併用または早めに検討するかを判断します。
相談の目安としては、「市販薬を1~2週間使って改善が見られない」「出血が頻繁・多量」「痛み・腫れで歩きにくい・日常生活が制限される」「脱出して戻らない・排便で脱出が悪化する」といった場合です。
これらのサインを見逃さず、早めに来院いただくことで、治療期間を短くできたり重症化を防げたりします。
東京新宿レナクリニックでは、市販薬で改善が見られない方にも安心して相談できる体制を整えており、手術治療・注射療法・その他保存療法を含めた選択肢を丁寧にご説明します。
まとめ
市販薬は、軽度の痔の症状(軽い出血・かゆみ・腫れ少なめ・痛みがひどくないなど)であれば、成分を正しく選び、生活習慣の改善を行うことで十分に改善が期待できます。とはいえ、脱出がある・出血が多い・痛みが強いなど重めの症状では、市販薬だけでは改善が難しいケースがあります。また、症状が長引くと組織の変化が進んでしまい、治療が複雑になることもあります。市販薬はあくまで“第一歩”として考え、改善が見られない場合や不安な場合は専門のクリニックで診察を受けましょう。東京新宿RENA CLINICでは、患者さんそれぞれの痔の種類・程度に応じて、市販薬による対処から専門治療まで、安心して相談できる体制を整えております。どうぞお気軽にお越しください。
参考文献
- Yamana, T., Japanese Practice Guidelines for Anal Disorders I. Hemorrhoids. Journal of Anus, Rectum and Colon. 2017; 1(3): 89‑99. PMC
- Hachiro Y., Kunimoto M., Abe T., Ebisawa Y., Aluminum potassium sulfate and tannic acid (ALTA) injection as the mainstay of treatment for internal hemorrhoids. Surg Today. 2011;41(6):806‑809. PMC
- “Recurrence Rates and Pharmacological Treatment for Hemorrhoidal Disease: A Systematic Review.” J‑GLOBAL. 2023.