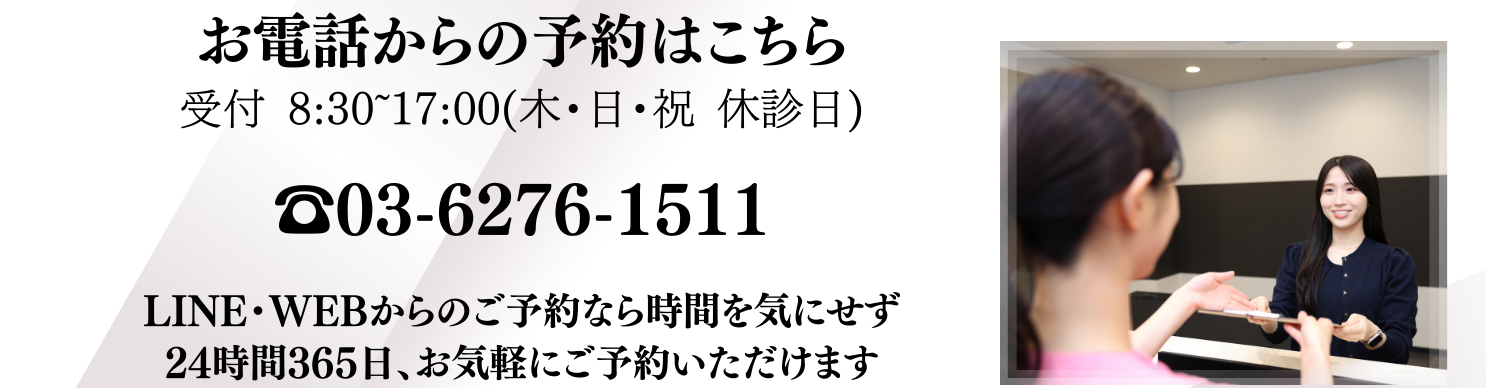なんだか胃がずっと重い… 食後だけじゃなく、朝起きたときや夜寝る前にも胃もたれを感じる…なんてことありませんか?
胃もたれは、「暴飲暴食」「脂っこい食事」「ストレス」などで起こる軽いもの、という印象を持たれがちですが、続く胃もたれにはもっと深刻な原因が潜んでいることもあるんです。
特に「胃癌」のリスクは、初期には自覚症状がほとんどなく、胃もたれ程度の違和感しかないことも多いので、見逃してしまう人が少なくありません。
今回は、胃もたれが“ただの疲れ”や“食べ過ぎのせい”では済まされないケースについて分かりやすく解説していきます。
目次
1. 胃もたれとは何か?症状の特徴とメカニズム
胃もたれとは、食べ物が胃で十分に消化されずに胃内に長くとどまることで、胃の重さ・張り感・不快感などが続く状態を指します。
具体的には、みぞおちのあたりが重苦しい、食後に胃が膨らんだような感じがする、胃の中に食べたものが残っているような感覚、吐き気がすることがある、というような症状が典型です。
胃もたれの背景には複数の要因があります。
まず、胃の蠕動運動(胃が食べ物を攪拌し小腸へ送る運動)の低下が挙げられます。
ストレスや加齢、胃の筋肉や神経の機能低下がこれに影響します。
次に、胃酸の分泌の異常。酸が足りないと消化が進まず、逆に過剰だと胃粘膜を刺激して炎症を起こし、機能が乱れます。
さらに、食事の内容・時間帯も重要で、脂肪分・タンパク質が多い食べ物、揚げ物、濃い味、アルコール、刺激物などは消化負担を増やしますし、食後すぐに横になる、就寝直前に食べるなどの習慣も胃の働きを妨げます。
このように、胃もたれは“胃そのものの働き”“食生活・生活習慣”“内外のストレス”等、複合的な要因で起こるものです。大多数は一時的・軽度ですが、それが何週間も続くようなら、単なる不調ではなく疾患が関係している可能性を考える必要があります。
2. 胃もたれが続く原因:病気か日常習慣かの見分け方
胃もたれが続く原因を特定するには、「生活習慣」によるものか、「病気」によるものかを見極めることが肝心です。
日常的な原因としては、食べ過ぎ・飲み過ぎ、脂っこいもの・刺激の強い食べ物の大量摂取、夜遅くの食事、睡眠不足、過度のストレスなどがあります。
こういった原因が明らかな場合は、まずそれらを見直すことで改善することが多いです。
一方、病気による胃もたれの原因として挙げられるのは、慢性胃炎・萎縮性胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・ヘリコバクター・ピロリ菌感染・機能性ディスペプシアなどです。
これらは胃粘膜の炎症や傷、消化管の運動機能の乱れなどにより胃内容物の排出が遅れたり、胃の感じ方が過敏になったりすることで胃もたれを引き起こします。
さらに、胃癌もそのひとつ。特に進行した胃癌では、胃の出口付近が狭くなったり、胃壁の動きが制限されたりして食べ物の通過が妨げられ、胃もたれが生じることがあります。
見分け方のポイントとしては、次のようなサインがあれば「病気を疑う」方がよいでしょう
- 胃もたれが明らかな原因なしに続く(食事を変えても改善しない)
- 胃もたれに加えて減量・体重減少がある
- 血便・黒色便が出る、吐血や吐物に血が混ざることがある
- 食後だけでなく空腹時も胃が重い・胃痛がある
- 睡眠を十分取っても疲れが取れない・夜中に胃の不快感で目が覚めるなど
3. 胃癌と胃もたれ:早期発見の鍵と注意すべきサイン
胃癌は、我慢できるほどの症状しかないことが多く、初期段階では胃もたれや軽い胃の違和感程度でしか実感がないことが珍しくありません。
進行すると、胃の蠕動が悪くなる、胃や幽門(胃から十二指腸への出口)が狭くなる、食べ物がうまく通らなくなるといった機能的な支障が出るため、胃もたれが続いたり、食事が満足に摂れなくなったりすることがあります。
注意すべきサイン:
- 胃もたれが数週間以上続くにも関わらず、食生活やストレスを改善しても改善が見られない
- 食後の満腹感・胃の膨張感が強く、少量の食事でも苦しくなる
- 意図しない体重減少(無意識のうちに体重が落ちている)
- 食欲不振
- 吐き気・嘔吐、特に血が混ざるような場合
- 黒い便や貧血症状(顔色が悪く、だるさや息切れが出ることがある)
早期発見が重要な理由は、胃癌は早期であれば内視鏡治療や、比較的低侵襲な治療で治る可能性が高くなるためです。進行してからでは、手術の範囲が広くなり、体への負担や予後も悪くなります。
東京新宿RENA CLINICでは、こうした注意サインがある方には躊躇せず胃カメラ検査をおすすめしており、早期胃癌発見のための体制を整えています。
4. 検査と診断:胃もたれがなかなか治らない場合にすべきこと
胃もたれが改善しない場合、まずは専門医による問診・診察が重要です。いつから症状が出ているか、どのようなタイミングで悪化するか(食後・空腹時・夜間など)、どのような食生活や仕事・ストレス環境か、その他の症状(吐き気・体重変化・便の色など)があるかを詳しく聞き取ります。
続いて行われることが多い検査:
- 胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査):胃・食道・十二指腸の粘膜を直接観察でき、炎症・潰瘍・腫瘍などの有無を確認できます。組織を採取して病理診断をすることも可能です。
- ピロリ菌検査:感染があれば除菌治療により慢性胃炎・萎縮性胃炎の改善および胃癌リスク低減に繋がります。
- 超音波検査・CT検査:胃以外の臓器(肝臓・膵臓など)の病変が関与していないか確認するため。特に腹部全体の症状が出ている場合などに有用です。
- 血液検査:貧血・炎症マーカーなどを調べ、腫瘍マーカーなどの補助的な指標も参考になります。
診断の後は、原因に応じた治療が行われます。胃炎・潰瘍であれば薬物治療、ピロリ菌除菌、食生活の見直し、ストレス管理。機能性ディスペプシアなら、胃運動改善薬や漢方などが使われることもあります。胃癌が見つかった場合には病期に応じた治療計画がたてられます。
5. 改善策と予防法:生活習慣でできること+東京新宿RENA CLINICでのサポート
胃もたれを改善・予防するためには、生活習慣を日常から整えることが非常に効果的です。具体的な改善策:
- 食事内容の見直し:脂っこいもの・高タンパク・刺激物(辛いもの・香辛料・アルコールなど)を控える。食物繊維を豊富に、野菜・果物・発酵食品も取り入れる。
- 食べ方と時間:ゆっくりよく噛む、腹八分目を意識する、夜遅くの食事を避ける、就寝の3時間前までには食事を済ませるようにする。
- ストレス管理・睡眠:十分な睡眠時間の確保、リラックスできる趣味や運動、休息を取ること。自律神経を整えることが胃にも好影響。
- 適度な運動と体の冷え対策:軽いウォーキングやストレッチなどで胃腸の動きを促進。お風呂で体を温めるなど冷えを防ぐ工夫も。
- 定期的な健康チェック:気になる症状が続くようなら、胃カメラ検査などで早期に原因を特定すること。
まとめ
胃もたれが続くというのは、「ただの疲れ」「食べ過ぎ」で片付けていいものかどうか、見極めが肝心です。
日常的な食習慣やストレスなどによる軽い原因であれば、食事内容の改善や睡眠・運動で十分に改善できることが多いですが、それでも症状が数週間以上続く・体重減少がある・吐き気・黒い便などのサインがある場合は、胃癌を含む消化器の疾患を疑う必要があります。
早期発見が治療の成功に大きく影響します。東京新宿レナクリニックでは、こういった注意すべきサインを見逃さず、苦痛の少ない胃カメラ検査や、適切な診療・治療を提供できる体制があります。胃もたれが“続く”時、自分の体と向き合う第一歩として、お気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。