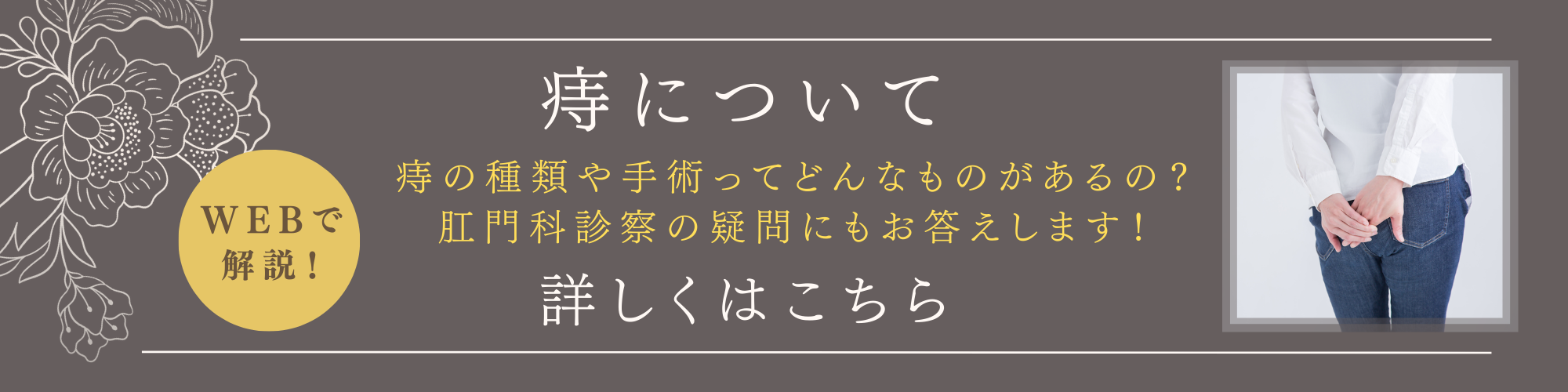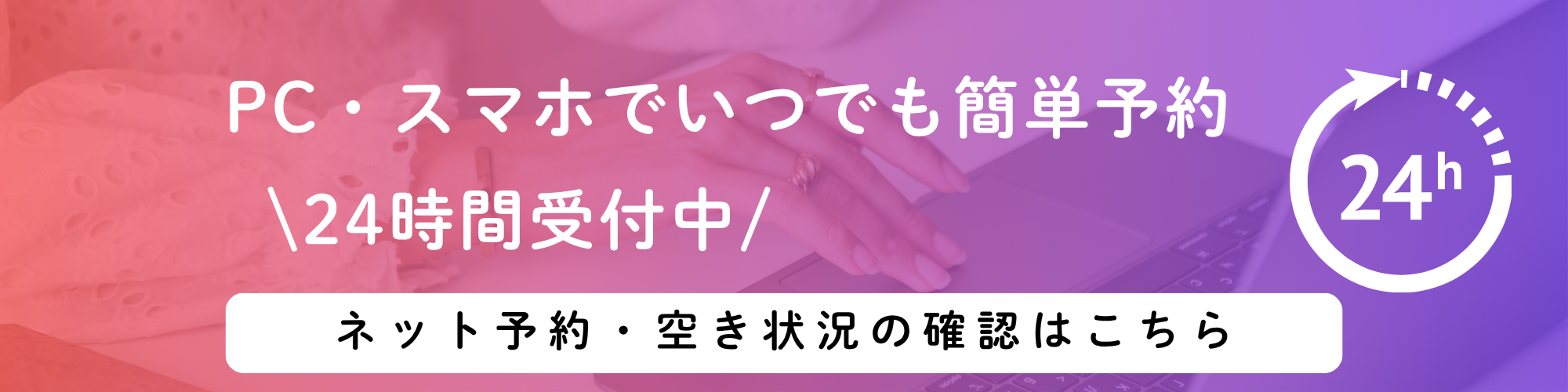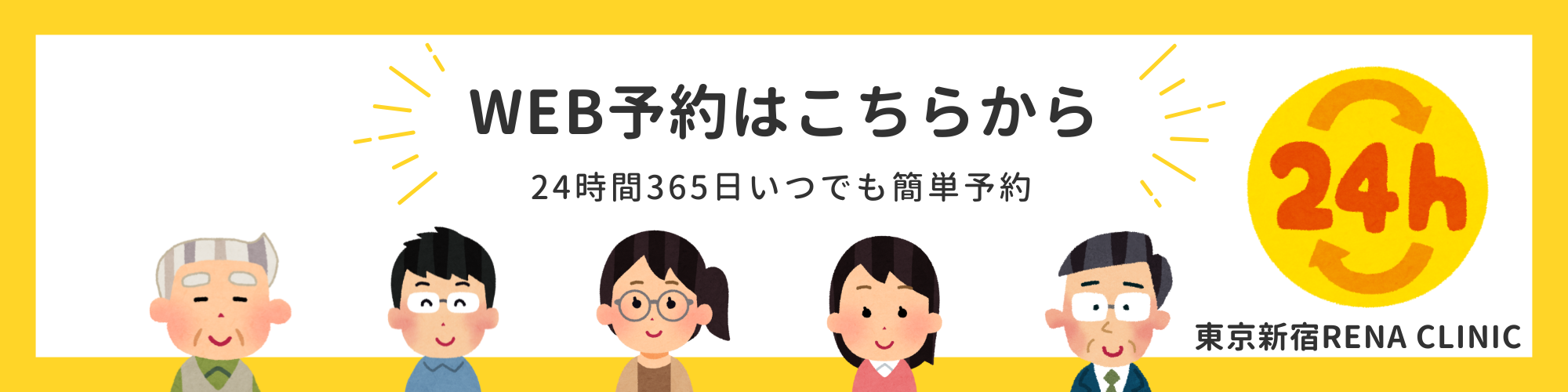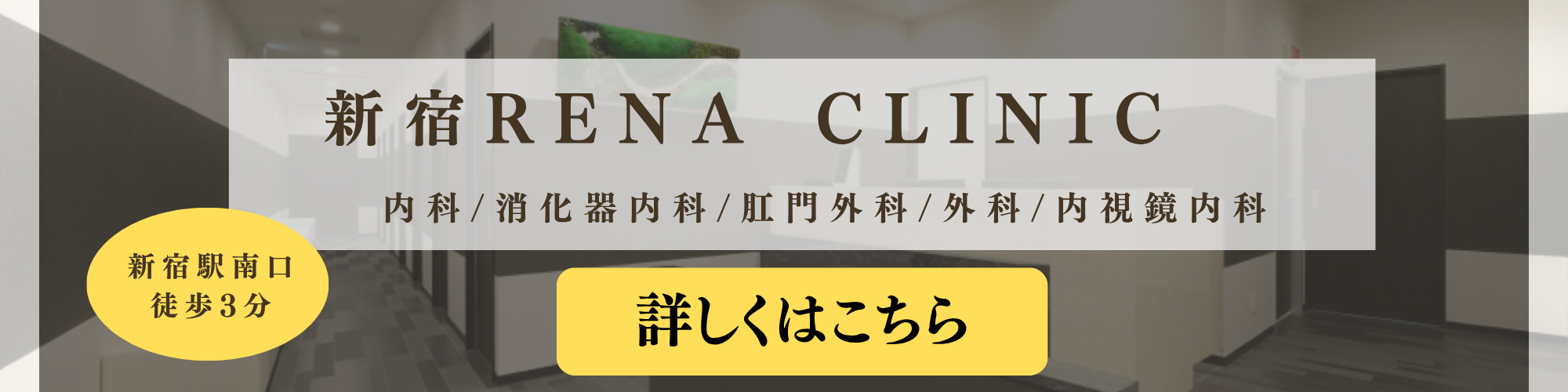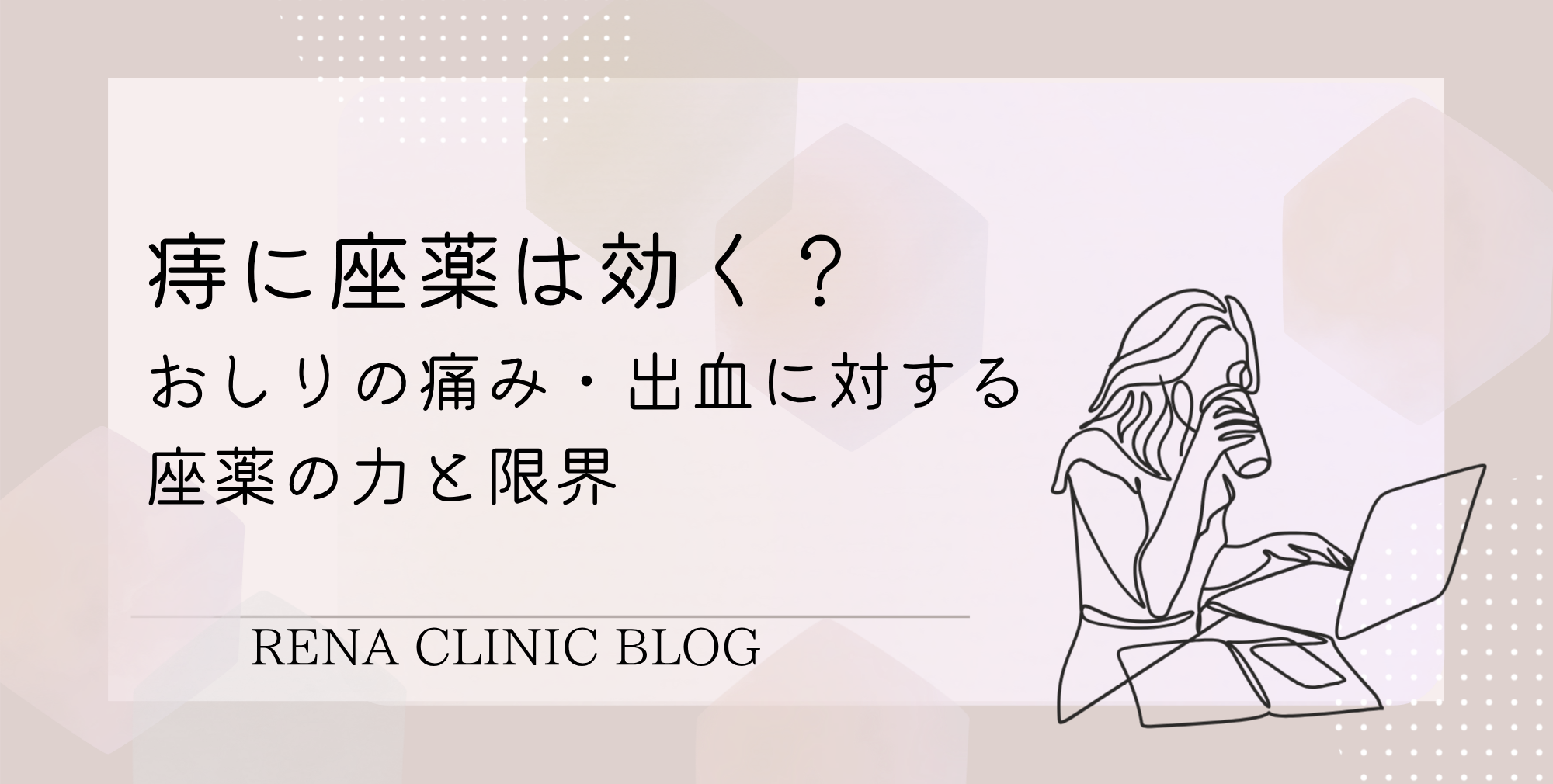
「お尻のいぼ」「出血」「痛み」──この三つが揃うともう立っても座ってもツライ。そんなとき、「座薬」を使おうか悩んだこと、ありませんか?市販薬や病院処方でよく耳にするけれど、「本当に効くの?」「いつまで使えるの?」「副作用は?」などの不安も多いはずです。この記事では、痔の種類ごとに“座薬の効き目”を医学的にも整理しつつ、「どの場合に期待できるか/こんなケースでは別の治療を考えたほうがいいか」を、できるだけ具体的に説明していきます。
目次
1. 痔の種類と座薬の役割とは
痔には大きく分けて「内痔核」「外痔核」「切れ痔」「痔ろう」などがあり、それぞれ症状や治療法が違います。簡単に整理すると、
- 内痔核:肛門の内側の静脈叢が腫れてぽこっとなるタイプ。痛みよりも出血や脱出(トイレットペーパーで押して戻すなど)が問題になることが多い。
- 外痔核:肛門の外側にできて、腫れや痛みが強いことが多い(血栓性外痔核など)。
- きれ痔(裂け痔):肛門の粘膜または皮膚が裂けて痛み・出血。
- 痔ろう:肛門の周囲にトンネルができて膿が出るタイプ。座薬では対応困難なことが多い。
では、座薬はどこに効くかというと、主に内痔核や軽度の出血・炎症・痛みなどの症状に対して有効です。
肛門の奥の内側に直接薬を置くことで、血流を抑えたり炎症を鎮めたりすることが期待できます。また、痛みや腫れを和らげる作用のある成分が含まれるものがあります。
ただし、外痔核で激痛・血栓がある場合や、痔ろう・重度の脱出があるケースでは、座薬だけでは不十分で、手術等や別の治療も視野に入れる必要があります。
2. 座薬が効くケース・効きにくいケース
効きやすいケース
- 内痔核の初期:出血や軽い脱出、炎症・むくみが主な症状の段階では、座薬で炎症を抑えたり、血管収縮成分などで症状軽減が期待できる。
- 痛み・むずむず感・腫れが少ない炎症型の症状:排便のあとジンジンする、むくんでいる感じがある、軽い痛みを伴う場合など。
- 出血が少量で、壊死や感染がないとき:量が少ない鮮血がトイレのあとに見られるケースなど。
効きにくい/限界があるケース
- 外痔核で血栓を伴うもの:急性期の激しい痛みがあるタイプでは、まず鎮痛や排膿、場合によっては外科処置が必要。座薬だけでは痛みのコントロールや改善が遅くなることがある。
- 痔ろう・長期間続いている脱出・重度の肛門組織の痛み:これらは構造的な問題が絡んでおり、薬物だけでは根本的な改善に限界がある。
- 安定しない生活習慣(便秘や排便時に強くいきむ・長時間座る等)による繰り返しの刺激がある場合:座薬の効果があっても再発しやすくなる。
3. 座薬の成分とその効果・注意点
座薬の成分には多くの種類があります。それぞれの特徴を知ることが、効き目を最大限引き出すために重要です。
主な成分例と働き
- ステロイド成分(例:ヒドロコルチゾン等):炎症を強く抑える作用があります。痛み・腫れの軽減には有効ですが、長期使用には皮膚・粘膜の萎縮や感染リスクなどの注意が必要です。
- 血管収縮成分(フェニレフリンなど):腫れを引かせる作用。出血・むくみのあるタイプによく使われます。
- 麻酔成分(リドカイン等):痛みを一過性に取るのに役立ちますが、根本治療ではない。
- 保護剤あるいは収れん・修復作用を持つ成分(例:スクラルファート等):粘膜の保護や修復を助けるもの。最近の研究で、スクラルファート入りの外用・座薬で症状改善が確認されています。
- 5-アミノサリチル酸(5-ASA)のような抗炎症・抗炎化学物質:炎症を抑える作用があり、一定の症状で有効という報告があります。
注意点
- 長期間の頻回使用は避ける:ステロイドを含むものは特に粘膜・皮膚への影響が出る可能性があります。
- 用法・用量を守る:使用回数・期間は指示を守りましょう。自己判断で過度に使うのは危険です。
- アレルギー・刺激感:成分によってはヒリヒリ感、かゆみが出ることがあります。
- 他の治療との併用:便秘対策、生活習慣改善、食事、水分摂取、座浴などと組み合わせることで座薬の効果を高めます。
東京新宿RENA CLINICでは、あなたの症状に合った座薬を処方するとともに、生活習慣のサポートも一緒に行っています。
4. 座薬の正しい使い方と生活習慣でのサポート
座薬は「薬を入れればそれで終わり」ではありません。正しい使い方と生活習慣の工夫があってはじめて効果が発揮されます。
正しい使い方
- 使用前に手を洗う。肛門周囲も清潔に。
- 排便後か、できればぬるま湯で肛門を洗浄・拭く。湿っていたり便があると薬が届きにくくなる。
- 座薬の先端を軽く湿らせて滑りをよくする。肛門を軽く広げて奥まで挿入する。痛みがある場合は無理をしない。
- 挿入後は数分間は肛門をしめて保持すると薬が流れ出しにくくなる。動きすぎると薬が出てしまうことあり。
- 指示された頻度・期間を守る。改善がなければ受診を。自己判断で長期化させない。
生活習慣のサポート
- 便を柔らかく保つ:食物繊維を十分に、毎日の水分摂取を。便秘や硬い便は痔を悪化させる最大の敵。
- 排便時の“いきみ過ぎ”を避ける:トイレで長く粘るのもよくない。
- おしりを冷やさない・血流をよくする:シャワーやぬるま湯浴、入浴、座浴など。
- 運動する・長時間座りっぱなしを避ける:血流改善のため。
- トイレットペーパーの使い方・清潔さ:強くこすらず、刺激を避ける。
まとめ
座薬は、痔のうち「裂肛」「軽度〜中等度の炎症」「出血」「痛み・むくみ」などの症状に対して、局所での改善が期待できる有効な選択肢です。しかし、外痔核の血栓を伴う激しい痛みや、脱出・痔ろうなど構造的な変化が強いケースでは、座薬のみでは十分でないことがあります。また、成分ごとのメリット・リスク、正しい使い方、そして便秘対策などの生活習慣改善の併用が、効果を長持ちさせる鍵となります。もし「座薬を使ってみていいか」「どの座薬がいいか」を迷われたら、まずは専門的に診察を受けることが大切です。東京新宿レナクリニックでは、あなたの症状・ライフスタイルを丁寧に伺い、「座薬が効くかどうか」「どの治療法が最適か」を一緒に判断させていただきます。お気軽にご相談ください。
参考文献(医学論文より)
・Effectiveness and tolerability of rectal ointment and suppositories containing sucralfate for hemorrhoidal symptoms: a prospective, observational study
Marik, A. R.; Miklós, I.; Csukly, G.; 他 International Journal of Colorectal Disease SpringerLink
・5-ASA Suppositories in Hemorrhoidal Disease – DOAJ Canadian Journal of Gastroenterology DOAJ
・Recombinate streptokinase vs phenylephrine-based suppositories in acute hemorrhoids (THERESA‑3)
・Comparison of efficacy and safety between surgical and conservative treatments for hemorrhoids: a meta-analysis
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。