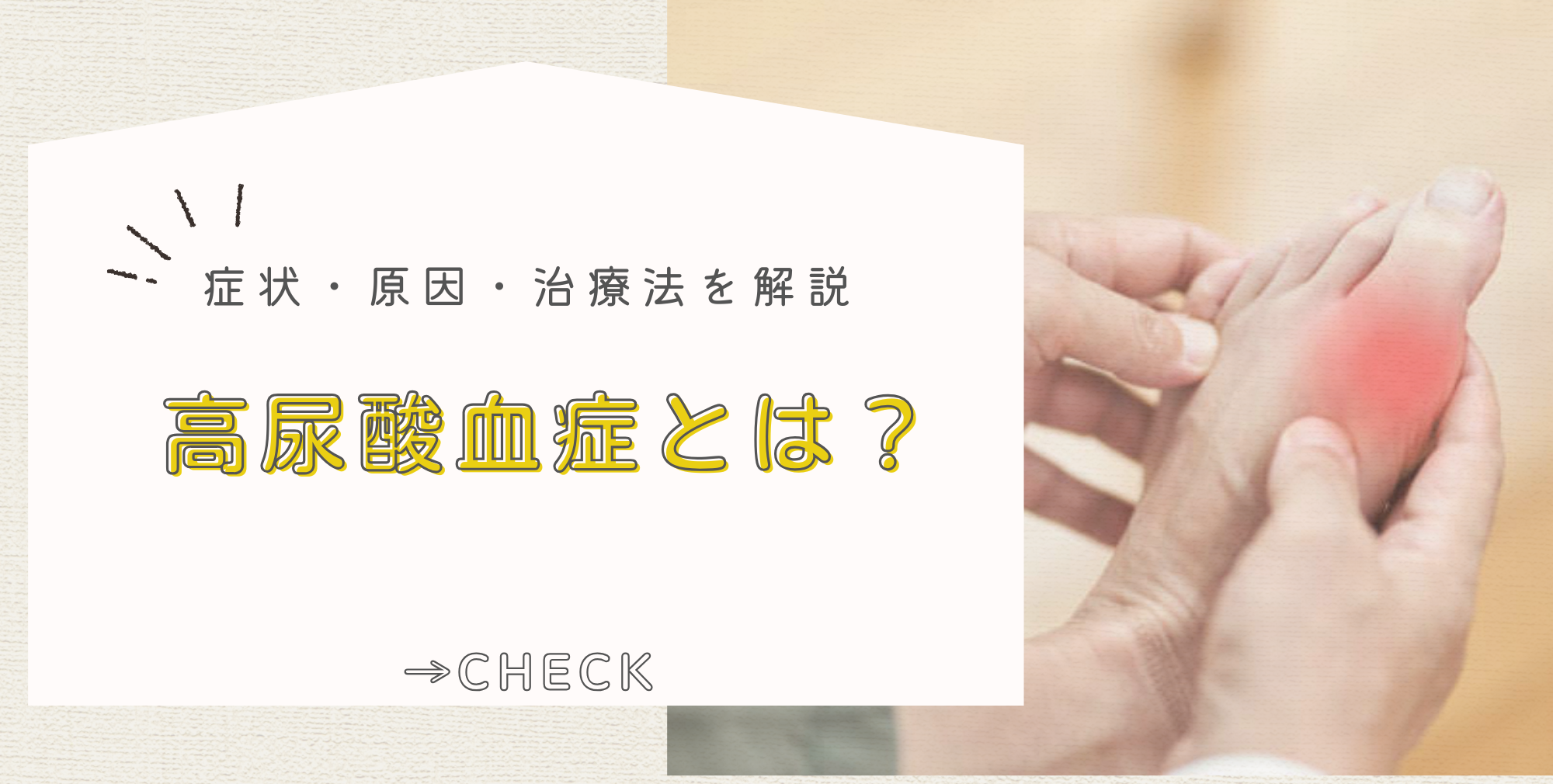
健診で尿酸値が高いって言われたものの、痛みや自覚症状が特にないため「そのうち治るかな…」と放っていませんか?
尿酸値が高い状態=高尿酸血症になると、“痛風発作”や、腎臓・関節にダメージが出たり、尿路結石になったりすることも。しかも、普段の飲み方・食べ方・体型など、ちょっとしたことが引き金になったりします。
この記事では、高尿酸血症の本当のところ—原因・症状・治療・予防までを、わかりやすくまとめます。「血液検査で尿酸が高い」と言われた方は、まずここからチェックしてみましょう。
目次
1. 高尿酸血症って何?その基準と種類
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が正常範囲を超えて高くなっている状態を指します。
具体的には、多くの医療機関で 男性で7.0 mg/dL以上 をひとつの目安とすることが多く、女性では少し基準が異なることがあります。
尿酸とは体内でプリン体という物質が分解される際にできる老廃物で、通常は腎臓や尿で体外に排出されます。しかし、その産生が多すぎるか、排泄が追いつかなくなると血中に尿酸が溜まっていきます。
種類としては大きく次のようなタイプがあります:
- 産生過剰型:プリン体を過剰に含む食品の摂取が多い、あるいはプリン代謝が活発であるなどで尿酸の生成量が多いタイプ。
- 排泄低下型:腎機能が低下していたり、尿酸を排出する機能が弱まっているタイプ。
- 混合型:生成が多く、排泄も低下している両方の要因を持つタイプ。
また、「無症候性高尿酸血症」という段階があります。
これは尿酸値は高いけれど、まだ痛風発作や他の症状が出ていない状態を指します。
この段階で生活習慣を改善できれば、将来の痛風発作や合併症のリスクを下げることができます。
2. 高尿酸血症の症状と放っておくとどうなるか
高尿酸血症そのものは、多くの場合、初期には特に自覚症状がありません。しかし、尿酸が体内で結晶化し、関節に蓄積することで次のような症状や合併症が現れることがあります。

主な症状
- 痛風発作:関節が突然赤く腫れ、激しい痛みを伴います。特に足の親指の付け根に起こることが多く、朝方や夜間に痛みが強くなることがあります。
- 関節の腫れ・熱感・発赤:見た目にも変化があり、触ると熱さを感じることがあります。
- 関節の可動域制限:発作を繰り返すと、関節の動きが悪くなったり痺れ感が出たりすることがあります。
放っておくと起こること
- 尿路結石:尿の中で尿酸が沈積して結石となり、排尿時に激しい痛みを伴います。
- 腎障害や慢性腎臓病:過剰な尿酸・結晶が腎臓にダメージを与え、長期的には腎機能が低下することがあります。
- 痛風結節:皮膚の下などにしこり(結節)ができ、関節の変形や痛みの慢性化を招くことがあります。
- 生活の質の低下:発作による痛みで歩行困難になるなど、日常生活に支障が出るケースも少なくありません。
症状がない高尿酸血症でも、定期的な検査で尿酸値・腎機能・生活習慣をチェックし、必要な対策をとることが合併症を防ぐために重要です。
東京新宿レナクリニックでは、これらの症状とリスクを早期に把握する診察を提供しています。
3. 診断方法と治療の進め方
高尿酸血症が疑われたら、まずは診断を確定するための検査と、状況に応じた治療ステップを理解することが大切です。
東京新宿RENACLINICでは以下のような流れで対応しています。
診断・検査
- 血液検査:血清尿酸値を測定。通常は7.0 mg/dL を超える値が高尿酸血症と診断されることが多い。加えて、腎機能(クレアチニンやeGFR)、肝機能、血糖値、脂質なども合わせて調べます。
- 尿検査:尿中の尿酸排泄量を測定して、「排泄低下型」か「産生過剰型」かのタイプを確認。また、尿に潜血・蛋白がないかを見ることで腎臓への影響を調べることもあります。
- 画像検査等:痛風発作を疑う場合や結石リスクがある場合には、超音波検査などで尿路結石の有無を確認することも。
治療の進め方
- 生活習慣の改善がまず基本:プリン体を多く含む食品やアルコールの制限、体重管理、十分な水分摂取、適度な運動など。
- 薬物療法:生活改善だけで尿酸値が目標値まで下がらない場合や、痛風発作・結石・腎障害のリスクが高い場合には薬を使います。尿酸生成を抑える薬(例:アロプリノール、フェブキソスタットなど)や排泄を促進する薬が選ばれます。
- 発作対応:もし痛風発作が起きた場合、まずは痛み・腫れ・炎症を抑えるための治療(NSAIDsなど)を行い、その後尿酸コントロールを始めるのが一般的です。
治療目標としては、尿酸値を 6.0 mg/dL 以下 に維持することが多くのガイドラインで推奨されています。東京新宿RENACLINICでは、一人ひとりの検査結果・生活背景を考慮して、最適な薬物・非薬物治療プランをご提案しています。
4. 日常でできる予防と生活習慣の見直し
高尿酸血症をコントロールし、痛風発作や合併症を防ぐためには、生活習慣の改善が非常に重要です。東京新宿レナクリニックでは、患者さんそれぞれのライフスタイルを伺いながら無理なく続けられる予防策を提案しています。

食事の工夫
- プリン体を多く含む食材(レバー、干物、魚卵、甲殻類など)は頻度・量をコントロール
- アルコール摂取を減らす。特にビールや日本酒はプリン体に強く影響を与える
- 飲食のタイミングとバランスを意識:野菜を多めに、脂肪分の多い食事は控えめに
運動と体重管理
- 適度な有酸素運動(ウォーキング、水泳など)を週数回行う
- 肥満傾向がある場合は体重を減らすことが、尿酸値・腎機能双方の改善に効果あり
水分摂取と代謝促進
- 飲水量をしっかり取る(体質や状態によるが目安として1日2リットル前後を意識)
- 脱水状態を避ける。発汗後のケアを怠らない
その他の注意点
- ストレス・睡眠不足を減らす
- 薬の影響がある場合は医師と相談(利尿剤や一部薬剤は尿酸を上げることがある)
- 定期的な健康診断で尿酸値・腎機能等をチェックすることが大切
5. 治療後のケアと長期管理のポイント
高尿酸血症は「治療して終わり」ではなく、その後のケアと長期管理が非常に重要です。
東京新宿RENACLINICでは、治療後も患者様が痛みや不安なく過ごせるよう以下のポイントをご案内しています。
- 定期的な尿酸値モニタリング:薬物療法を始めた場合や生活習慣を変えた場合は周期的に血液検査を行い、尿酸値が目標値(一般的には6.0 mg/dL以下)に維持されている
 か確認
か確認 - 合併症のチェック:腎機能・尿路結石・関節の変形などがないか、定期的な検査(尿検査・超音波・画像診断など)を行う
- 痛風発作の予兆対策:前兆(違和感・関節のむくみ・軽い鈍痛など)を感じたら早めに対処する(冷却・痛み止めなど)
- 日常生活の維持:体重管理・水分摂取・定期運動・飲酒制限など、良い習慣を長く維持することが再発防止・合併症予防につながる
- 薬の継続と調整:薬を自己判断で中断しないこと、必要に応じて薬の種類・量の見直しを医師と相談
まとめ
高尿酸血症は、「ただ尿酸値が高いだけ」で放置されがちですが、そのままにしておくと痛風発作、尿路結石、腎機能障害などの合併症を引き起こす可能性が高くなります。症状が出ていなくても、血液検査での尿酸測定、生活習慣の見直し、食事・飲酒・体重管理がまず大切です。もし食事や生活を変えても尿酸値が頻繁に高くなってしまう、あるいは痛風発作を経験している場合は、薬物療法を含めた専門的な治療を検討することが望まれます。早期発見・継続的な管理が、将来の痛みや体の負担を減らす鍵です。東京新宿RENACLINICでは、検査・治療・長期管理をトータルでサポートいたします。気になる「尿酸値の高さ」「関節の痛み」があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。





