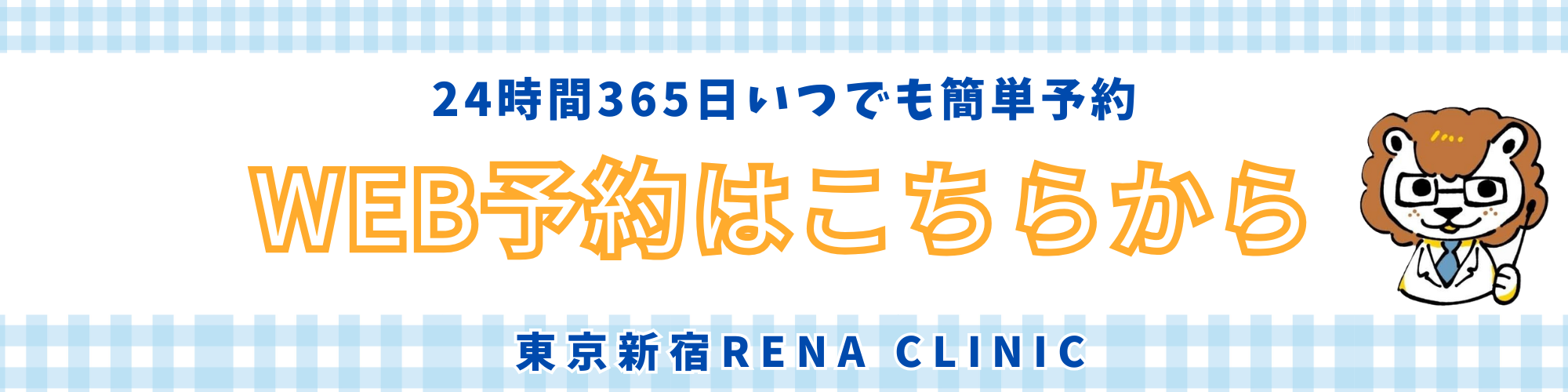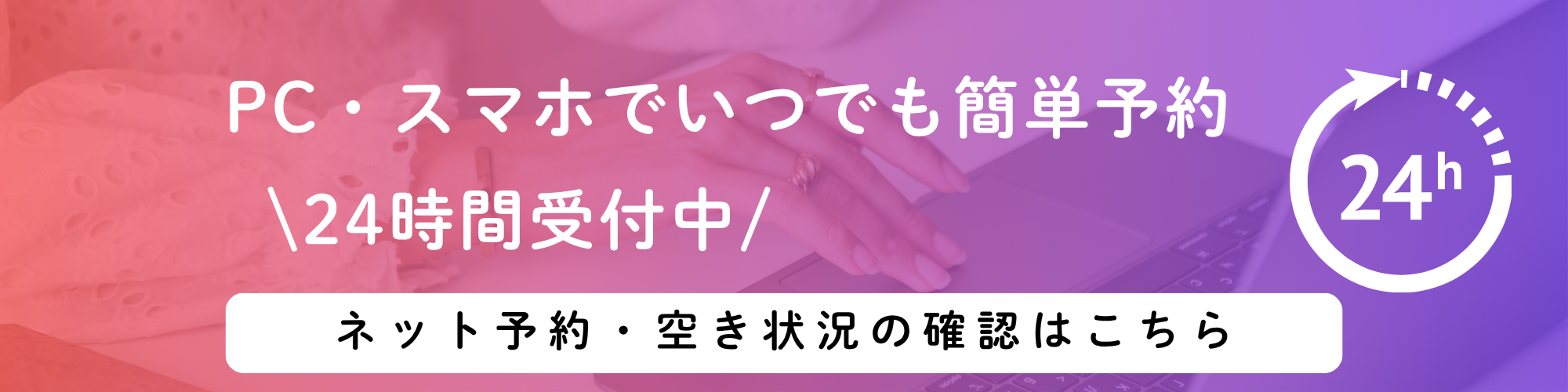「あれ、最近なんだか胃がずっと重い…」そんな“胃もたれが続く”感覚、意外と多くの方が経験しています。
「あれ、最近なんだか胃がずっと重い…」そんな“胃もたれが続く”感覚、意外と多くの方が経験しています。
食後すぐに満腹感が残ったり、胃の中がモヤモヤしてスッキリしなかったり、日によってけっこう長く続いたりすることも。
「まあそのうち治るだろう」と思って放っておいたら、気づいたら1週間、2週間続いていて…。
ここで気になるのが、「このままにして大丈夫?」「病院に行くべき?」という疑問です。今回はそんな不快な胃もたれが続くとき、どう考えたらいいのか、そしてどんなタイミングで受診を検討すべきかを、東京新宿レナクリニックの観点から分かりやすくご紹介します。
目次
1. 胃もたれが続くとは?その原因と見落としがちなポイント
胃もたれとは一般的に、「食後になかなか胃の内容物が消えない感じ」「胃が重い・張る感じ」「食後すぐ満腹になる」「胃が鳴る・ガスが出る」などの症状を指します。
医学的には「胃・十二指腸領域に由来する不快症状」の一部として捉えられており、特に器質的な異常がない“機能性ディスペプシア”も多く含まれます。
まず知っておきたいのは、「なかなか治らない」「繰り返す」「数週間以上続く」などの場合は、少し慎重に考えるべきということです。例えば原因としてこんなものがあります。
- 食事の内容・タイミング:脂っこいもの・刺激物・アルコール・食べ過ぎ・早食いなど。
- 胃の動きの低下・消化管の運動機能の低下(胃排出能の遅れ)や、胃の壁が伸びにくくなる「胃容積適応低下」などの機序も関連があります。
- ストレスや自律神経の乱れ・心理的な影響(いわゆる「腸‐脳連関」)も関与。
- 感染(たとえば ピロリ菌の有無)も要チェック。ガイドラインでは、まずピロリ菌の有無を調べて、陽性であれば除菌を検討することが推奨されています。
2. 自宅でできるセルフケアと生活改善のコツ
胃もたれが気になるとき、まずは生活・食事・習慣を見直すことが大きな助けになります。ここで、実践しやすいセルフケアのポイントをご紹介します。
・食事の工夫
- 脂っこい・刺激の強い食材(揚げ物、香辛料、アルコール)を控えてみましょう。
- 食事は「ゆっくり・よく噛んで」、胃に負担をかけないように。
- 少量×複数回に分けて食べる「小分け食」が有効です。
- 食後すぐ横にならない、寝る直前の食事を避ける。
・生活習慣の見直し
- 適度な運動(ウォーキングなど)で胃腸の動きを促しましょう。
- 良好な睡眠・ストレス管理も大切です。緊張や不安が胃腸症状を増悪させることがあります。
- 喫煙・過度の飲酒は避けましょう。
・薬・サプリ・市販薬の注意
市販の胃薬や抗酸剤などで一時的に楽になることもありますが、あくまで “暫定的な対応” です。症状が長く続く場合は、根本原因を探るためにも受診を検討しましょう。
また、常用している薬(痛み止め、NSAIDs、鉄剤など)が胃もたれの原因になっている可能性もあるため、使っている薬があれば医師・薬剤師に相談してください。
これらのセルフケアを1〜2週間試してみて「少し改善してきた」「違和感が軽くなった」場合は引き続き継続する価値はあります。ただし、「改善しない」「むしろ悪化している」「新たな症状が出た」場合は、次の受診を検討すべきサインです。
3. 「病院に行くべきか」受診を検討するサインとは?
胃もたれが続くとき「そろそろ病院?それとももう少し様子見?」と迷う方も多いでしょう。ここでは、いつ受診したほうがよいか、判断の助けになるサインを整理します。
東京新宿レナクリニックでは、次のような場合を見逃さず受診をおすすめしています。
受診を検討すべき「赤旗」サイン
- 明らかな体重減少を伴う胃もたれ・食欲低下
- 吐血またはコーヒー色吐物/黒色タール便(下血)
- 嚥下困難・持続する嘔吐
- 家族に胃がん・食道がんの既往がある
- 胸・顎・左腕に痛みが放散する腹部の不快感(心臓疾患の可能性を否定できない)
受診すべき“長期化・改善しない”のサイン
- セルフケア開始後2〜4週間たっても改善がほとんどない、あるいは症状が悪化している
- 食後の重さが毎回出る・満腹感が異常に早い・胃が張る感じが頻回
- 胃もたれ以外に腹部の膨満感・ゲップ・吐き気が頻発する
- 胃もたれ症状に加えて、別の消化器症状(便通異常・下痢・便秘)も併発している
なぜこれらの症状で受診を検討するかというと、一定の確率で明らかな器質的疾患(潰瘍・胃がん・胆石・膵疾患など)が隠れているという報告があるからです。
また、疑わしい場合や複数の該当する症状がある場合には上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査を早めに検討すべきとされています。
東京新宿レナクリニックでは、「まず生活改善を試してみる」「改善なければ早めにご相談を」という方針を推奨しており、症状の続く度合いや他の症状の有無を詳細にお伺いした上で、必要な検査・治療のご案内をしています。東京新宿RENA CLINICでは、初診のご相談も歓迎しております。
4. 受診したら何を調べる?検査・問診・診断の流れ
「受診しよう」と決めたら、実際どんな流れ・検査があるのかを知っておくと安心です。以下、一般的な流れと、特に当院で重要視しているポイントを整理します。
問診・既往歴の確認
まず、いつから、どんなタイミングで胃もたれが出たか、食事との関連(何を食べた直後か、満腹感の出方、ゲップ・吐き気の有無)、他の症状(体重減少、嘔吐、便の色・回数、飲酒・喫煙歴、薬の服用歴、精神的ストレスなど)を問診にご記載いただきます。
身体診察・基本検査
体重・体格のチェック、腹部触診・聴診、その他必要に応じて血液検査(貧血・肝機能・膵酵素・腫瘍マーカー等)を行います。
除外・確認すべき疾患の検討
胃もたれの原因として多いのが、 ピロリ菌感染/逆流性食道炎/胆石・胆嚢疾患/胃がん・食道がん/膵疾患/機能性胃腸症など。早期に上部内視鏡検査を受け、原因を特定することが有効です。
必要な検査
- 非侵襲的検査(例:ピロリ菌尿素呼気検査)
- 上部消化管内視鏡(胃カメラ):胃・食道・十二指腸の直接観察。潰瘍・がん・食道炎・胃炎などを確認。
- 胃の動き(胃排出能)・機能検査(必要時)
診断・治療方針の決定
検査結果をもとに、「器質的疾患あり」「器質的な異常なし・機能性ディスペプシアと考えられる」「他の疾患の可能性あり」などに分類され、治療方針が決まります。機能性の場合は、薬物療法(PPI=プロトンポンプ阻害薬、H2受容体拮抗薬、プロキネティクス=胃運動促進薬など)と、生活改善という流れが一般的です。
5. まとめ:早めの対応が安心です
胃もたれが続くと「何となく、そのうち治るだろう」と思いがちですが、日数が経つほど治りにくくなる可能性もあります。また、生活改善だけではカバーできない原因(感染、機能低下、器質疾患など)が隠れていることも否定できません。セルフケアとして食事内容・量・食習慣・ストレス・運動などをまず見直すことは非常に重要ですが、それでも2〜4週間改善がみられない場合や、体重減少・嘔吐・黒便・嚥下困難などの具体的な症状がある場合には、早めの受診をおすすめします。東京新宿レナクリニックでは、こうした胃もたれに関するご相談を受け付けており、必要な検査・治療方針まで丁寧にサポートしております。気になる症状がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。
参考文献
- Talley NJ, Ford AC. Functional dyspepsia. N Engl J Med. 2015;373(19):1853‑1863.
- Evidence‑based clinical practice guidelines for functional dyspepsia 2021. J Gastroenterol. 2022;57(2):47‑61.
- Functional Dyspepsia: A Review of the Symptoms, Evaluation, and Treatment Options. Gastro‑Hep Communications. 2020;?.
- Review article: current treatment options and management of functional dyspepsia. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10(3):168‑174.
- Reassessment of functional dyspepsia: A topic review. Am J Gastroenterol. 2012;107(7):9xx‑9xx.