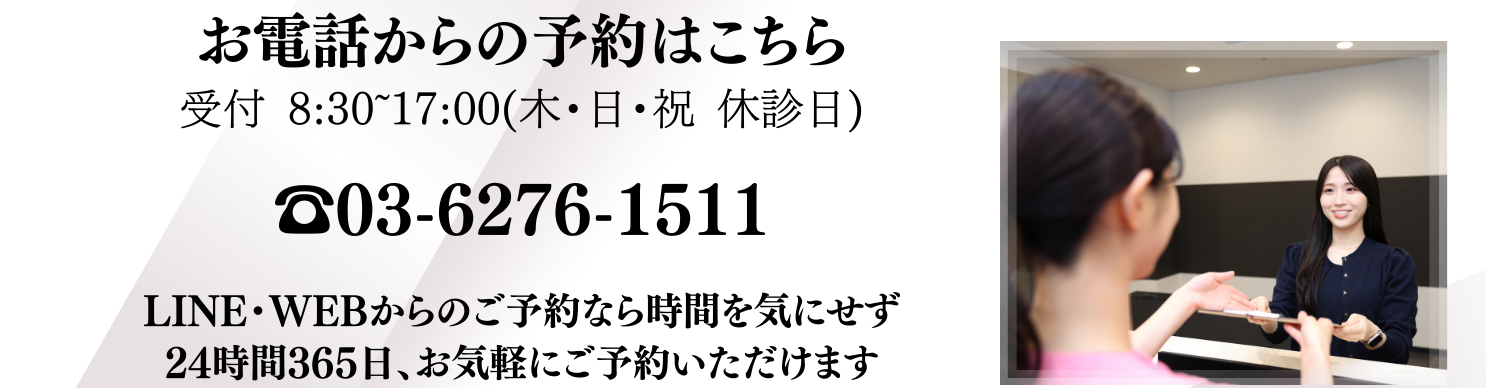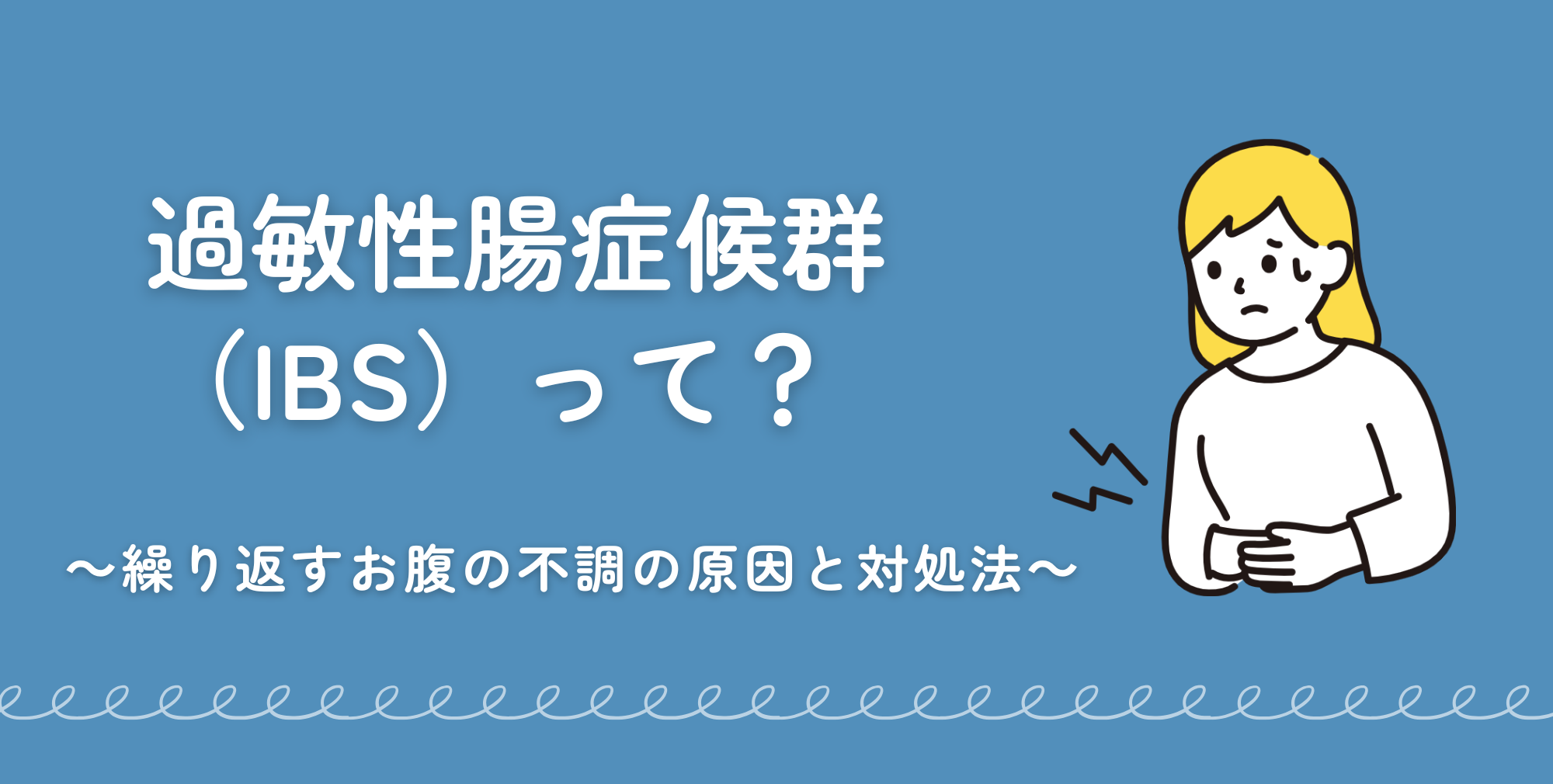
「お腹がゆるくなったり、急に便秘になったり…なんで?」 「ストレスかな?」「過敏性腸症候群(IBS)かも?」 そう思って我慢してる人、多いかもしれません。
でも、実は“IBSじゃなかった”というケースもあるんです。 似たような症状でも、全然ちがう病気が隠れていることも…。
今回は、「過敏性腸症候群って何?」「どう見分けたらいいの?」を、できるだけわかりやすく、やさしくお話しします。
お腹のサイン、見逃さずにケアしていきましょう!
【目次】
- 過敏性腸症候群(IBS)とは?
- 症状のタイプと特徴
- 原因と悪化させる要因
- 診断と治療の流れ
- 「実は違う病気だった」というケースも
- 日常生活でできる対策
- まとめ
1.過敏性腸症候群(IBS)とは?
過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)は、 検査をしてもはっきりとした異常が見つからないのに、腹痛や下痢、便秘といった腸の不調が慢性的に続く病気です。
特に、仕事や学校、外出先などで緊張や不安を感じると症状が強くなる傾向があります。
IBSは、腸の動きや感覚が過敏になっていることが原因とされ、腸と脳の情報伝達が乱れることで発症すると考えられています。
20~40代の働き盛りに多く、ストレス社会の現代では珍しくない疾患です。
生活の質(QOL)を大きく損なうことがあり、「お腹のせいで行動を制限されている」と感じている方も多いです。
過敏性腸症候群は命に関わる病気ではありませんが、長期にわたる不快な症状により、心身のストレスが大きくなるため、早めの対処が大切です。
2.症状のタイプと特徴
過敏性腸症候群にはいくつかのタイプがあり、症状の現れ方に違いがあります。
代表的なタイプは以下の通りです。
- 下痢型:突発的な強い便意や、食後すぐに下痢を起こすのが特徴。通勤途中や外出中に症状が出ることが多く、トイレの場所が気になる傾向があります。
- 便秘型:数日間便通がなく、排便時にも残便感があるタイプ。お腹の張りや不快感を伴うことが多く、女性に多いとされています。
- 混合型:下痢と便秘を交互に繰り返すタイプ。腸のリズムが乱れているのが特徴で、日によって症状が変わることがあります。
- 分類不能型:上記に当てはまらない、日によって異なる症状が現れるタイプ。
症状は心理的な影響を強く受けやすく、試験や会議前、電車に乗るときなど、緊張が高まる場面で顕著になります。
症状の種類と頻度を把握することが、適切な治療に向けた第一歩となります。
3.原因と悪化させる要因
IBSの正確な原因は明らかではありませんが、 「腸の過敏性」「腸の運動異常」「自律神経の乱れ」「ストレス」など、複数の要因が関係していると考えられています。
特に注目されているのが「腸と脳の連携の乱れ」です。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、脳と密接に情報をやりとりしています。
ストレスや不安が続くとこの連携がうまくいかなくなり、腸が過剰に反応し、痛みや異常な便通を引き起こします。
また、食事内容も大きな要因の一つです。
脂っこいもの、アルコール、カフェイン、人工甘味料などは腸を刺激しやすく、IBSを悪化させることがあります。
生活習慣の乱れ、睡眠不足、過労なども影響します。
過敏性腸症候群は一時的なものではなく、体質やライフスタイルと関係が深いため、原因を見つけて生活全体を見直すことが大切です。
4.診断と治療の流れ
IBSの診断は、まず「器質的な異常がないか」を確認することから始まります。
血液検査、腹部エコー、大腸カメラ(内視鏡)などで重大な病気が隠れていないかを調べたうえで、症状の経過やタイプに基づいて診断されます。
IBSは命に関わる病気ではありませんが、放置すると生活の質を大きく損なうため、適切な診断と治療が重要です。
治療には薬物療法、食事指導、生活習慣の見直し、心理的アプローチなどが含まれます。
薬では、下痢や便秘の症状を抑える整腸剤や消化管運動調整薬、ストレスによる過敏性を抑える薬などが処方されます。
また、食事内容を見直す「FODMAP食制限」も有効な場合があります。これは、腸にガスや水分をためやすい糖質を避ける食事療法です。
症状の改善には時間がかかることもありますが、自分に合った治療法を見つけて継続していくことが重要です。
5.「実は違う病気だった」というケースも
過敏性腸症候群と診断されていた方の中には、実際には「潰瘍性大腸炎」や「クローン病」などの炎症性腸疾患(IBD)だったというケースもあります。
これらの疾患は初期症状がIBSと似ていることがあるため、自己判断や市販薬での対応を続けていると診断が遅れる可能性もあります。
- 下痢や腹痛が長引く
- 血便が出る
- 夜間にトイレに行きたくなる
- 体重が減ってきた
- 微熱が続く
といった症状がある場合は、過敏性腸症候群だけで片づけずに、内視鏡検査などの精密検査を受けることが大切です。
特に若年でもIBDの発症は増えており、早期発見・治療が重要です。
6.日常生活でできる対策
過敏性腸症候群の症状を軽減するためには、日常生活の工夫が欠かせません。
まず意識したいのが「ストレス管理」です。睡眠時間を確保する、リラックスできる時間を作る、呼吸法や軽い運動を取り入れるなど、自律神経を整える習慣を心がけましょう。
食生活では、刺激の強い食品や冷たいものを控え、バランスのとれた食事を心がけます。
食物繊維を多く含む野菜や穀物は腸に良いとされていますが、過剰に摂るとガスがたまりやすくなることもあるため、自分の体に合った量を見つけることが大切です。
また、食事の時間を規則正しくし、ゆっくりよく噛んで食べることで、腸への負担が減り症状も落ち着きやすくなります。
IBSは「治らない病気」ではありません。
生活習慣を整え、自分のペースで対策を続けることで、症状のコントロールは十分に可能です。
東京新宿RENA CLINICには管理栄養士が在籍しており、食生活の見直しや改善について専門的な指導を受けていただけます。
7.まとめ
過敏性腸症候群(IBS)は、腹痛や便通異常などが慢性的に続く身近な病気です。
明確な異常がないにもかかわらず、生活に支障をきたすことも多く、早めの対応が大切です。
腸と脳の連携を整えるために、ストレス管理や食生活の見直し、適切な治療が効果を発揮します。
日常生活の工夫や医師のサポートを受けることで、症状の改善と再発予防が期待できます。
お腹の不調に悩んでいる方は、ひとりで抱え込まず、早めに相談することをおすすめします。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 高度な専門医療機関、クリニックで消化器内視鏡・外科治療を習得後、
2024年東京新宿RENA CLINIC開院。