
寒さが本格的になってくると、あったかい鍋が恋しくなりますよね。
でも「牡蠣」は冬の味覚の王様!ぷりぷりで濃厚な味わいは、多くの人の食欲をそそります。でもちょっと待って!
その牡蠣、しっかり火が通っていますか?冬場に増える「ノロウイルス食中毒」の原因として、牡蠣が挙げられます。
今回は、牡蠣とノロウイルスの関係、正しい予防法、もし感染してしまった時の対処法まで、わかりやすくご紹介します。
目次
- 冬に多発!牡蠣によるノロウイルス感染の実態
- ノロウイルスの特徴と、牡蠣が持つリスク
- 安全に牡蠣を楽しむための食べ方・調理のコツ
- 感染が疑われたら?家庭での対処と医療機関受診の目安
- まとめ:冬の味覚を楽しむために私たちができること
目次
1. 冬に多発!牡蠣によるノロウイルス感染の実態
ノロウイルスは、毎年冬になると日本中で感染者が急増する感染性胃腸炎の原因ウイルスです。
その感染源の代表格が「牡蠣」をはじめとする二枚貝。特に11月から3月にかけての寒い時期は、ノロウイルスによる食中毒の発生件数がピークを迎えます。

ノロウイルスは感染力が非常に強く、たった数個のウイルス粒子でも人に感染することが知られています。牡蠣は海水をろ過して栄養を摂取するため、ノロウイルスに汚染された海域で育ったものはウイルスを体内に蓄積してしまうことがあります。そしてそれが、加熱不十分な調理や生食によって人の体に入り、感染を引き起こすのです。
実際、冬になると「牡蠣を食べたあとに下痢・嘔吐が止まらない」といった患者さんが、東京新宿レナクリニックにも多く来院されます。感染後の症状は、突然の吐き気や嘔吐、激しい下痢、腹痛など。高熱を伴うこともあります。小さなお子さんや高齢者、免疫力が低下している方では重症化する可能性もあるため、注意が必要です。
感染を防ぐには、まず「牡蠣にはノロウイルスが潜んでいる可能性がある」という意識を持つことが大切。生食用と加熱用の牡蠣の違い、適切な調理法、食べるタイミングなど、基本をしっかり押さえることが重要です。
2. ノロウイルスの特徴と、牡蠣が持つリスク
ノロウイルスは非常に小さく、アルコールでは死滅しにくいという性質を持っています。
ウイルスは乾燥に強く、低温環境下でも長期間生存可能なため、冬の時期に感染が広がりやすくなるのです。
ノロウイルスに感染した牡蠣を食べたとしても、見た目も匂いもまったく変わらないため、汚染されているかどうかは判断が難しいです。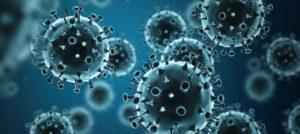
「新鮮だから大丈夫」「生食用って書いてあるから安心」と思いがちですが、実際には生食用牡蠣でも感染例が報告されています。
生牡蠣がリスクとなる大きな理由は、ウイルスが体内に蓄積していても、通常の洗浄や下処理だけでは除去できないからです。
また、軽く炙ったり表面だけ火を通した調理方法では、中心部にいるウイルスを死滅させることができません。
ノロウイルスは中心温度90℃以上で90秒以上の加熱が必要とされています。
さらに、ノロウイルスは人から人へもうつる厄介な存在です。例えば、調理した人が感染していた場合、調理器具や手指を介して家族全体に感染が広がるケースもあります。感染しても症状が出ない人もいるため、自覚がないまま周囲にウイルスを広げてしまうこともあります。
3. 安全に牡蠣を楽しむための食べ方・調理のコツ
「じゃあ牡蠣は食べない方がいいの?」と思われる方もいるかもしれません。
でも、ご安心ください。しっかりとした調理と衛生管理を心がければ、冬の味覚・牡蠣を安全に楽しむことができます。
まず基本中の基本は「十分な加熱」です。中心部までしっかり火を通すことが何より重要。
具体的には、牡蠣の中心温度が90℃以上で90秒以上キープされる状態を目安にしましょう。鍋料理などでは、見た目で判断せず時間で計るのがおすすめです。
次に注意したいのが、調理器具や手指の衛生です。感染者が触れたまな板や包丁、食器からも二次感染が起こるため、使い終わったら熱湯や塩素系漂白剤で消毒を徹底しましょう。
調理前後には石けんを使った丁寧な手洗いも忘れず行いましょう。
また、食材の保存方法も大切です。加熱前の牡蠣は5℃以下で保存し、調理後のものはなるべく早く食べきるようにしましょう。再加熱する際も、再度しっかり中心まで温めることが重要です。
さらに、リスクの高い人—特に乳幼児、高齢者、妊娠中の方、免疫が低下している方—は、生食や加熱不十分な牡蠣を避けるのが望ましいです。家庭での小さな配慮の積み重ねが、感染リスクを減らすことに繋がります。
4. 感染が疑われたら?家庭での対処と医療機関受診の目安
牡蠣を食べた後、吐き気や腹痛、下痢が続くと「ノロウイルスかも…」と不安になりますよね。
ここでは、感染が疑われた時の基本的な対処法と、受診のタイミングについて解説します。
まず、ノロウイルスは通常、1~3日程度で自然に回復する病気です。特効薬はなく、対処療法が中心となります。
最も大切なのは「脱水を防ぐこと」。嘔吐や下痢で失った水分と電解質を補うために、経口補水液やスポーツドリンクなどでこまめに水分補給を行いましょう。
食欲がない時は無理に食べず、胃腸を休ませるのが基本。
無理に固形物をとると吐き気を悪化させることがあります。
下痢止めの薬は、ウイルスを体外に排出するのを妨げてしまうこともあるため、医師の指示がない限り自己判断での使用は避けましょう。
感染を広げないためにも、家族との接触は最小限に。特に、調理や食事の配膳は別の人が行うようにしてください。吐しゃ物や便を処理する際は手袋・マスクを着用し、処理後は塩素系漂白剤でしっかり消毒を行いましょう。
医療機関の受診が必要なケースとしては、
- 水分が取れない
- 嘔吐や下痢が長引く
- 血便が出る
- 意識がもうろうとする
などが挙げられます。
こうした症状がある場合、速やかに医師の診察を受けてください。
東京新宿レナクリニックでは、ノロウイルスを含む感染性胃腸炎の診療にも対応しております。不安な症状がある方は、お気軽にご相談ください。
5. まとめ:冬の味覚を楽しむために私たちができること
冬のごちそう、牡蠣は、正しく調理すれば安全に美味しく楽しむことができます。
ただし、ノロウイルスのリスクを知り、加熱・衛生・予防に気をつけることが大前提です。
特に冬場はウイルスの感染力が高まる時期ですので、手洗いや消毒、体調管理にも一層の注意が必要です。
「牡蠣=危険」ではなく、「知って備える」ことが大切。東京新宿RENACLINICでは、冬の感染症対策を含め、皆さまの健やかな毎日をサポートしています。安心して冬の味覚を楽しむために、ぜひお気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。





