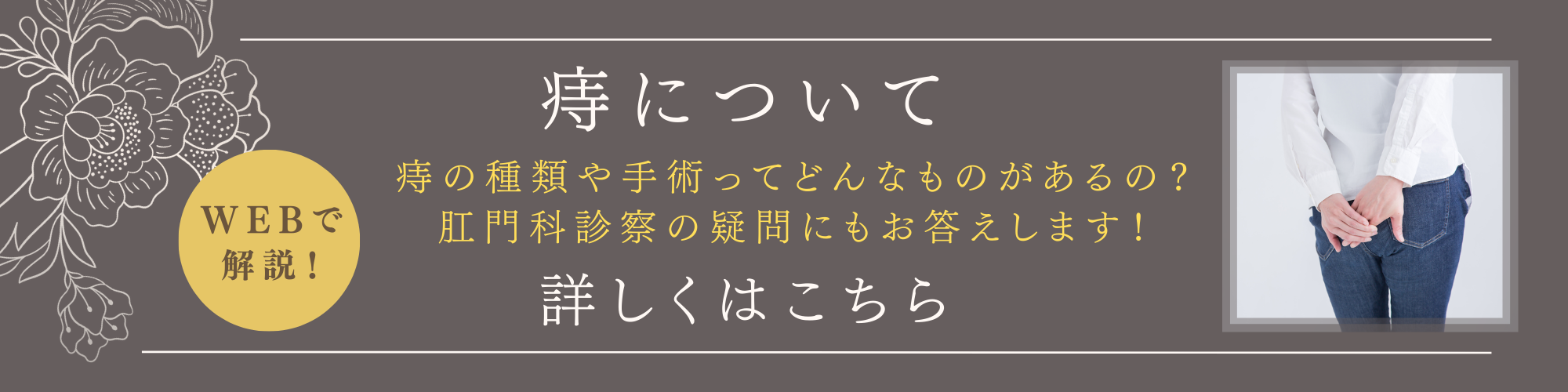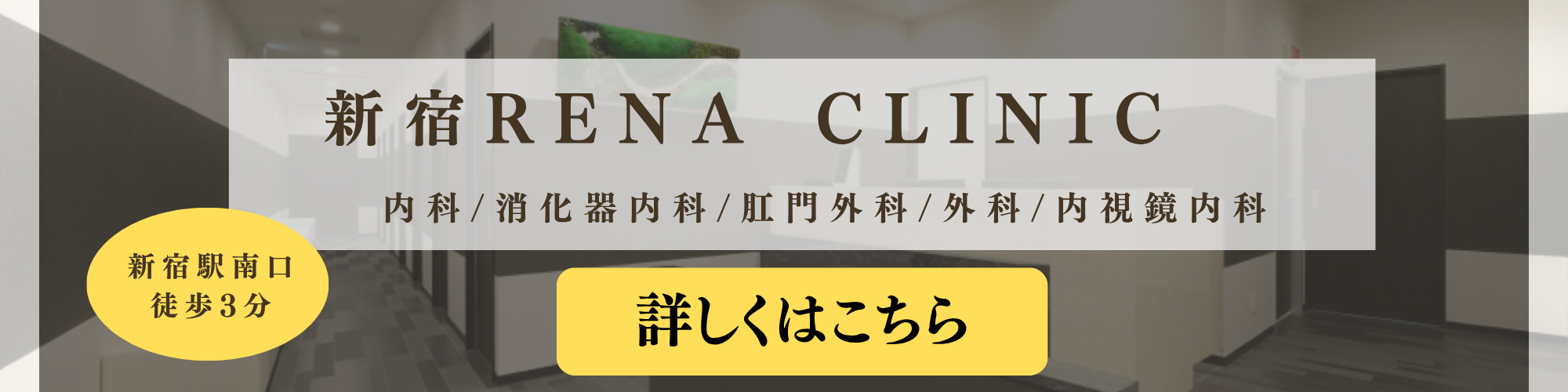「おしりがなんだか痛い…」「トイレットペーパーに血がついてるかも…」そんなとき、「まあ大丈夫だろう」と放っておいていませんか?
でも、案外思い切って早めに相談しておいたほうがラクになることも多いのです。
おしりのトラブルは恥ずかしさから受診を迷う方が多いですが、症状を放置すると長引いたり、重症化のリスクが高まったりすることも。
今回は「本当に肛門科で診察を受ける必要があるのか」をテーマに、どんな症状なら受診すべきか、まず自分でできるチェックは何か、そして受診時には何を期待できるかを、できるだけわかりやすく解説します。
目次
1. なぜ「おしり」の診察が必要?肛門科とは何を診る?
まず、「肛門科=おしり専門の診察」という言い方をしていますが、専門的には「肛門・直腸・下部消化管」のトラブルを扱う「大腸肛門科」という分野です。
痛み・出血・かゆみ・異物感・便通の変化など、“おしりまわりの違和感”は、実は日常的によくあるものながら、自分だけで判断しづらい症状でもあります。
たとえば、出血・かゆみ・異物感などを「たぶん痔だから大丈夫」で済ませてしまうと、実は「肛門裂傷」「痔瘻」「直腸や大腸のポリープ・腫瘍」といった重大な問題を見逃す可能性があります。
症状が軽くても、「診察を受けた方がいいのかも」と思ったら、早めに専門医に相談するメリットは十分にあると言えます。
2. 「この症状なら受診を考えよう」– 自分でできるチェックポイント
では、もしかして肛門科の診察が必要かも、と感じた時、自分でチェックできるポイントをご紹介します。症状のサインを知っておくことで、「放っておいて大丈夫かな?」という迷いが少なくなります。
チェックポイント
- トイレットペーパーに鮮やかな赤い血がつく、あるいは便に血が付いている。

- 肛門まわりに「かゆみ」「違和感」「ジンジン・ヒリヒリ」といった痛みがある。
- 便が硬くて出にくい、排便時にいきみが伴っている。
- 肛門の出口あたりに“しこり”や“ふくらみ”を触れる、あるいは“飛び出す感じ”がある。
- 排便後、肛門まわりに違和感や残便感が続く。
- 便通が急に変わった(便秘が続く・下痢が続く)または30分以上トイレに座ってしまう。
これらの症状のうち、特に「出血」「しこり・ふくらみ」「便通異常」が複数あれば専門医の診察を受けるタイミングと言えます。出血がある場合には「肛門以外の原因(大腸ポリープ・がんなど)を除外」するため、診察と場合によっては検査が必要とされています。
また、年齢や家族歴もポイントです。40歳以上、または大腸がんなどの家族歴がある方は、軽い出血でも受診を前向きに検討したほうがよいとされています。
「恥ずかしい…」「大変そう…」と感じる方も多いですが、実際には診察は短時間で終わることが多く、早めに受診するほど治療もシンプルになるケースが多いです。こうした“早期相談”が後々の安心につながるのです。
3. 診察・検査ってどんな流れ?実はハードル低めです
実際にどんな流れで肛門科の診察が行われるのかを知っておくと、受診へのハードルが下がります。ここでは、一般的な流れをわかりやすくご説明します。
1.問診・症状の確認
まず、事前にWEB問診票を記入いただき、最近の症状(出血の有無・便通・痛み・違和感・しこみ感)や生活習慣、既往歴、家族歴などを記載していただきます。
さらに出血の頻度・色・量、便の状態(硬さ・回数)、肛門まわりの症状などを細かく記載いただけると、その後の診察がスムーズです。
その上で医師が問診内容を確認しながら、お話をお聞きします。
2.視診・触診 服を一部脱いでいただき、横向きの体勢で肛門・直腸まわりを目視・触診します。
服を一部脱いでいただき、横向きの体勢で肛門・直腸まわりを目視・触診します。
外から見える“しこり”“腫れ”“皮膚の変化”などが確認できます。
指で肛門内を軽く触る「直腸指診」や「直腸鏡検査」も行われ、腫瘍・ポリープ・肛門管の異常の有無をチェックします。
こうした診察だけでも、症状の原因(多くは痔核・裂肛・肛門周囲皮膚炎など)が推定できます。
3.説明・治療方針の提示
診察の結果に基づき生活習慣の見直しや薬剤処方、軽度痔核なら経過観察や硬化療法、重症例なら手術療法など、患者さまに合った選択肢をご提案します。
東京新宿レナクリニックでは、来院された方が「来て良かった」と思っていただけるよう、わかりやすく説明し、プライバシーにも配慮した空間を心がけています。
4. 受診後に得られる効果・安心感と、先送りのリスク
受診した場合に得られる効果・安心感
- 症状の原因が明確になり、「これは痔だから大丈夫」と安心できることもあります。
- 生活習慣・食習慣・排便習慣に基づいた改善策を管理栄養士や医師などから直接指導してもらえるため、再発・悪化の予防につながります。
- 出血・しこり・痛みなどが長引く前に適切な処置を受けることで、症状改善までの期間が短くなる傾向があります。
- 重大な疾患の可能性を早期に排除でき、精神的な不安が軽くなります。
先送り・受診をためらった場合のリスク
- 症状が進行して「しこりが飛び出す」「血の量が増える」「痛み・かゆみが強くなる」など、治療が複雑になる可能性があります。
- 出血を繰り返すことで貧血になる・肛門周囲の炎症を伴う・痛みで排便が困難になる…という二次的な問題が出てくることがあります。
- 「痔かな?」と自己判断して放置していたら、実はポリープ・腫瘍・炎症性腸疾患だったというケースがあります。
- 症状が悪化すると、仕事・運動・座る時間・旅行など日常生活に影響が出てしまうこともあります。
5. まとめ
出血・かゆみ・異物感・便通異常など、おしりまわりの違和感は軽く見過ごしがちですが、放置していると手遅れになってしまうケースもあります。早めに診察を受けることで、原因が明らかになり、適切な対策・治療に移ることができる上、不安も軽減されます。おしりの悩みは“恥ずかしいこと”ではなく“早めに相談して解決すべきこと”です。東京新宿レナクリニックでは、デリケートなお悩みに寄り添い、安心して相談できる診察体制を整えています。どうぞお気軽にご相談ください。
- 監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。
参考文献
- Colorectal Cancer Risk in Patients with Hemorrhoids: A 10-Year Population-Based Retrospective Cohort Study/Chen YL 他/Journal of Gastroenterology and Hepatology
- Risk Factors for Hemorrhoids on Screening Colonoscopy/Peery AF 他/PLoS One
- Hemorrhoids: Diagnosis and Treatment Options/Johanson J 他/American Family Physician
- Office Evaluation of Rectal Bleeding/Kodner IJ 他/Journal of the American College of Surgeons