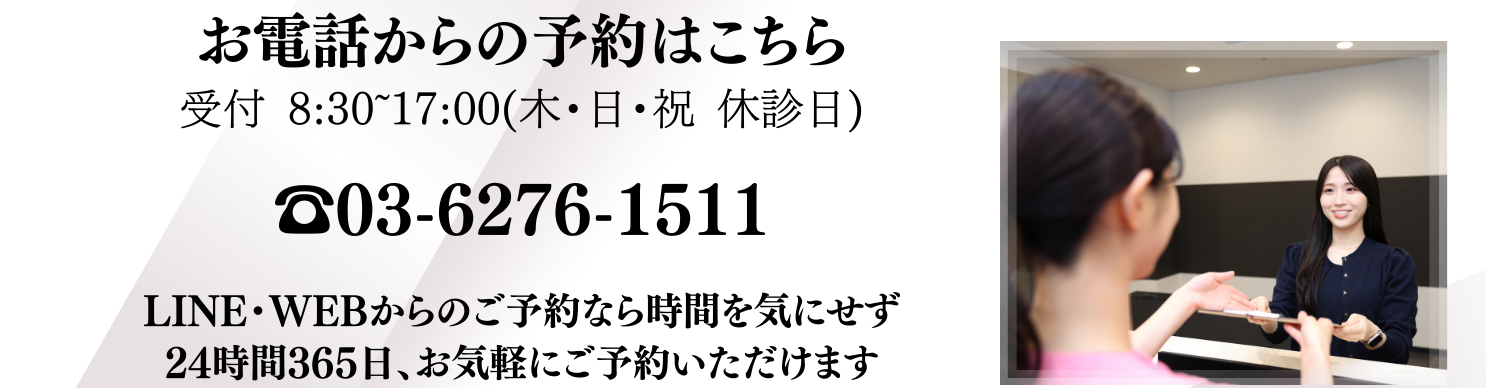こんにちは!新宿RENA CLINICです!
今日は、聞いたことはあるけど詳しくはよく知らない…そんな方も多い「アニサキス」について解説します。
お刺身やお寿司を食べるときにちょっと気になる、あの寄生虫。
実際にどんな危険があるのか?どうやって予防できるのか?
知っておいて損はない情報をわかりやすくお届けします!
目次
- アニサキスとは?魚に潜む見えないリスク
- 実際にあったアニサキス症の症例と苦しみ
- 内視鏡による診断と治療の流れ
- 食中毒を防ぐための具体的な予防策
- よくある誤解とアレルギーのリスク
1.アニサキスとは?魚に潜む見えないリスク

アニサキスは、生魚に寄生する線虫の一種で、主にサバ、アジ、イカなどに多く見られます。
魚を生で食べることで人体に入り込み、胃や腸の壁に侵入することで激しい腹痛を引き起こします。
海辺の地域では特に感染の頻度が高く、実際に年間を通じて複数の症例が報告されています。
新鮮で美味しい刺身や寿司にもリスクがあるため、「目に見えない危険」があることを理解しておくことが大切です。
2.実際にあったアニサキス症の症例と苦しみ
アニサキス症では、突然激しい胃の痛みを訴えて救急外来を受診される方が少なくありません。
中には腹痛の原因が分からず不調が続いた末に検査でアニサキスが見つかるケースもあります。
なかでも重症例では、胃の中に5匹以上のアニサキスが寄生し、アナフィラキシーショックを起こして血圧が低下するなど、生命に関わる危険な状態になることもあります。
魚介類の摂取が直接的な引き金となることが多く、体調の急変には注意が必要です。
3.内視鏡による診断と治療の流れ
アニサキスの確定診断と治療には内視鏡検査が有効です。
胃の内部をカメラで確認し、寄生虫を発見次第、専用の鉗子で摘出します。
虫体は非常に小さいため見つけにくい場合もありますが、経験を持つ医師が丁寧に確認し、確実に除去します。
アニサキスは胃酸にも強く、自然排出されることは少ないため、内視鏡による迅速な処置が痛みの軽減と合併症の予防に重要です。
早期受診が回復のカギとなります。
4.食中毒を防ぐための具体的な予防策
アニサキス症を予防するためには、生魚を安全に扱うことが重要です。具体的には以下の対策が効果的とされています:
- 魚を購入後すぐに内臓を取り除く
- -20℃以下で24時間以上冷凍する
- 十分に加熱(中心温度60℃以上で1分以上)する
また、しめ鯖や炙り系の加工品でも加熱不十分な場合にはアニサキスが生きている可能性があります。
調理前の目視による確認もある程度有効ですが、完全に防ぐことは難しいため、信頼できる調理・流通過程であることが安心材料になります。
5.よくある誤解とアレルギーのリスク
アニサキスによる症状は「噛まれて痛い」と誤解されがちですが、実際にはアレルギー反応によって痛みが生じると考えられています。
そのため、虫体が体内で死んでも症状が続くことがあり、放置すると炎症や腸閉塞などにつながるリスクもあります。
施設によってはアレルギー薬の投与で様子を見ることもありますが、 最も確実なのは内視鏡による直接の確認と摘出です。
症状を軽視せず、速やかに受診することが大切です。
まとめ
アニサキス症は、誰もが身近に経験する可能性のある食中毒の一種です。
特に刺身や寿司などの生魚を好む方にとっては、正しい知識と予防意識が不可欠です。
痛みが急に現れた場合や、食後の不調が続く際には、内視鏡による検査・治療が早期回復の鍵となります。
東京新宿RENA CLINICでは、迅速な内視鏡診断・治療が可能ですので、気になる症状があれば、いつでもご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 多くの病院、クリニックで消化器内視鏡・外科治療を習得後、
2024年東京新宿RENA CLINIC開院。