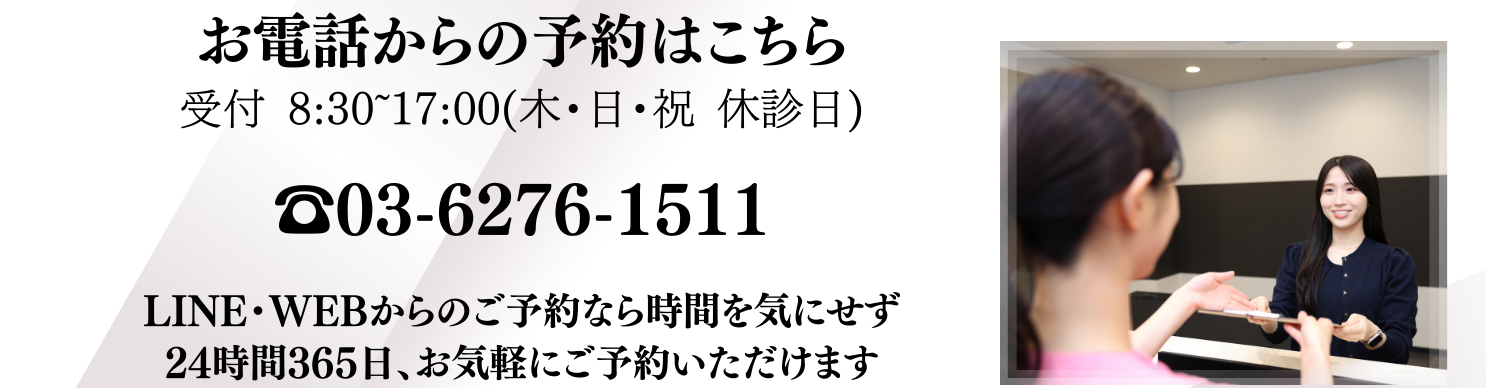「便に血が混ざる」「便通に変化がある」「お腹が張る感じが続く」――そんな症状があると、「まさか直腸癌?」と不安になる方もいるでしょう。
直腸癌は大腸の肛門に近い部分で起こるがんで、進行するまで自覚症状が乏しいのが特徴です。
しかし実は、リスク要因には生活習慣、遺伝、炎症性腸疾患など、予防や早期発見の手立てになるものもあります。
本記事では直腸癌の原因に焦点を当て、どんな工夫や検査がリスク軽減に役立つのかを解説していきます。
目次
1. 直腸癌ってどんながんなの?|基礎知識と症状
直腸癌は、大腸の直腸部分に発生するがんで、便の出口に近い部分です。
大腸全体にできる腺腫性ポリープが長い期間をかけてがん化するケースだけでなく、炎症性腸疾患や遺伝疾患によっても発症リスクが高まります。

症状としては
- 血便や下血、黒色便
- 便通の変化(下痢→便秘、便が細くなるなど)
- 排便時の痛みや不快感
- 腹痛、腹部膨満感
- 体重減少や貧血症状
初期には無症状も多く、進行するにつれて上記のような異変が現れます。
米国では45歳から、99%以上の発症が50歳以上とされており、近年は若年層でも増加傾向。日本でも高齢化とともに件数は増える一方で、若年層への注意も必要です。
2. 生活習慣が引き起こすリスク要因
多くの場合、直腸癌は遺伝要因よりも生活習慣や環境的要因が関与します。
【主な生活リスク】
- 高脂肪・高糖質・赤身肉・加工肉食品(ハム・ソーセージなど)の過剰摂取
- 肥満・内臓脂肪の増加
- 喫煙や過度の飲酒
- 運動不足
- 食物繊維不足
- NSAIDsやスタチンなどの薬剤服用
これらは、腸内での胆汁酸濃度や慢性的な炎症を高め、ポリープのがん化を促進したり、がんそのものの発生率を引き上げたりするメカニズムがあります。
例えば、赤身肉を週数回以上食べる人はリスクが高く、さらに肥満やアルコール摂取は相乗的に発癌率を高めることもわかっています。
3. 遺伝性・炎症性腸疾患が関係するケース
生活習慣以外にも以下のような背景がある場合は、直腸癌のリスクが高まります。
1. 家族歴・遺伝性症候群
家族に大腸癌や直腸癌の既往があると、リスクは2〜3倍に増加します。
また、リンチ症候群(HNPCC)やFAP(家族性大腸腺腫症)などの遺伝性疾患は、がんの発生リスクが非常に高く、生涯で50%以上になることもあります。
2. 炎症性腸疾患(IBD)
潰瘍性大腸炎やクローン病を長期患っている場合、10年、20年と経過するごとに直腸・大腸がんのリスクは数倍〜十数倍に上昇します。
3. その他の背景
放射線治療部位にがんが発生するケースや、特定の腸内細菌が関与する場合もあります。
こうした高リスク群は、通常より精度の高い検診スケジュールが推奨されています。
4. 検査や予防でリスクを下げる方法
直腸癌は、ポリープをいかに早く見つけ、除去するかが予防の鍵です。
スクリーニング検査
- 大腸内視鏡:ポリープの有無や粘膜異常を観察・組織採取できるため、最も精度が高く、定期的な検査が理想とされています
- 便潜血検査:簡便で有効ですが、複数回にわたって行うことが望ましいです
生活習慣の改善
- 赤身肉・加工肉食品の摂取を控え、野菜・果物・食物繊維を豊富に
- 適度な運動と体重維持
- 禁煙・飲酒を控える。
5. 早期発見でどう変わる?症状・受診の目安
直腸癌は早期に発見できれば治療成績が良好です。ステージ0やI期で見つかれば、内視鏡切除や局所切除でも治癒が可能です。
自覚症状が出たときは…
- 血便・下血がある
- 便が細くなる・便通が変化する
- 腹痛・下腹部不快感
- 説明できない体重減少や貧血
こうした症状が1〜2週間続く場合は、速やかに受診してください。
特に若年者での増加も報告されており、症状があれば年齢に関わらず専門医の診察が必要です。
まとめ
直腸癌の原因には、生活習慣による後天的な要因、遺伝性疾患や炎症性腸疾患などの背景、そして腸内環境が影響します。
重要なのは、これらを理解し、定期的な検診(特に大腸内視鏡)と生活習慣の改善で早期発見・予防に努めることです。
特に、便潜血や内視鏡検査は腺腫性ポリープの段階での発見・切除が可能で、将来的ながんのリスクを大きく減らせます。
血便や便通の変化を感じたら、ためらわずに専門医へ。東京新宿RENACLINICでは、リスク評価から検査、生活指導にいたるまで、患者様に寄り添った診療を行っております。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。