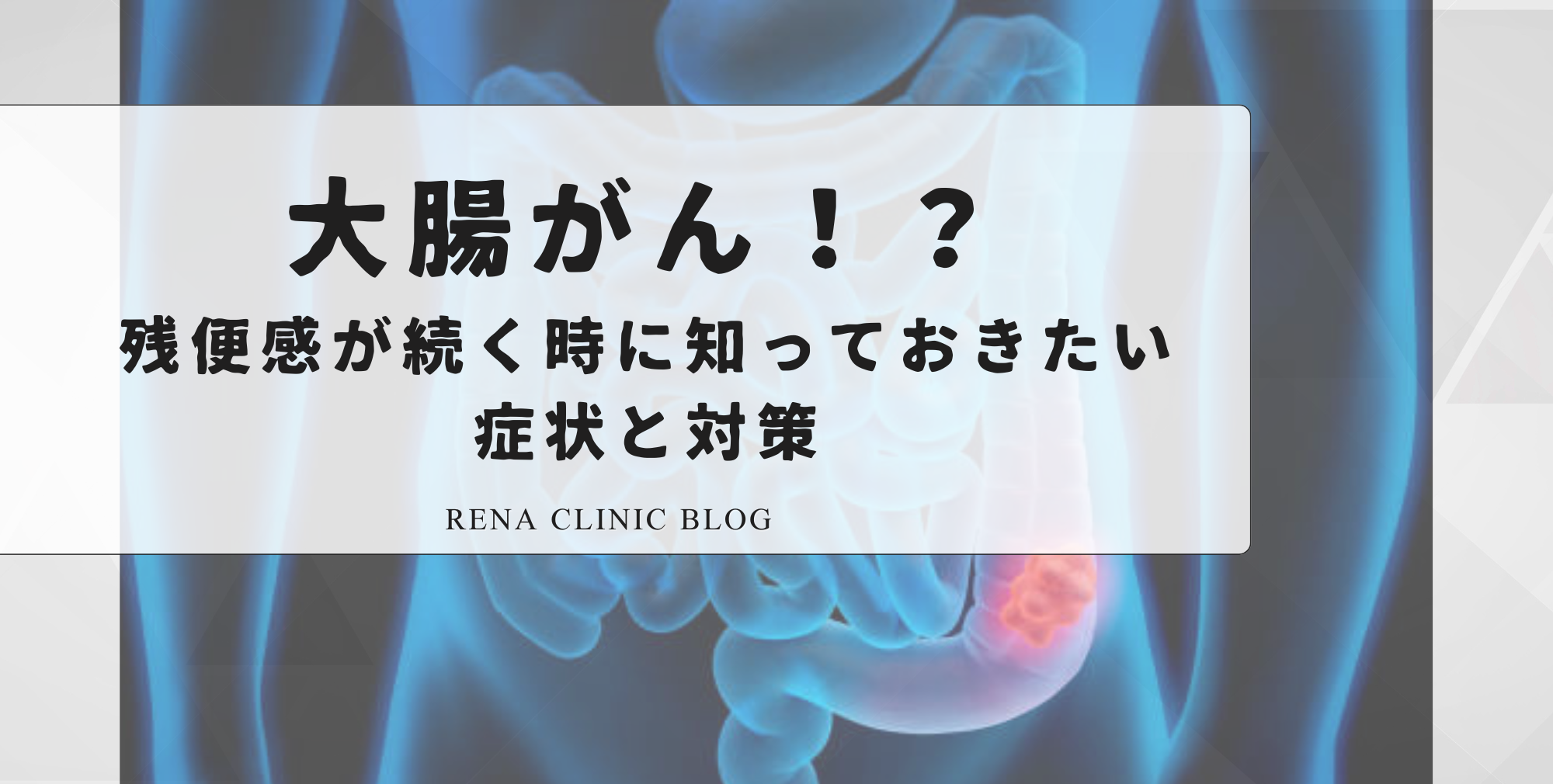
「便を出したのに、どうも残ってる感じがする」「トイレを出てもスッキリしない…」
そんな“残便感”が続くのって、地味につらいですよね。「便秘かな」「ストレスかな」で片付けてしまうことも多いですが、実は残便感が持続するのは大腸癌など重大な疾患の初期サインであることもあるのです。
残便感が“ただの便秘やお腹の調子”で済むものか、それとも注意すべきものかを判断するためには、他の症状・経過・頻度などをきちんと見ることが大切です。
今回は、残便感が続く方に向けて、「どんな場合に心配か」「どんな検査をすべきか」などをわかりやすく解説します。まずは、残便感とは何か、どういう状態が“普通じゃない”かを見ていきましょう。
目次
1. 残便感とは何か?続く原因の基本
「残便感」とは、排便後にも便が残っているような感じ、あるいは排便しても“出し切れていない”という不快感を指します。医学的には「不完全排便感」「排便後の不満感」などとも呼ばれ、便 秘・腸の運動異常・肛門周囲の問題などさまざまな原因で起こります。
秘・腸の運動異常・肛門周囲の問題などさまざまな原因で起こります。
まず、生活習慣や機能的な要因から。便秘がちで硬い便が多いと、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が抑制され、便が腸壁にこびりついたり、腸管が十分に空にならないことがあります。
水分不足・食物繊維不足・運動不足も大きな要因です。また、ストレスや不規則な生活習慣も腸の働きを乱す原因になります。
次に、肛門・直腸の機能異常。排便時に肛門が十分開かない、肛門のしまり具合(括約筋)が異常、不適切なトイレ習慣(我慢する・時間をかけすぎるなど)などが残便感を生じさせます。
さらに、直腸の感覚が鈍くなっていたり、残便があるのを感じても完全に排出する力が弱くなっていたりすることもあります。
そして器質的な原因。腫瘍やポリープが腸管内にできていると、腸管内腔が狭くなり、便の通過がスムーズでなくなるために、残便感や便の形状変化が生じます。
また、炎症性腸疾患や直腸の疾患、過去の手術・癒着なども可能性があります。
つまり、残便感が“続く”ということは、「機能の問題」「生活習慣の問題」「器質的な病変」のどれか、または複数が絡んでいる可能性があるということです。まずはどのタイプかを見極めることが、適切な対応の第一歩となります。
2. 大腸癌における残便感:特徴と他の症状との関連性
残便感が「ただの便秘やお腹の調子」の範囲を超えて、「大腸癌を疑うべき状態」になるには、他の症状との組み合わせ・経過の持続性・排便スタイルの変化などに注意が必要です。
まず、大腸癌で残便感が出やすいのは、腫瘍が直腸やS状結腸など、排便通路に近い部位にできているケースです。
ここでは腸管の腔が狭くなっているため、便が通るときに“引っかかる感じ”や“途中で止まる感じ”があり、完全に排便できないような感覚が残ることがあります。
他の症状として併発しやすいものに以下があります
- 血便・粘血便(便に血が混じる・便器が赤くなるなど)
- 排便習慣の変化(便秘と下痢を繰り返す、便が細くなる)
- 腹痛・腹部膨満感、不快感などの腹部症状
- 貧血や体重減少など、体全体に影響する症状が現れることもあります。進行がんでそうした傾向が強くなることが多いです。
さらに、“残便感が続く期間”が重要です。数週間にわたって改善しない・徐々に悪化する傾向がある、または他の症状が少しずつ積み重なってきているならば、注意が必要です。特に40歳以上、高リスク因子(家族歴・既存ポリープなど)がある人は、残便感があるなら軽く見ずに医師に相談すべきです。
3. 続く残便感=癌ではないケースとの見分け方
残便感があっても、それが必ず大腸癌というわけではありません。多くの人が経験する“普通の不調”であることもあります。
非癌性の原因が多いケースの特徴
- 残便感が日によって違う/お通じが改善するときがある
- 便秘傾向(硬い便・水分不足など)が主体で、生活習慣の改善である程度改善する
- 排便後の時間の経過で“スッキリする”感じが出ることがある
- 他の重大な症状(血便・体重減少・腹痛など)がほとんどない
- 下痢と便秘の交互(刺激・食べ物・ストレスによるもの)があったり、過敏性腸症候群のような機能性の腸の問題が背景にある
見分け方のポイント
- 残便感の頻度・期間:1~2週間で治まるか、それとも数週間以上続くか
- 排便スタイルの変化:便の形・太さ(細くなる・リボン状になるなど)・排便後に“まだ残っている感”が強いか
- 出血の有無・色:血が混じるか・鮮血か・粘液性のものか・黒く・暗い血が混じるかなど
- 全身症状の確認:体重減少・疲労感・貧血または顔色の変化・お腹の張りや痛み
- 家族歴・年齢・既往歴:40歳以上・ポリープやがんの家族歴があるか・炎症性腸疾患の既往など
判断の流れ
- 問診 → 残便感の始まり・持続時間・その他症状の有無を詳しく聞く
- 便の性状のチェック(形・太さ・硬さ・色など)
- 排便習慣・食事・水分・運動など生活習慣の見直しを試みる
- 検査が必要と判断されれば、便潜血検査や大腸内視鏡検査を検討
東京新宿RENACLINICでは、これらの見分けポイントを基に、残便感が続く患者さんに対して、「まずは生活改善と早期の検査」のバランスをとって対応しています。
4. 検査方法と診断プロセス:どう調べるか
残便感が一定期間続いたり、他の疑わしい症状が加わったりした場合、医師はどのように診断を進めるかを知っておくと安心です。
問診と身体診察
まず、残便感がいつから始まったか・どのくらいの頻度か・他の症状(血便・腹痛・便の形・体重変化など)があるかを確認します。また、排便のパターン(便秘・下痢・交互型など)、便の性状(硬さ・太さ・形・色)を確認します。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
最も確実に腸管内を観察できる方法であり、腫瘍・ポリープ・炎症部位を検出でき、組織を採取することで病理診断できます。残便感が続く・便の形が変わる・血便があるなど複数の異常が併存しているときには、大腸カメラ検査を勧められることが多いです。
その他の検査
- CTスキャンや超音波検査などで腸の周囲や他臓器の状態を確認
- 血液検査で貧血・炎症マーカーを調べる(癌が進行していたり出血が続いていると貧血が出ることがあります)
- 内視鏡以外の方法での排便機能検査、肛門直腸の機能検査など
診断後の流れ
- 検査で癌やポリープが見つかれば、その大きさ・部位・浸潤度に応じて治療方針を決める

- 軽度であれば内視鏡的切除などの治療が可能になる場合もあり、進行している場合は手術・薬物療法などが検討される
5. 日常でできる対策と改善のヒント
残便感を軽くする・悪化を防ぐために、日常生活でできることがいくつかあります。続けることで腸の調子を整え、検査のリスクを下げられることがあります。
食事・水分・食物繊維
- 毎日の食事に野菜・果物・全粒穀物など食物繊維を十分に取り入れる。便のかさを増し、腸を刺激することで蠕動運動を促進します。

- 水分をしっかり摂る。便を柔らかく保つことが残便感を軽くする鍵です。特に水・お茶など無色の飲み物が効果的。
- 食生活のバランスを整え、脂肪過多・肉中心・過度の加工食品などが腸に負担をかけないようにする。
排便習慣
- 便意を我慢しない。便意があるときにはトイレに行く習慣をつけること。
- トイレで長時間いきむことを避ける。いきみが腸や肛門に負担をかけることがあります。
- 腹筋を適度に使う運動や姿勢を意識する。特に下腹部・直腸周りの筋肉の働きを助ける運動(歩行・軽い腹筋など)を取り入れてみる。
生活習慣の見直し
- 適度な運動を継続する。ストレッチ・軽いジョギングなどで腸の動きを促す。
- ストレス管理を意識する。ストレスは腸の動きに影響を与えるため、リラックス・睡眠・趣味の時間を持つこと。
- トイレ環境を整える(足を置ける台を使う等、排便姿勢を工夫する)。
継続観察と医師への相談タイミング
- 残便感の変化を日記等で記録する。どのくらいの頻度で・どのタイミングで・どんな便の状態か・他の症状があるか等。
- 改善がみられない・他の異常症状(血便・腹痛・体重減少など)が加わったら早めに医師に相談する。
このような対策を続けることで、残便感が改善することがあります。重篤な病気の早期発見にもつながります。
まとめ
残便感が続くというのは、「単なる便秘」や「お腹の調子が悪いだけ」かもしれませんが、それでも無視すべきではありません。特に残便感が数週間以上続く・便の形や太さが細くなる・血便・腹痛・体重減少など他の症状が併発しているときは、大腸癌の可能性を含めて考える必要があります。早期であれば内視鏡的切除など比較的負担の少ない治療でも十分対応可能なことが多いため、進行を防ぐことができます。東京新宿レナクリニックでは、必要な検査を早期に行い、患者さん一人ひとりに合った対応を心がけています。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。
参考文献リスト
- Shinomiya Y, Kim SH, Kurihara M, et al. Prevalence and clinical significance of evacuation disorders in patients with low anterior resection syndrome. BMC Surgery. PMC
- Bagshaw P, Warusavitarne J, Faiz O, et al. Health‑related quality of life, faecal continence and bowel function in rectal cancer patients after chemoradiotherapy followed by radical surgery. Colorectal Disease. PubMed
- Ní Laoire Á, Fettes L, Murtagh FEM, et al. A systematic review of the effectiveness of palliative interventions to treat rectal tenesmus in cancer. Palliative Medicine. SAGE Journals
- Chow OSI, Law WL, Lee YH, et al. Colorectal cancer. Location dependent symptoms? Colorectal Disease. PubMed





