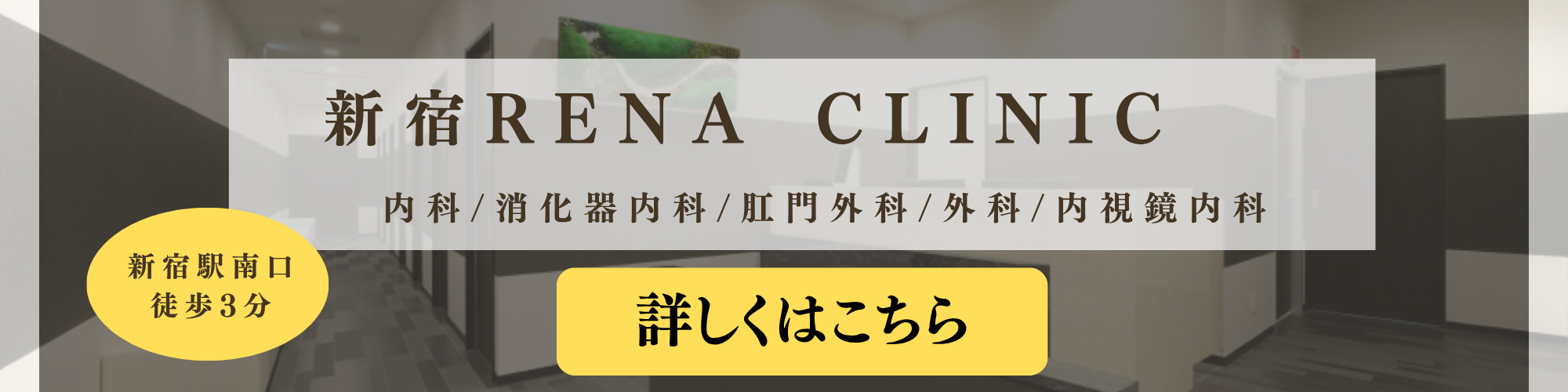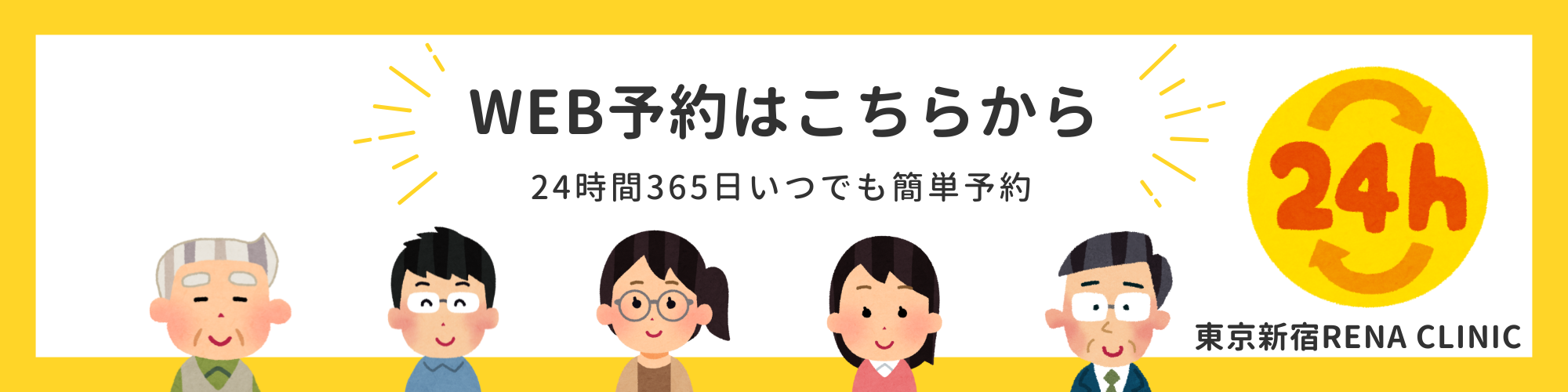お酒を楽しんだり、辛い物で汗をかいたりするのって、仕事や付き合い、友人関係において大切ですよね。
でもその楽しいひとときが、実は「痔」のトリガーになってしまうことがあるってご存じでしょうか?
「あれ?なんか最近お尻がムズムズする」「トイレ行くとき血が・・・?」そんな経験をしている方は、お酒や辛い物との関係を見直してみましょう。
今回は「お酒・辛い物が痔に及ぼす影響」について、できるだけ身近に、わかりやすくお話ししていきます。
目次
1. お酒が痔に与える影響とは?
まず、お酒が痔にどう影響するかを整理しましょう。
- お酒は利尿作用があり、体内の水分を多く排出させます。これにより腸から便が水分を奪われ、便が「硬く・乾燥」しやすく、排便時に“いきみ”が強くなってしまうことがあります。
こうした”いきみ”は直腸・肛門部の静脈にかかる圧力が痔を誘発・悪化させる原因になります。
- お酒を飲むことで血管が拡張しやすいとされ、肛門・直腸部の静脈にも影響を与え、静脈うっ血を起こしやすくなり、痔核の発症・進行を促す可能性があります。
- また、慢性的な大量飲酒では肝疾患(肝硬変など)を伴うことがあり、肝臓からの血流が滞ることで肛門部の血管に負荷がかかるという報告もあります。
つまり、お酒は痔において“直接の原因”とまでは断定できなくとも、間接的な悪化因子として十分に考慮すべき存在です。
つまり、飲む量・頻度・水分補給・排便習慣などをつい見逃してしまうことで、知らず知らずのうちに痔のリスクを高めていることがあります。
2. 辛い物(スパイス・唐辛子類)が痔を刺激するメカニズム
次に、辛い物が痔にどう影響するかを見ていきましょう。
辛さの主役であるカプサイシンは、摂取すると消化管を通過する際に粘膜や腸壁を刺激し、排便時に刺激された便・直腸粘膜が肛門へ来ると“ヒリヒリ”とした違和感を生じることがあります。実際、辛い食事後に肛門部の刺激や「出した後ちょっとしみる」という経験を持つ方は少なくありません。
では、どうして“悪化”する要因となるのか。ポイントは排便習慣・便性状の変化にあります。
辛い物を多く食べると、便が柔らかくなりすぎて下痢気味になったり、あるいは逆に刺激→腸の動きが変化→便秘・不規則な便通になったりすることで、“便の通りが悪い”“いきむ”という状況を招きやすくなります。こうした「いきみ」「便通異常」「腸管の刺激」が痔の発症・増悪の土台となります。
また、辛い物による腸・肛門粘膜の“残留刺激”も無視できません。辛い物の成分が便残留物として肛門部粘膜と接触したとき、痔で既に炎症を起こしている部位では痛み・かゆみを感じやすくなります。
以上を踏まると、辛い物そのものが痔を“発症”させる決定因とは言えないものの、「既に痔がある」「便通が乱れている」「肛門部が敏感な状態である」このような方にとっては“トリガー”となりうるという理解が適切です。新宿RENACLINICでも、辛い物好きの方には「辛さを少し控える」「食後速やかに水・食物繊維でケア」「排便習慣を整える」などをご提案しています。
3. 「お酒×辛い物」の相互作用で痔リスクアップ?
これまで別々に見てきた「お酒」と「辛い物」ですが、併せて摂ることで“痔へのダブルパンチ”となるリスクが高まる可能性があります。
まず、お酒による脱水・便の硬化・血管拡張という“便通悪化/血管負荷増”と、辛い物による腸粘膜刺激・便通変動・排便時肛門部粘膜への炎症刺激という“粘膜負荷/いきみ増”とが加算的に作用することが考えられます。つまり、お酒で便が硬くなっているところに辛い物をぶつけるようなイメージです。
具体的には、飲み会で辛いメニューとお酒を多めに摂った翌日、「便がいつもより出にくい/お尻がヒリヒリする/出血した」といった状態に陥りやすくなります。
さらに、お酒を飲んでいるとトイレで長居したり、座位でダラダラしたりする機会も増え、トイレでの“いきみ時間延長”という痔にとって悪条件となる行動が併発しやすいという点も見逃せません。
したがって、東京新宿レナクリニックでは「お酒を飲みながら辛い物を食べた日の翌日は、便通・肛門ケアをいつも以上に意識しましょう」とお伝えしています。
例えば、飲んだ後にミネラルウォーターや温かめの飲み物を摂る・辛さの強い料理はしばらく控える・食物繊維豊富な軽食をとる・排便タイミングを整える、などが有効です。
4. ライフスタイルでできる痔予防・症状悪化防止のポイント
「まず何をすればいいのか?」という方のために、具体的な生活習慣アドバイスをお届けします。特にお酒・辛い物と痔の関係を踏まえて、次のようなポイントを意識してみてください。
- 水分をしっかり摂る:飲酒時には利尿作用で脱水傾向になりやすいため、1杯のお酒につき少なくとも1〜2杯の水を摂るようにしましょう。水分不足になると便が硬くなり、排便時のいきみが増します。
- 食物繊維を意識する:毎日の食事で十分な食物繊維(1日に25〜30g程度)を意識してください。野菜・果物・全粒穀物などが有効です。便が柔らかく、通りやすい状態を保つことが痔の発症・悪化を防ぐ基本です。
- 辛さの強い料理の頻度・量を調整:どうしても辛い物が好きな方は、辛さを少しセーブする、辛いメニューのあとは食物繊維と水分で胃を休ませる、などの工夫を忘れずに。肛門部に残留刺激を残さないように、温かいお湯に浸かる・座浴を行うのも有効です。
- トイレ習慣を見直す:トイレでは「いきまない」「長居しない」が鉄則です。スマホを持ち込んで長時間座ると、直腸・肛門部に血液が溜まりやすく痔のリスクが高まります。お酒+辛い物の後こそ、この点を意識しましょう。
- 適度な運動・姿勢の改善:長時間座りっぱなし・立ちっぱなしは肛門周辺の血流を滞らせがちです。ときどき立ち上がって軽く動く、腹筋を過度に使わない運動を心掛けることで、静脈うっ血を軽減できます。
- 飲酒・辛い物チェックポイント:飲酒後や辛い物を食べた後に「便の様子がいつもと違う」「お尻に違和感がある」などあれば、早めにケアを。特に痔を既に持っている方は、こうした“アラート”を見逃さないようにしましょう。
これらのポイントを日々実践していくことで、痔の発症・再発・悪化のリスクをぐっと下げることができます。東京新宿レナクリニックでは、症状が出てしまった後だけでなく、こうした「生活習慣からのケア」までご案内しております。
5. まとめ
お酒と辛い物、それぞれが単独でも痔にとって“要注意”の食・飲料要因であり、両者を同時に習慣的に摂取することで、さらに痔の発症・悪化リスクが高まる可能性があります。飲酒による脱水や血管拡張、辛い物による腸・肛門粘膜への刺激、便通の乱れ、排便時のいきみ…これらが負のサイクルとなり、お尻のトラブルを招きやすくなります。とはいえ、辛い物を完全にやめる必要はありませんし、お酒も上手に付き合っていけばそれほど問題ではないもの。重要なのは「量・頻度・その後のケア」であり、トイレ習慣・水分・食物繊維・排便環境を整えることです。健康なお尻ライフのために、ぜひ今日から少し意識を変えてみてください。東京新宿RENA CLINICでは、こうした生活習慣と痔の関係についても丁寧にご説明・ご相談を承っております。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。
参考文献
- [Is there a correlation between dietary habits and hemorrhoidal disease/雑誌名: Diseases of the Colon & Rectum.
- Risk factors for hemorrhoidal disease among healthy young and middle-aged Korean adults /(最初の著者 Lee 他)/雑誌名: International Journal of Colorectal Disease.
- Alcohol and hemorrhoids: Possible links and more/雑誌名: Medical News Today