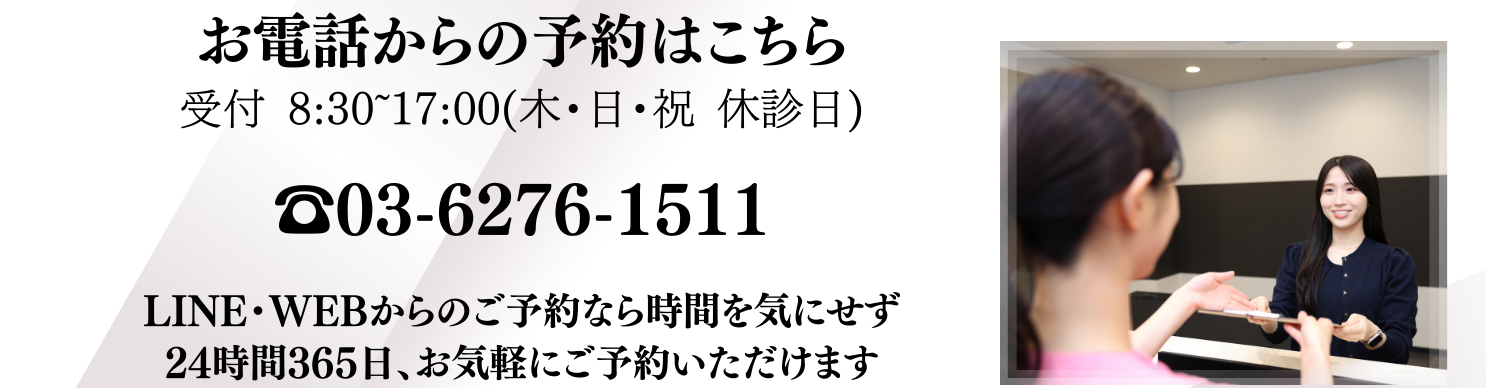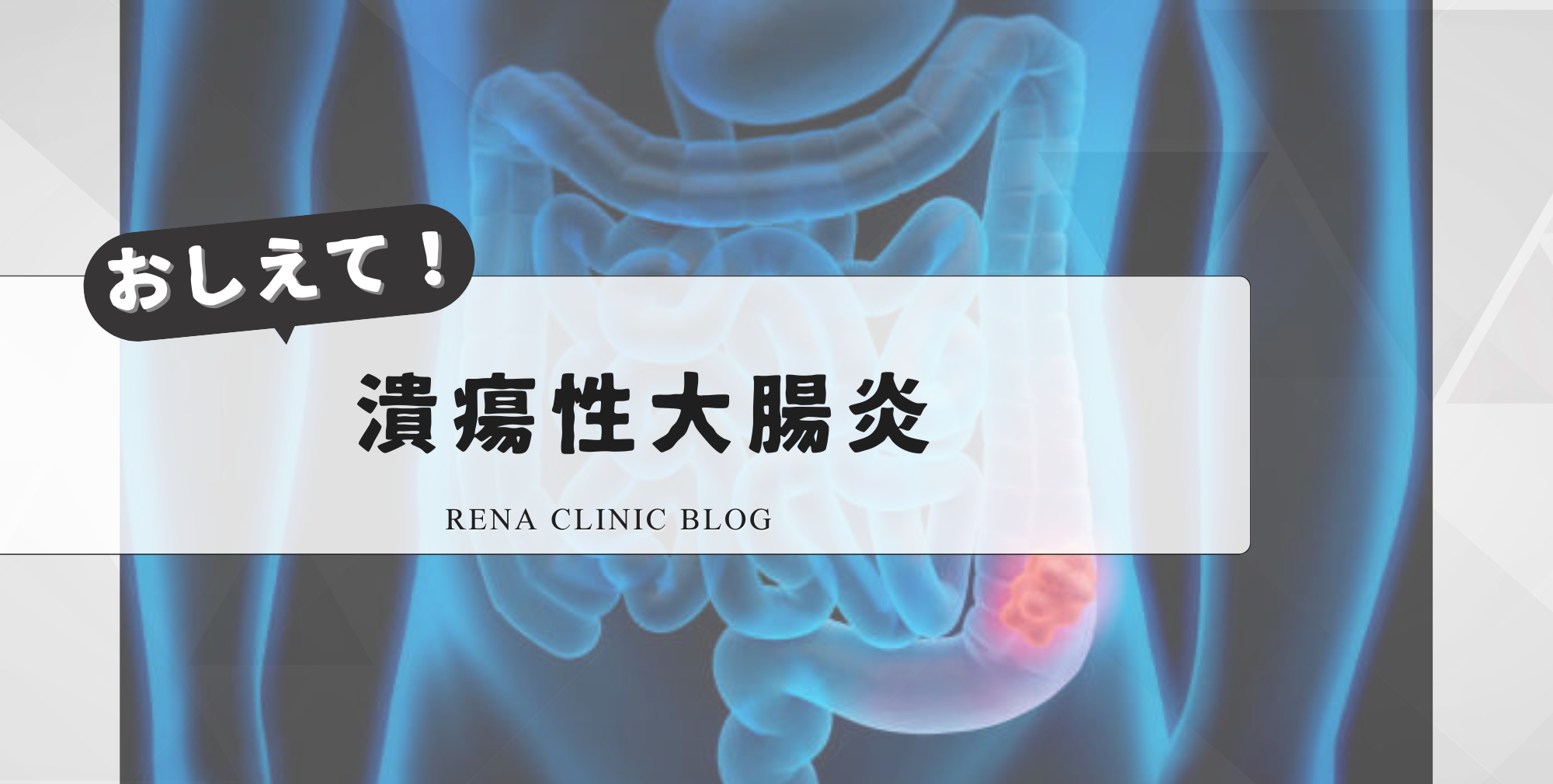
気になる便の悩み、腹痛、血便…もしかして潰瘍性大腸炎かも?そんな不安を抱えている方は多いと思います。
潰瘍性大腸炎は若い世代にも多く見られる慢性的な病気ですが、治療が進んだ今、正しいケアと管理で日常生活に大きな支障なく過ごせるようになりました。
ここでは「潰瘍性大腸炎とは何か」「どうやって診断されるのか」「どんな治療を受けられるのか」を、わかりやすくご説明します。ぜひ最後までご覧ください。
1. 潰瘍性大腸炎とは?
潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が生じる「炎症性腸疾患(IBD)」のひとつです。
症状は直腸から始まり、大腸全体に広がることもあります。日本では指定難病にも指定されており、年々患者数が増加している傾向にあります。
発症年齢は10代後半から30代に多く見られますが、どの年代でも発症する可能性があります。男女差はあまりなく、症状の出方や重症度は個人差があります。
原因は完全には解明されていませんが、免疫機能の異常、遺伝的要因、腸内細菌のバランスの乱れ、環境因子(ストレスや食生活など)が複雑に関与していると考えられています。
潰瘍性大腸炎は、再燃(悪化)と寛解(落ち着いた状態)を繰り返すのが特徴です。そのため治療は「炎症を抑える」ことだけでなく、「寛解状態を維持する」ことも重要となります。
2. 主な症状と経過の特徴
潰瘍性大腸炎の代表的な症状は、血便・下痢・腹痛です。便意があっても出ない「しぶり腹」や、粘液が混ざった便などもよく見られます。
症状の強さや頻度には個人差がありますが、初期には排便回数の増加や便に少量の血が混じる程度というケースも少なくありません。
進行すると、大量の血便、発熱、体重減少、貧血、全身倦怠感などの全身症状が現れることもあります。
また、皮膚炎、関節炎、目の炎症といった腸以外の臓器に炎症が起こる「腸管外症状」も確認されています。
この病気のもう一つの特徴は、「経過が波のように変動する」点です。症状が落ち着いている寛解期と、症状が悪化する再燃期を繰り返します。
そのため、長期的な管理と通院が非常に重要です。患者さんによっては、何年も寛解期が続く方もいれば、数ヶ月ごとに再燃する方もいます。
このような病態に応じて、治療内容や通院間隔を柔軟に調整する必要があります。
3. 診断方法と検査の流れ
潰瘍性大腸炎を診断するには、まず問診によって症状や発症経過を詳しく確認します。

そのうえで、感染症や他の腸疾患を除外するために、血液検査や便培養などの基本検査を行います。
診断の決め手となるのは、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)です。この検査で直腸や大腸の粘膜の状態を直接観察し、炎症の範囲や重症度を確認します。
また、粘膜から小さな組織を採取して、顕微鏡で炎症の特徴を調べることも重要です。
血液検査では、炎症マーカー(CRPや白血球数)、貧血の有無、栄養状態などをチェックし、重症度の判定に活用されます。
さらに超音波検査やCT、MRIなどの画像検査を追加して、合併症の有無を確認することもあります。
潰瘍性大腸炎は、他の疾患(感染性腸炎、クローン病、大腸がんなど)と似た症状を呈することがあるため、慎重かつ多角的な診断が求められます。
東京新宿レナクリニックでは、専門医による内視鏡検査と各種検査データを総合的に評価し、的確な診断を行っています。初めての方でも安心して検査・診察を受けていただける環境を整えています。
4. 治療法(薬物療法・食事療法・手術など)
潰瘍性大腸炎の治療の中心は「薬物療法」です。
最もよく使われるのが、5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤です。これには内服薬、坐薬、注腸薬などがあり、病変の範囲や重症度に応じて使い分けられます。
軽症〜中等症の多くの患者さんにとって有効な治療です。
中等症以上になると、ステロイド(副腎皮質ホルモン)を用いることがあります。炎症を急速に抑える効果がありますが、副作用があるため長期使用は避けられます。
ステロイドを減量していく過程で、再燃しないように免疫調節薬(アザチオプリンなど)や生物学的製剤(抗TNF-α抗体、抗IL-12/23抗体など)を併用することもあります。
その他の選択肢として、白血球除去療法(LCAP)や、最近ではJAK阻害薬など新しい作用機序の薬も登場しています。
重症例や薬でコントロールできない場合、大腸を全摘出する手術が行われることもありますが、近年は薬物療法の進歩によりその頻度は減っています。
治療のゴールは「寛解導入」と「寛解維持」の2つです。症状がない期間をできるだけ長く保ち、再燃を防ぐことが目標です。
5. 日常生活の注意点とケア
潰瘍性大腸炎は、症状が落ち着いている寛解期でも、日常生活での注意が大切です。
特に食生活とストレス管理は、再燃の予防に大きく関わります。食事面では、脂っこいものや刺激物、アルコールなどは控えめにし、消化にやさしい食材を選ぶことが基本です。
活動期には食物繊維を減らし、寛解期には徐々に通常の食事に戻すといった工夫も必要です。また、水分と栄養をしっかり補給することも重要です。
ストレスや睡眠不足は腸の働きに影響を及ぼすため、規則正しい生活とリラックスする時間を意識的に持つことが求められます。軽い運動や趣味の時間を確保することも、心身の健康につながります。
さらに、通院や服薬の継続も大切です。自己判断で薬を中止すると、突然再燃することがあります。
また、発症から長期間経過している方には、大腸がんのリスクが高まるため、定期的な内視鏡検査が推奨されます。
まとめ
潰瘍性大腸炎は、適切な治療と日常のセルフケアを行うことで、長期間安定した生活を送ることが可能な病気です。症状の波があるからこそ、早期診断と継続的なフォローアップが大切です。東京新宿レナクリニックでは、内科・消化器の専門医が在籍し、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの診療を行っています。どんな小さな不調でも、気になることがあれば早めの相談をおすすめします。東京新宿RENACLINICでは、あなたの健やかな毎日を全力で支えます。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。