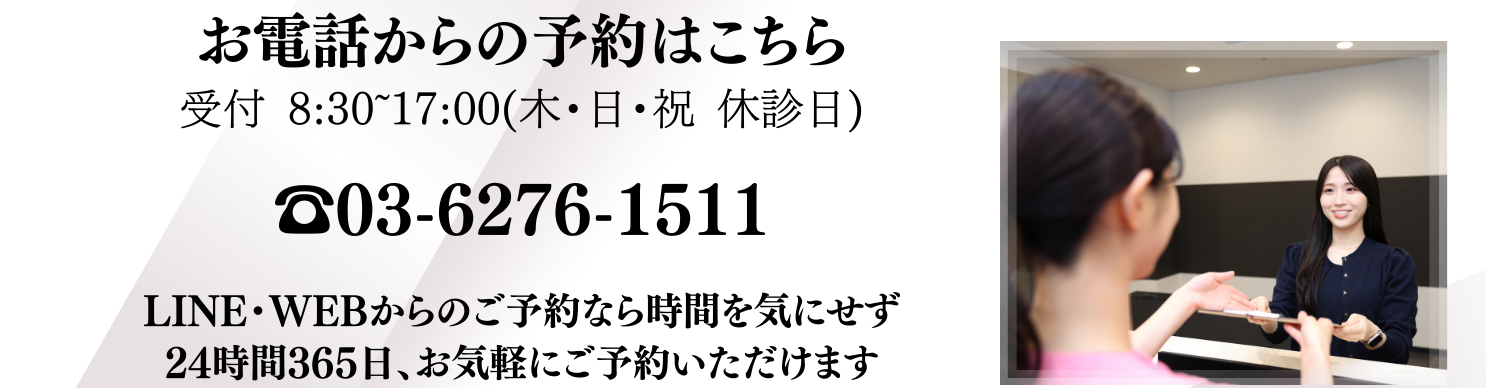「何を食べたらいいのか分からない…」「食事が怖い…」潰瘍性大腸炎を抱える方からよく聞くお悩みです。
食べ物が症状に直結しやすいこの病気では、食事は治療と同じくらい大事な自己管理のひとつ。
でも、ネットの情報が多すぎて混乱していませんか?ここでは“潰瘍性大腸炎と食事の基本”を、医療的な視点からわかりやすくご紹介します。
1. 潰瘍性大腸炎における食事の役割
潰瘍性大腸炎の食事療法は、直接的に病気を「治す」ものではありませんが、症状を安定させるために非常に大きな役割を果たします。
食べ物が腸を通る以上、腸に炎症がある状態では、食事によって刺激や負担が加わり、症状が悪化する可能性があるのです。
特に活動期(症状が出ている時期)には、腸の粘膜が敏感になっているため、食事内容に注意が必要です。脂っこいものや繊維の多い食材、刺激物などは炎症を悪化させることがあり、個々の体調に応じた調整が重要になります。
一方、寛解期(症状が落ち着いている時期)には、栄養バランスを重視した食事を心がけることで、再燃を防ぎ、健康な腸内環境を保つことができます。栄養不足は免疫機能の低下を引き起こし、再発リスクを高めることもあるため、寛解期でも食事の質はとても大切です。
ただし、「潰瘍性大腸炎の人はこれを食べなければならない」「絶対にこれはダメ」といった明確なルールがあるわけではなく、症状の程度やその人の消化吸収力によって個人差があります。だからこそ、自分の体と向き合いながら、適切な知識を身につけることが食事管理の第一歩になります。
2. 活動期と寛解期で異なる食事の考え方
潰瘍性大腸炎の特徴は、症状が出る「活動期」と症状が落ち着く「寛解期」が繰り返されることです。このサイクルに合わせて食事内容を調整することが基本となります。
【活動期】
この時期は、腸の炎症が強く、腹痛・下痢・血便などの症状が出やすい状態です。
腸を刺激しないように、「低脂肪」「低残渣(繊維の少ない)」「消化の良い」食品を選ぶ必要があります。
たとえば、白粥、うどん、すりおろしたリンゴ、豆腐などが代表的です。乳製品や生野菜、海藻類、揚げ物、スパイス類は避けた方が無難です。
【寛解期】
症状が安定している寛解期では、少しずつ通常の食事に戻していくことが可能です。
ただし、「何でも食べていい」わけではなく、腸に負担をかけない食習慣を続けることが再燃予防につながります。
この時期には、栄養バランスを重視した食事(たんぱく質・ビタミン・ミネラルの補給)を意識し、体力や免疫力の維持に努めます。
それぞれの時期で「正しい食事」は変わりますが、共通して大切なのは「自分に合っているかどうか」を見極めること。何を食べると調子が良いのか、悪化するのかを記録しておくと、体との向き合い方が見えてきます。
3. 食べてよいもの・避けたいもの
潰瘍性大腸炎の食事管理でよく聞かれるのが、「結局、何を食べたらいいの?」という疑問です。ここでは、活動期・寛解期に分けて、基本的な目安をご紹介します。
【活動期におすすめの食材】
- 白粥、うどん、そうめん
- 絹ごし豆腐、卵、白身魚の煮物
- すりおろしリンゴ、バナナ
- カボチャ、にんじん(やわらかく煮る)
- ポタージュスープ
【避けたい食材】
- 揚げ物、脂の多い肉類
- 生野菜、根菜の固い部分、海藻類
- 香辛料の多い料理(カレー、キムチなど)
- アルコール、カフェイン(コーヒー、緑茶など)
- 牛乳、チーズなどの乳製品(個人差あり)
【寛解期には】
寛解期には、制限を少しずつ緩めながら、栄養をしっかり摂ることがポイントになります。玄米や雑穀米も、様子を見ながら取り入れることができます。
たんぱく源としては、鶏むね肉、鮭、納豆などがおすすめです。
ただし、どんな食材でも「個人差」が大きく、人によってはバナナで下痢が悪化することもあります。大切なのは、少量ずつ試しながら、自分の「食べても大丈夫なものリスト」を作っていくことです。
栄養補助食品や腸にやさしいレシピを活用するのも良い選択肢です。
東京新宿RENACLINICでは、食事面からの症状コントロールを重要視し、医師・管理栄養士による毎日の食生活指導を行っています。
4. 食事に関するよくある質問と誤解
潰瘍性大腸炎と食事については、インターネットやSNSにさまざまな情報があふれており、かえって混乱してしまうことも少なくありません。
ここではよくある質問と、それに対する正しい理解をご紹介します。
Q.「潰瘍性大腸炎は絶食が一番いいの?」
A. 一部の重症例では一時的に絶食が必要になることもありますが、基本的には“食べながら治す”方針が中心です。必要な栄養が足りないと、腸粘膜の修復も遅れてしまいます。
Q.「牛乳や乳製品は絶対NG?」
A. 牛乳で下痢をする方は避けた方が良いですが、必ずしもすべての患者さんがダメというわけではありません。ヨーグルトや乳酸菌飲料が体に合う人もいます。
Q.「サプリメントや栄養補助食品は使ってもいい?」
A. 栄養が不足しがちな方には、医師と相談のうえで適切なサプリを取り入れるのもひとつの方法です。ただし、自己判断での多量摂取は避けましょう。
Q.「ずっと制限食じゃなきゃいけないの?」
A. 寛解期にはある程度食事の幅を広げることができます。症状に合わせて食材を選びながら、楽しめる食生活を目指しましょう。
5. 続けやすい工夫とサポート体制
潰瘍性大腸炎の食事管理は、「継続」がとにかく大切です。ただ、毎日のこととなると、負担に感じたり、飽きてしまったりするのも仕方ないこと。
ここでは、無理なく続けるための工夫をご紹介します。
まず、「完璧を目指さない」こと。多少の失敗や外食があっても、それが原因で再燃するとは限りません。
大事なのは、“普段の食事”の積み重ねです。7〜8割程度を意識するだけでも、腸への負担はかなり軽減されます。
次に、「レパートリーを広げる」こと。ネットには潰瘍性大腸炎向けのレシピが多数あり、食事制限中でもおいしく食べられる工夫がたくさん紹介されています。
例えば、ノンオイルの蒸し料理や、具材を選んだスープ、豆腐を使ったアレンジ料理などは、腸にやさしく満足感も得られます。
また、調子が悪い時の「備え」として、レトルトの低残渣食や栄養補助食品をストックしておくのもおすすめです。
食欲がない時でも最低限の栄養を確保でき、安心感にもつながります。
まとめ
潰瘍性大腸炎の食事は、症状を安定させるための大切な自己管理の一部です。活動期と寛解期で食べ方を変えながら、自分に合ったスタイルを見つけることがポイントになります。制限が多いと感じるかもしれませんが、工夫次第で楽しく続けることは可能です。東京新宿RENACLINICでは、管理栄養士や医師によるサポート体制を整え、患者さまが無理なく続けられる食生活を一緒に考えていきます。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。