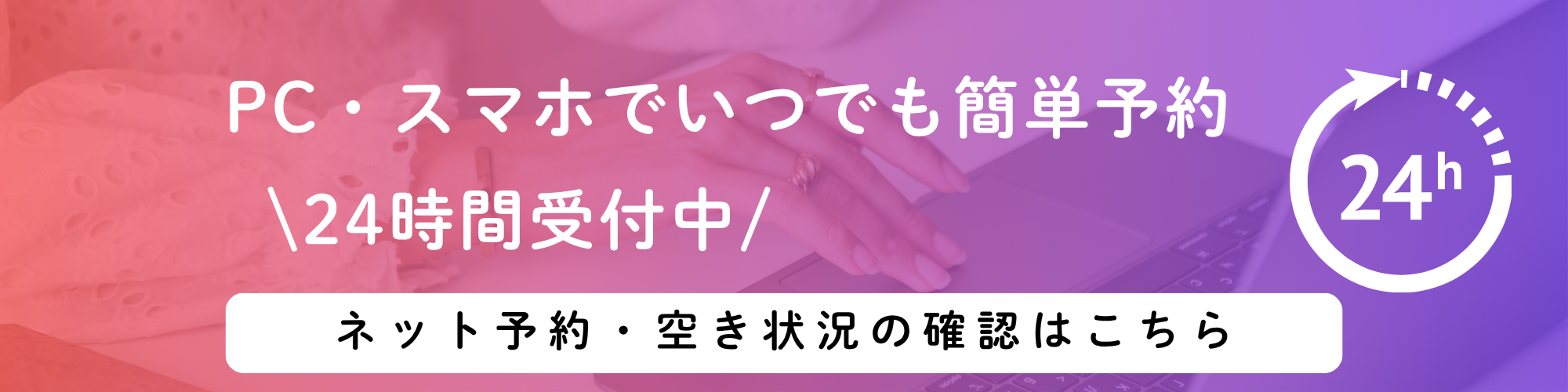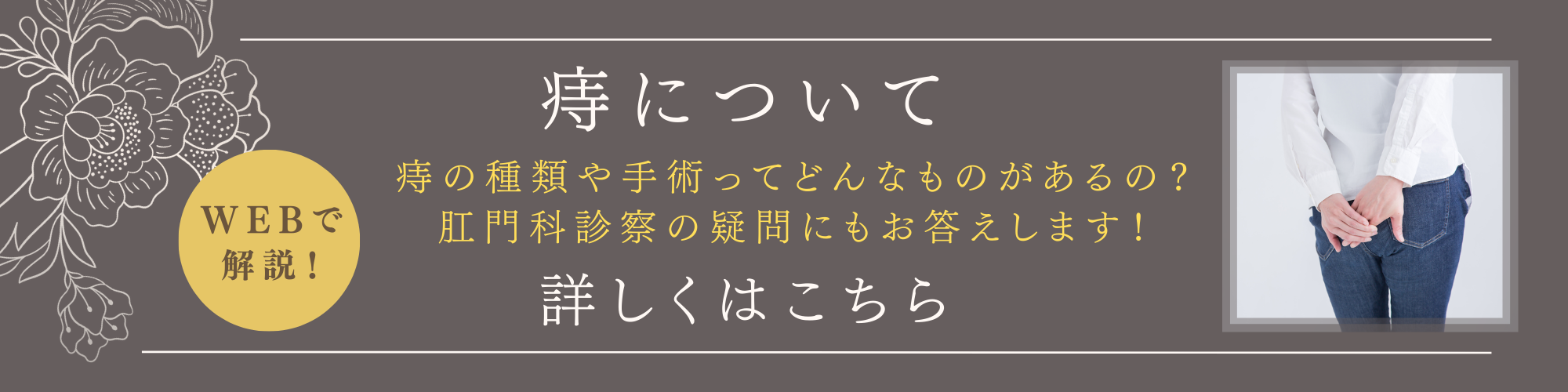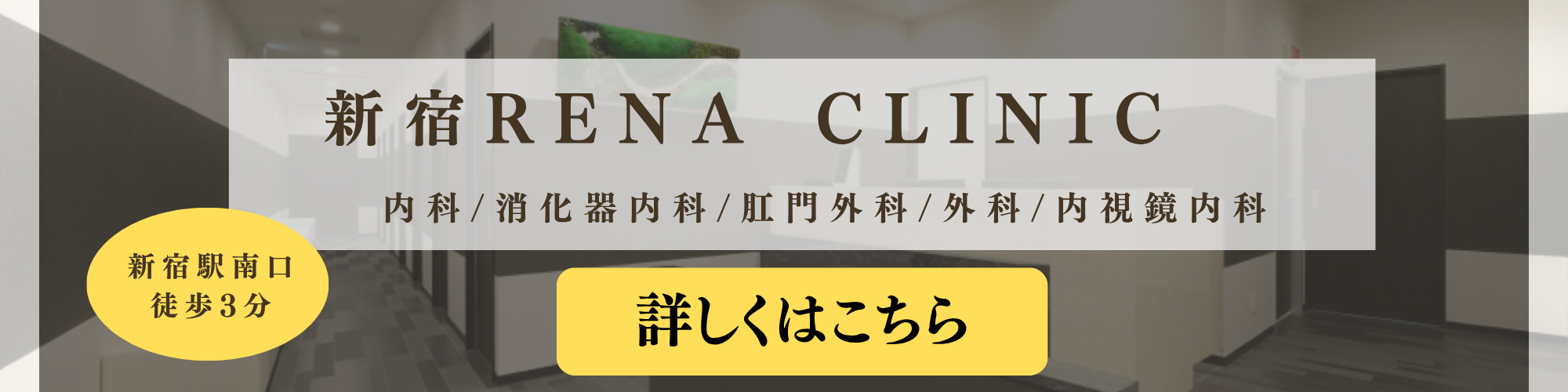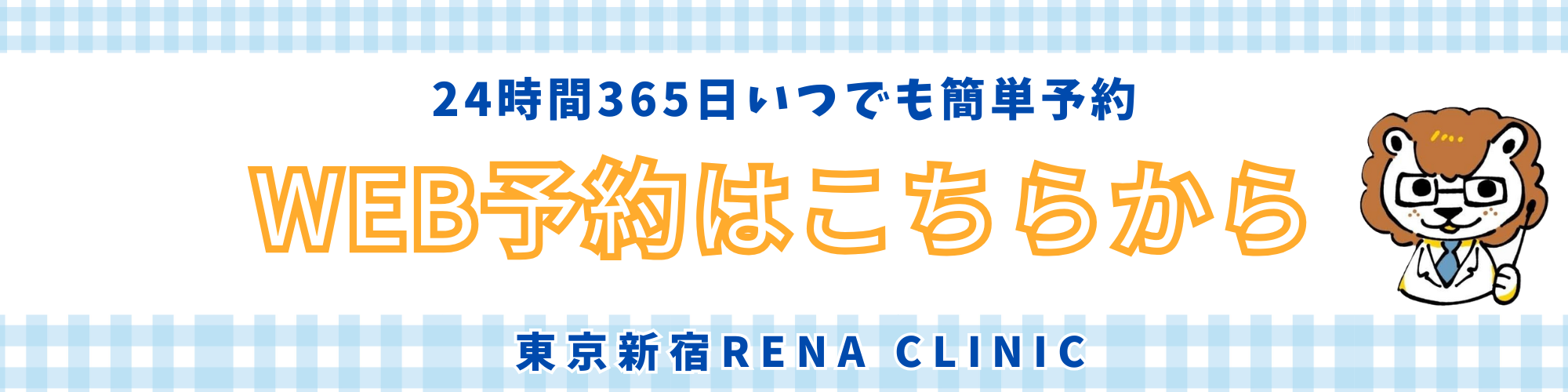便器に血がついていたり、トイレットペーパーに鮮血が付着していたりすると、「これは大丈夫?」「病院行ったほうがいい?」と不安になりますよね。
便器に血がついていたり、トイレットペーパーに鮮血が付着していたりすると、「これは大丈夫?」「病院行ったほうがいい?」と不安になりますよね。
しかも「肛門科」「内科」「消化器内科」などどこを受診したら良いのか迷ってしまう方も少なくありません。
今回は、どの科を選ぶべきか、どんな症状なら“肛門科”、どんな症状なら“内科(消化器内科)”を受診した方がよいか、
そして受診前に自分で確認できるポイントを分かりやすく解説します。
目次
1. 血便って何?鮮血・暗血・混ざり方で変わる原因
「血便」と言っても一口に同じではなく、色・量・混ざり方・出るタイミングなどで“どのあたりから出血しているか”のヒントになります。まず理解しておきたいのが次のような点です。
色の違い
- 鮮やかな赤い血:肛門・直腸・下部大腸近辺からの出血である可能性が高い。
- 黒っぽいタール便(メレナ):上部消化管(胃・十二指腸)からの出血が示唆される。
- 混ざった血・便の中に赤み:大腸中〜上部、もしくは腸管内のどこかで出血していて便と混ざって出てきている可能性。
出るタイミング・量・伴う症状
- 排便時に強く出る:痔(内痔核・直腸裂孔)など肛門部位の出血をまず疑う。
- 血が混ざって毎回出る・便通の変化がある・体重が減っている等:腸管の上部・中部・大腸の炎症・腫瘍などの可能性も。
- 少量でも出血が続く・便潜血検査陽性など:検査・精査が必要なケース。
このように、血便という症状を単純に「痔だろう」で終わらせずに、「どこから・なぜ出ているか」の視点を持つことで、肛門科・内科どちらに行くかの選択肢が見えてきます。
2. 肛門科を受診すべきケース・内科(消化器内科)を受診すべきケースの見分け方
どちらの科を受診すべきかを迷ったとき、自分の症状を整理して“どちらが可能性として高いか”を探ることが大切です。以下に具体的な見分け方を紹介します。
■ 肛門科受診がまず適しているケース
- 排便後すぐ、鮮血がトイレットペーパーに付着する・便器にポタッと落ちるだけの出血。
- 血の量は少なめ、痛み・肛門の違和感・痔核や直腸裂孔の既往がある。
- 便通に大きな変化はない、体重減少・夜間発汗・貧血など全身症状がない。
- 排便時に強くいきむ・便秘・長時間トイレに座る習慣がある。
これらのうち多数該当すれば、“まず肛門部の疾患”を疑い、肛門科を受診するのが現実的です。
痔であれば、生活習慣改善・保存治療・外来処置で対応可能なことが多いです。
ガイドラインでも「痔と思われるがアラーム症状がなければ肛門科的保存療法をまず行う」旨の記載があります。
■ 内科(消化器内科)受診が適しているケース
- 血便が便の中に混ざる・黒っぽくなる・血の量が多め。
- 便通習慣の変化(便秘→下痢・細長便・残便感)、体重減少、倦怠感・貧血がある。
- 家族に大腸がんの既往がある・自分が50歳以上・便潜血検査陽性。
- 排便時以外にも腹部の違和感・膨満感・腹痛・夜間の症状がある。
- 排便後鮮血のみ出るわけではなく、「何となく」血が混ざっていた・出血の原因が明らかでない。
このような場合には、「大腸・直腸・腸管の中」からの出血、さらには「大腸がん・ポリープ・炎症性腸疾患」の可能性も考慮し、消化器内科(大腸内視鏡を扱える施設)を受診することが望ましいです。ただし、肛門科と消化器内科のどちらも対応しているクリニックがもっともよいと思われます。東京新宿レナクリニックはいずれも対応しております。
3. 実際にどちらを選べばいい?受診のタイミングと「血便 受診すべきサイン」
実際に誰もが迷いがちな「どこに行くか」の判断。ここでは受診のタイミングと“肛門科/内科を選ぶ目安”を整理します。
■ 受診を早めに考えたほうがいいサイン(アラームサイン)
- 鮮血・黒色便が 反復している、あるいは 1回でも大量出血 があった。
- 血便に加えて 体重減少・貧血・倦怠感・夜間発汗・食欲低下 がある。
- 便通の習慣が最近変わった(細くなった便、回数の増減、残便感、便秘から下痢に変化)など。
- 年齢が50〜60歳以上、または家族に大腸がん既往のある方。
- 出血原因として明らかな痔・裂孔などが疑えない(例えば血の量が多い、便と一緒に混ざっている、痛みがない等)。
- 保存療法(生活習慣の改善・便通改善・痔治療)をしても 2〜4週間以上改善しない。
これらのサインがあれば、肛門部疾患の可能性だけでなく腸管中・大腸からの出血も視野に入れ、消化器内科(大腸内視鏡対応)あるいは直腸・大腸専門外来への受診をおすすめします。
■ 肛門科を選んでも良い目安
- 出血が鮮血少量・排便直後・痛みや肛門の違和感(痔核・肛門裂孔の既往)あり。
- 便通・体重・全身症状に大きな変化なし。
- 便中に血が混ざる感じではなく、「拭いたら血」という典型的な痔パターン。
このような場合には、まず肛門科的な診察・保存治療(便通改善・食事繊維・座浴・薬)で改善を図るのが適切です。ただし “改善しない・再発” が続く場合には、必ず精査が必要です。
当院では受診時に上記を確認し、必要に応じて大腸内視鏡を含む消化器専門の検査をスムーズにご案内しています。
東京新宿RENA CLINICでは、血便を見逃さずに肛門科、内科いずれの場合も対応しています。
4. 受診したら何を調べる?問診・検査・流れのご案内
血便で受診した後、どのようなステップで診察・検査が進むかを知っておくと安心です。
■ 問診・既往歴の確認
事前にWEB問診をしっかりと行っていただきます:
- 出血の色・量・便と一緒か別か、トイレットペーパーに付くか便器に直接落ちるか。
- 血便以外の症状:便通習慣の変化(便秘・下痢・交互)、体重変化、倦怠感、夜間発汗、食欲低下。
- 既往歴・家族歴:痔核・肛門裂孔・大腸ポリープ・大腸がん家族歴。
- 便の形や頻度、便を出す際のいきみ具合・排便所要時間・便秘・下痢の有無。
- 薬の服用歴・ anticoagulant/抗血小板薬使用・出血傾向。
この問診で「痔に典型的」「腸管中疑う」「大腸がんリスクあり」などの分類が初期に行われます。
■ 身体診察・初期検査
- 肛門・直腸部の視診・触診・肛門鏡(必要時)で痔核、裂孔、肛門腫瘤を確認。
- 血液検査:貧血(ヘモグロビン低値)、鉄欠乏性貧血、炎症反応など。
- 便培養(必要時)。
- 下部消化管・腹部の診察で腫瘤・腹部膨満・しこりなどの有無を確認。
■ 内視鏡検査・追加検査
血便の原因が明確でない場合
- 大腸内視鏡:ポリープ・腫瘍・炎症性腸疾患を直接観察・組織採取。
- 肛門部鏡(肛門鏡・直腸鏡):肛門裂孔・痔核・直腸腫瘍の確認。
「肛門科的出血と思われても、腸管内の重要疾患を見逃さないために大腸鏡検査を検討すべきことが多いです。
■ 診断・治療方針
検査結果に応じて
- 痔核・直腸裂孔:便通改善・保存療法・外来処置(結紮・硬化療法)など。
- 大腸ポリープ:内視鏡的切除。
- 大腸がんや炎症性腸疾患:専門紹介・手術・抗炎症治療・化学療法など。
当クリニックでは、早期発見につながるよう、症状に応じて適切な専門医紹介・フォローアップをご案内しております。
5. まとめ:血便を“放っておかない”習慣を
血便は、大腸・直腸・腸管中からの出血=重大な病気のサインである可能性があります。鮮血かどうか・便通の変化・体重や倦怠感など“伴う症状”があるか・家族歴や年齢リスクがあるかをセルフチェックすることが、適切な科を選ぶ第一歩です。そして、肛門科でよければスムーズに処置が進みますし、内科(消化器内科)で専門検査へ進むべきなら、早めの受診が安心につながります。血便というサインを軽く見ず、「行って良かった」と思える一歩を。東京新宿レナクリニックでは、皆さまの安心を第一にご対応いたします。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。
参考文献
- Hira Imran et al. Lower Gastrointestinal Hemorrhage. JAMA. 2015.
- Numans ME. The Dutch College of General Practitioners guidelines on “Rectal bleeding”: a realistic view of a warning sign. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009.
- Wald A. et al. ACG Clinical Guideline: Management of Benign Anorectal Disorders. Am J Gastroenterol. 2021;116(10):1987‑2008.
- ASCRS Handbook – Management of Hemorrhoids. Diseases of the Colon & Rectum. 2024.
- Kairaluoma M. Examining a patient with rectal bleeding. EBM Guidelines. 2024.